
1月14日、松江の「一畑百貨店」が65年の歴史に幕を閉じた。直近の売上高は、最盛期2002年の108億円から6割減の43億円、県内唯一だった百貨店の閉店により島根は山形、徳島に続く3番目の「百貨店のない県」となった。長く親しまれてきた地域一番店の閉店が地元経済界に与えるインパクトは大きい。とは言え、その不在が実際の消費行動に与える影響は特定需要層を除けばミニマムだ。そうであるがゆえの閉店であることに構造的な問題がある。
18日、茨城県警は雇用調整助成金の不正受給の疑いで水戸京成百貨店の元幹部社員らを家宅捜査した。営業不振による赤字を回避すべく勤務データを改ざん、雇調金3億円を不正受給したという。そう、百貨店の苦境は “地方” だけの問題はない。郊外はもちろん都市部の市場縮小も止まらない。府中(伊勢丹)、相模原(伊勢丹)、港南台(高島屋)など、首都圏の中核都市でも閉店が相次いだ。渋谷の東急本店、新宿の小田急本館も既存業態を見限っての “再開発” に着手済みだ。
構造要因は3つ、生産年齢人口の減少、中間層マーケットの縮小、消費購買行動の変化である。百貨店市場はピークとなった1991年の9.7兆円から2022年には4.9兆円へ、店舗数も1999年の311店から180店(2023年11月)へ縮小した。“ワンランク上” を具現するアイコンとしてのオーラは色褪せた。この30年間の停滞が百貨店の主力ラインである “ベターゾーン” を求めるモチベーションを希薄化させたとも言える。
一方、コロナ禍の反動もあり百貨店各社の業績は前年比ベースで回復基調にある。株高、円安、インバウンドの戻りが高額品消費を押し上げる。しかしながら、本質的な需給調整は終わっていないとみるべきだ。確かに富裕層市場の開拓余地は大きい。しかし、この市場は一定の需要量を越えると極端にパーソナライズしてゆく。横並びは通用しない。富裕層未満の市場も同様だ。一律のベターゾーン・マーケティングは依然として供給過剰状態にある。したがって、遍在し、細分化されたニーズをいかに掬い上げるか、言い換えればパーソナルな “らしさ” のリアルな共感をいかにマーチャンダイジングするかが鍵となる。百貨店という一括りの業態を無意味にすることが次世代百貨店の方向性であり、規模化への誘惑を捨てることが出発点となろう。

2024年1月1日、日本列島が抱える最悪の自然災害リスクが能登半島において現実のものとなった。犠牲になられた方に深く哀悼の意を表すとともに被災地の日常の回復を願うばかりである。他人事ではない。首都圏直下や南海トラフ地震も「30年以内に70~80%の確率」で発生するとされる。つまり、今、まさにこの場所、この時かもしれない。果たして私たちは東日本大震災が突き付けた課題にどこまで本気で向き合ってきたか、時間の経過とともにリスクに対する過小評価が進んでいないか、今一度、まっとうに自然の力を恐れる必要がある。
巨大地震の発生は1日16時10分、気象庁は直ちに大津波警報を発令、避難を促した。しかし、半島という地理的な条件、寸断された道路、複雑な地形に点在する集落、通信障害、止まない余震、これらが被災実態を把握するうえでの障害となった。官邸の特定災害対策本部が非常災害対策本部へ “格上げ” されたのは発生から7時間以上が経過した23時35分、被災地からの要請を必要としない “プッシュ型支援” を開始したとの発表は翌2日の午後、自衛隊の投入は2日に1千人、3日に2千人、、、5日に5千人と逐次投入となった。
発生から “72時間” が勝負だ。国土の危機を検知するシステム、現場での指揮系統、初動のオペレーションは適切だったのか、評価は分かれる。とは言え、4日午前には海上自衛隊の揚陸艦による海路からの輸送もはじまった。自衛隊、消防、警察をはじめ全国自治体からの支援も本格化しつつある。初動対応の在り方はいずれ検証されるはずだ。まずは不明者の捜索と被災者の生活支援に全力をあげていただきたく思う。
原発の安全基準も検証が必要だ。志賀原発の揺れは設計上の想定を上回った。放射線監視装置は15ヶ所でダウン、住民避難路は通行止めとなり、外部電源機能は一時的に失われた。流出した油量の数値や敷地内水位の値も発表後に修正、訂正された。北陸電力は “安全上問題ない” と声明したが、かつて同社がまさにここで発生した臨界事故を長期にわたって隠蔽したことを想起した人も少なくないだろう。それだけに、4日の会見、原発の安全性について見解を求めた記者に対し、無言のまま背を向け、立ち去った岸田首相にはがっかりだ。例え、会見終了のアナウンスの後であってもトップとしての責任と覚悟を自らの言葉で表明すべきであった。対話を拒否した彼の姿が残したものは賛否を越えての失望だ。

12月20日、ダイハツ工業は64車種、3エンジンの認証試験で不正行為があったと発表、OEM供給車も含め全車種の出荷と生産を停止した。4月のドアトリム、5月のポール側面衝突試験に加えての新たな不正発覚に対して、調査を担当した第三者委員会は「不正対応の措置を講ずることなく、短期開発を推進した経営の問題」と断じた。操業停止の長期化は避けられずサプライチェーンと地域経済に与える影響は大きい。
不正が急増したのは2014年以降、トヨタ向けのOEM供給が増えた時期と一致する。トヨタも同日付けのリリースで「2013年以降、小型車を中心にOEM供給車を増やしており、これがダイハツの負担となっていた可能性がある」としたうえで「ダイハツの再生を全面的にサポートする」と表明した。トヨタグループでは日野自動車や豊田自動織機でも品質不正が発覚しており、親会社トヨタ自動車のガバナンスがあらためて問われる。
とは言え、ダイハツの不正は1989年から、日野自動車は2003年頃から、豊田自動織機も2008年頃から、と各社の不正はまさに常態化していたと言っていいだろう。もちろん各社そして親会社のガバナンスに課題はあるし、生産計画、生産体制、生産管理の在り方も問われる。これらはまさに “経営の問題” である。しかしながら、果たして “個” に帰すべき問題はないか。
組織や権威に委縮し、媚び、それをもって自己を正当化する風潮がまん延していないか。低位安定に甘んじ続けたこの30年、至る所で “内向き化” が進行し、多くの “個” もそこに安住した。それは自己防衛であり処世術であるのかもしれない。しかし、そうあり続ける限り、身内に閉じた世界から抜け出すことは出来ない。ダイハツに固有の問題ではない。私たち一人ひとりがそれぞれの立場において、停滞する現状に巣くう不正や不合理に抗うことが改革と再生への第一歩であり、唯一、それが正気と成長を取り戻す近道となる。
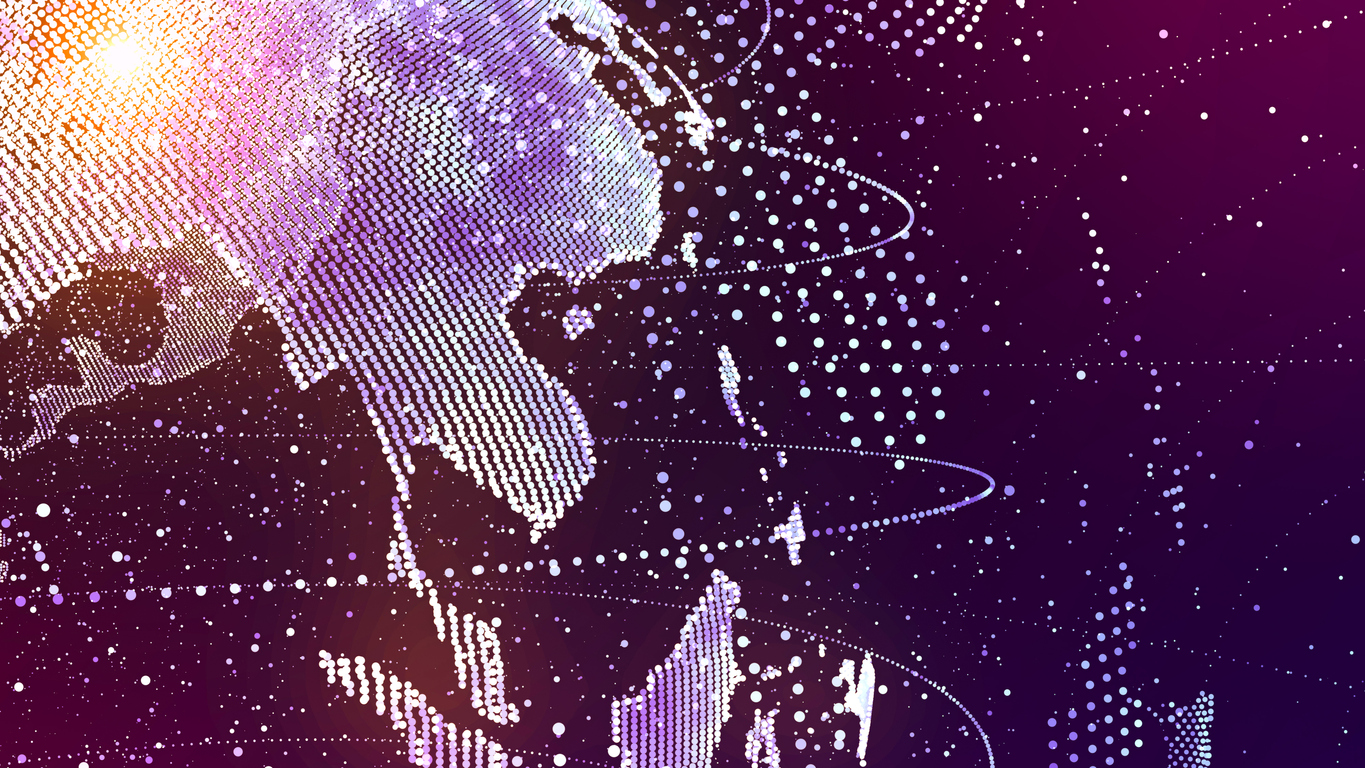
12月17日、日本ASEAN友好協力50周年特別首脳会議が開催、岸田氏は中国を念頭に「日本はASEAN諸国の平和と安定のパートナーとして、法の支配にもとづく自由で開かれたインド太平洋(FOIP)を推進する」と表明したうえで、共同ビジョンに「海洋安全保障協力を含む安全保障協力を強化する」との文言を書き込んだ。
日本、フィリピン、ベトナム、インドネシアは中国と海洋領有権で対立する。日本はこの4月、非軍事に限定された政府開発援助(ODA)とは別に安全保障分野における資金協力の枠組み「政府安全保障能力強化支援(OSA)」を創設、同様の問題を抱える国との連携強化をはかりたい考えだ。しかし、彼らにあっても対中国政策には温度差があり、米中対立には中立的でありたいというのが本音である。OSAはあくまでも「二国間の問題」であるとされ、共同ビジョンへの明記は見送られた。
日本とASEANとの関係は半世紀を経て大きく変わった。8月に発表された「日ASEAN経済共創ビジョン」に記されたとおり両者は公正で互恵的な経済共創の実現を目指すパートナーであって、既に支援する側と支援される側という関係ではない。否、もはや日本は選ばれる立場にある。筆者は先週、久しぶりにインドネシアを訪問した。ジャカルタ名物の渋滞は相変わらずで日本車のシェアも高い。しかし、明らかに中韓勢の存在感が増している。街を走り回るEVタクシーはBYD(中国)ブランドであり、イオンモールの催事スペースに並べられたクルマはHYUNDAI(韓国)のEV、“IONIQ 5”だ。
さて、筆者のインドネシア出張の目的は政府公認のハラール認証機関LPPOM MUIとの日本における独占代理契約の調印である※。インドネシアは人口2億4千万人を擁する内需型の成長市場であるが、資源やインフラ分野を除くと日本勢は出遅れている。イスラム教にもとづく生活習慣や文化の違いが要因の一つであるが、今回の提携を通じて、これらについても日本語でサポートできる体制を整えた。懸念は無用だ。そうそう、現地の外食チェーンのスタッフはサンタの帽子をかぶっていたし、商業施設のクリスマスイベントは親子連れでいっぱいだ。あれ?とも思ったが、みんな屈託なく楽しんでいる。敷居は意外に高くない。是非とも新たな可能性にチャレンジしていただきたい。
※LPPOM MUIとの業務提携について:株式会社矢野経済研究所、LPPOM MUIと「ハラール認証代理業務」に関する独占契約を締結(2023年12月14日)

政府肝入りの「異次元の少子化対策」の財源が明らかになりつつある。政府は2024年度末から児童手当の支給対象を現在の中学生から高校生へ拡大させることを決定しているが、これに合わせて高校生世代がいる世帯を対象に所得税と住民税の扶養控除の適用範囲を一律に引き下げる。これは高校生への支援が他に対して手厚くなることへの措置であると説明されるが、子育て世代間における “アメとムチ” 的な発想に “異次元の” という表現はすっかり色褪せる。
少子化対策には年間3兆円を越える財源が必要となる。規定予算内での調整や歳出改革では間に合わない。そこで “支援金制度” の導入である。政府は2024年度からの3年間を “加速化プラン” の実施期間と位置付けるが、これに対応する形で2026年度から2028年度まで1人あたり500円程度を公的医療保険に上乗せする計画だ。医療保険は企業も半額を負担するため社会全体で取り組むという大義にも合致する。しかし、保険料ではあるが、実質的には増税であり、こどものいない世帯からの不満が燻る。
後期高齢者の自己負担割合も引き上げる。出産育児一時金の財源にその一部を充当することで現役世代の負担を抑制する。しかし、そもそも後期高齢者の医療制度を健康保険制度から切り離した狙いは「現役世代による財政支援で後期高齢者の医療負担を軽減する」ことにあった。つまり、これは当初の制度設計に相反する策であって、すなわち見通しの甘さと政策の行き当たりばったり感を浮き彫りにさせるものである。
一方、ここへきて子育て支援策に新たな駆け込みもある。5日、こども世帯への生命保険料における控除引き上げ案が報じられた。住宅ローン金利の優遇、住宅リフォーム減税といった施策に加えての “生保優遇” には当然ながら「特定業種への偏り」や「低所得層に恩恵が及びにくい」ことへの批判があがる。
世代間、ライフスタイル(こどもの有無)、所得階層間、これらの対立をどう解消するのか。縦割り型の発想を越えた、抜本的な制度設計が必須である。“辻褄合わせ” ではすべてが中途半端となろう。結果、誰もが将来への確信を失う。少子化対策が最優先課題であるとすれば、今まさに「異次元」の覚悟が問われる。

今日、11月30日、国連の気候変動枠組み条約第28回締約国会議(COP28)がスタートする。国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は21世紀末時点における世界の平均気温を産業革命前比+1.5℃に抑えるためには「2035年時点で対2019年比60%の削減が必要」と指摘しており、これを公式な目標数値として成果に書き込めるかが会議の焦点である。“60%” という数字は5月の広島サミットでも確認されており、G7議長国である日本の覚悟も問われる。
今回の会議ではパリ協定で定めた「5年ごとに削減目標の達成度を検証し、それを踏まえて目標を再設定する」ルールがはじめて適用される。会議前に公表された検証結果によると「現状では “1.5℃目標” の達成は不可能」とのことであり、上記 “60%” の意味もここにある。加えて、議長国が合意を目指す “2030年までに再生可能エネルギーの導入量を3倍に” とする提案やEUが重視する “化石燃料の削減・廃止” を巡る議論の行方も注目される。
COP28を控えた11月20日、国際的な非政府組織(NGO)オックスファムが「気候変動が世界の格差を助長している」とのレポートを発表、「2019年、世界の超富裕層1%が排出する温暖化ガスは世界の排出量の16%に相当、自動車、道路輸送の排出量を上回るとともに100万基の風力タービンの効果を相殺する。影響は洪水、海面上昇、砂漠化、食料危機など多岐にわたり、被害は途上国に集中する。一方、1%の超富裕層の所得に60%の税を課すことで英国の排出量を上回る削減が実現でき、加えて化石燃料から再生可能エネルギーへの移行費用として6.4兆ドルが調達できる」という。
COPでは常に先進国と途上国が対立する。オックスファムの言葉を借りれば、豊かな国は “disproportionately(不釣り合い)” なほどの責任を有している、ということだ。一方、この問題において常に “途上国” として振る舞ってきた中国が「再生可能エネルギー3倍案」については米国とともに支持を表明するなど個々の主題ごとに各国の利害は錯綜する。中東産油国の反発は当然予想される。ただ、今回の議長国はまさに中東の産油国、アラブ首長国連邦(UAE)で、議長はアブダビ国営石油会社のCEOを兼務するジャベル産業・先端技術相である。それゆえの懸念もある。しかし、それゆえにこそ大胆でリアルな調整力を示していただきたい。
