
11月7日、宇宙へ旅立ってちょうど1か月、ISSに滞在する若田光一宇宙飛行士が上空から日本付近を撮影した画像をアップした。「各地の街の明かりがよく見えました」とのコメントどおり、東京湾を中央に構図した首都圏の写真はまさに広域地図そのままである。多摩川の流れや小田急線に沿った街の灯りも確認でき、筆者の自宅はこの辺りかな、などと宇宙からの眺めを疑似体験させていただいた。
私たちにとって宇宙はまだ特別な空間だ。しかしながら、今、宇宙をルートにした輸送システムが現実の産業領域となりつつある。文部科学省は「革新的将来宇宙輸送システム」の実現に向けたロードマップを策定、2030年頃を目途にコストをH3ロケットの半分程度に抑えた“基幹ロケット発展型”を打ち上げ、2040年頃には2地点間高速輸送に適用可能な “高頻度往還飛行システム” の実現を目指す。この時のコストはH3の1/10以下だ。
今年6月に開催された(一社)宇宙旅客輸送推進協議会(SLA)の第3回シンポジウムでは、SLAが提示したインプットパッケージをベースに試算された2040年時点における宇宙輸送の世界市場規模が発表された。これによるとヒトの輸送とモノの輸送を合わせた総市場規模は計11兆円を越える。実現すれば、東京と米西海岸、東京と欧州は、平均時速9000㎞で、それぞれ約60分で結ばれる。
もちろん、そのためには機体を帰還・回収する技術、点検・整備や部品の供給体制の構築、運行システム、地上側施設、環境負荷など、解決すべき課題が山積する。JAXAではこれらの解決に向けて「革新的将来宇宙プログラム」をスタート、機体の再利用と低コスト化の実現に向けて宇宙関連はもとより非宇宙の業界や大学等の研究機関に対して研究提案を呼びかける。
内閣府 宇宙開発戦略推進事務局が策定した宇宙関係の令和5年度予算概算要求の総額は前年度比24%増の4824億円、うち、「将来宇宙輸送システムロードマップの実現」のための研究開発予算は66億円だ。予算額の妥当性を評価できる知見は筆者にないが、民間からの投資の必要性は自明である。宇宙、非宇宙を問わずより多くの企業の参画を促すためには事業予見性への信頼が不可欠だ。ロードマップの進捗に関する情報共有を前提とした産学に開かれた共創型の体制で研究開発を加速していただきたく思う。

10月25~26日、山梨県北杜市で慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科(SDM)の山形与志樹教授が主催する未来社会共創イノベーションラボ※1のワークショップが開催された。テーマは「ゼロカーボンでウェルビーイングな北杜市の実現に向けて」、地産地消グリーン電力、自動運転EV、ゼロエミビレッジ、花と緑のワデュケーション、ドローン林業、そして、未来の観光ビジョンなど、多様な視点からの報告と議論が2日間にわたって展開された。
主催者である山形教授の研究テーマは未来都市デザイン。交通、エネルギー、産業、地域を1つのシステムとして捉え、先端テクノロジーを活用した持続可能なスマートシティづくりを目指す。北杜市では、オーストリアのWerfenweng村を拠点に環境にやさしい広域ツーリズムを推進するNGO「アルパイン・パールズ」をロールモデルに “まだ誰も見たことのない未来社会づくり” に挑む。まずは観光拠点である清里エリアと行政機関、市立病院、コミュニティホールなどが集中する長坂エリアを仮想フィールドに、自動運転EV、ドローン、地産地消エネルギーを活用したサスティナブルな地域づくりを提案してゆく。
当社からは、当社カーボンニュートラルビジネス研究所※2が八ヶ岳山麓でスタートさせた地域経済循環モデルの実証プロジェクトについて伊藤愛子所長が講演、ワークショップにはエネルギーと住環境を担当する調査チームのリーダーと観光消費の経済波及効果やAIを使った産業別未来予測に取り組む研究員、そして、筆者の3名が参加、次世代モビリティとグリーン電力を中心テーマに、観光産業、ドローンを活用したスマート林業、北杜市のブランディングの在り方など、幅広い課題について意見交換をさせていただいた。
今、自動運転やMaaSの実証実験が各地で本格化しつつある。自動運転レベル4※3も間もなく解禁だ。しかし、先端技術と法令整備だけで持続可能なまちづくりは実現しない。セクターを越えての取り組みと地域の合意形成が必須である。ワークショップには(一社)八ヶ岳ツーリズムマネジメント、(一社)ゼロエミやまなし、をはじめとする地元のステークホルダーも参画、地産地消電力とソフトモビリティを一体的に推進するための戦略が議論された。そう、ここには民間の側に脱炭素に向けてのビジョンと組織があって、それを牽引するリーダーがいる。北杜市の優位はここにある。とは言え、行政からの一押しも不可欠だ。市の “もう一歩” に期待したい。
※1 未来社会共創イノベーションラボ:環境とウェルビーイングが好循環する未来社会の実現を目指して、持続可能な都市システムの研究と実践に取り組んでいる。
https://yamagata.sdm.keio.ac.jp/
※2 カーボンニュートラルビジネス研究所:2018年12月に株式会社矢野経済研究所が設立した組織。脱炭素へ向けた社会・産業構造の転換をビジネス機会と捉え、新たな価値の創出を目指している。2022年7月、八ヶ岳山麗で小さな経済循環モデルの実証実験 “ココラデ・プロジェクト” をスタートさせた。
※3 自動運転レベル4:国土交通省が定義した6段階の自動運転レベル(レベル0~レベル5)のうち、レベル4は特定条件下における完全な自動運転を実現できる段階。遠隔監視のもとで特定ルートを走行する巡回バスなどが可能となる。

日本中を震撼させた「酒鬼薔薇聖斗」こと少年Aによる神戸連続児童殺傷事件(1997年)の全記録が廃棄されていた。最高裁は「社会的な影響が大きく、史料的な価値が高い事件や少年非行の調査研究に資する記録は永久保存とする」旨の通達を出しており、神戸家裁は「経緯は不明」としつつも「運用は適切でなかった」旨、釈明した。
これほどの事件に関する資料が廃棄されていたこと自体も驚きであるが、これを問われた最高裁の回答には愕然とさせられる。報道によると「本件についての見解は差し控える」、「廃棄の経緯が不明であることに問題はない」とのことだ。
10月6日、河野デジタル担当相は「2024年度中に健康保険証を廃止し、マイナンバーカードに一体化させる」と表明した。カードの普及率は6年半を経て5割に留まる。つまり、取得を動機づける利便性を提案出来なかったということであり、任意から義務化への転換はこれに業を煮やしての決断である。要するに失策だった。取得推進のインセンティブにどれだけの税金が投じられたのか。「マイナポイント第2弾」だけでも1兆4000億円の予算が組まれた。広報宣伝にも莫大な予算が投じられてきた。失われた膨大な時間と投下された税金に対する検証はなされたのか。
旧統一教会を巡る対応も煮え切らない。“今後は一切の関係を断つ” とまでトップが表明せざるを得ない組織の活動に関与し、その信用を補完し続けてきたことに対する社会的責任が「丁寧な説明」や「猛省」の一言で免責されていいのか。そもそもあたかも “なかったこと” のように振る舞い続けられる無恥と不誠実さは一体どこから来るのか。いつから日本の “大人” はこうなったのか。
主張のちがいや施策の失敗が本質ではない。異論を揶揄し、批判を封じ、都合の良い事象のみを選び取り、不都合な事実から目を逸らすよう方向づける、ここが危うさの根本だ。これは隣国の話ではない。
「政治の決め事は7世代先の人々のことを念頭においてなされる。なぜならこれから生まれてくる世代の人々が地面の下から私たちを見上げているからだ」、これはネイティブアメリカン「オノンダーガ族」に継承される言葉だ(「それでもあなたの道を行け」、ジョセフ・ブルチャック編、めるくまーる社)。そう、「今」を歴史として未来へつないでゆく責任を忘れてはならない、ということだ。
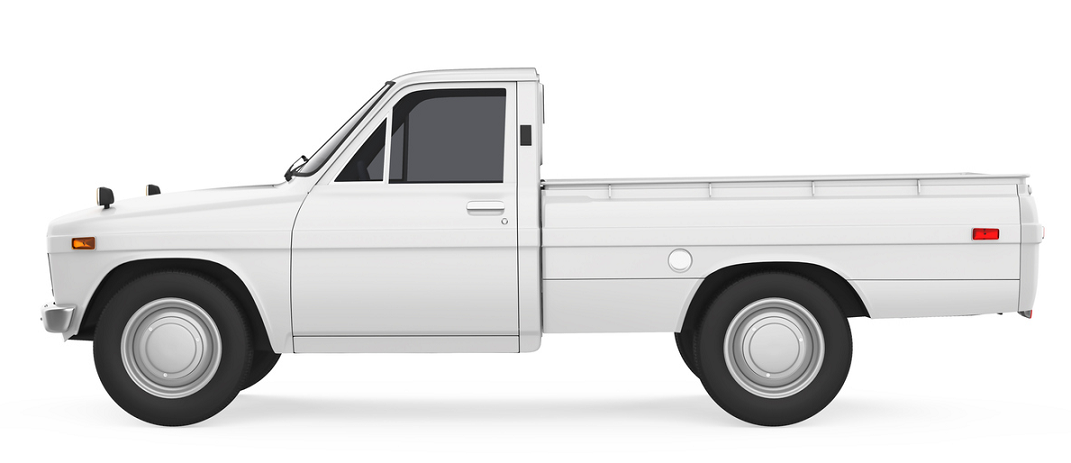
10月12日、報道各社は「トヨタ自動車がミャンマーの自動車組み立て工場でピックアップトラック『ハイラックス』の生産をスタート、今月から販売会社が予約の受付を開始した」と報じた。
トヨタは2019年、ヤンゴン近郊の経済特区に豊田通商と合弁で現地法人を設立、2021年2月の開業を目指して準備を進めていた。しかし、その直前、国軍による軍事クーデターが発生、工場の稼働は無期限延期となっていた。
とは言え、ミャンマー情勢は安定したわけでなく、ましてや民主派の復権などほど遠い。10月12日、反国軍デモを取材したとして拘束された日本人のドキュメンタリー作家に対する裁判が結審した。扇動罪、通信法違反、入国管理法違反を合わせて計10年の禁固刑である。また、同日、民主派指導者アウンサンスーチー氏も新たに2件の有罪が確定、刑期は合計26年となった。言論や表現の自由は完全に封殺されている。国軍の強権的姿勢はむしろ強まっていると言えよう。
10月10日、世界の人権状況を監視している国際NGO(非政府組織)「ヒューマン・ライツ・ウォッチ」(本部ニューヨーク)は、日本がODAの一環として供与した旅客船3隻が軍事転用されていると指摘した。そのうえで、「日本政府は人道支援以外の開発支援を停止し、深刻な人権侵害に関与した国軍に対して制裁を課すべき」と声明した。日本はクーデター以降、新規ODAは停止した。ただ、既存のODAは継続している。同NGOはこうした状況を「経済制裁に対して中途半端」と評価したうえで、「あらゆる外交手段を駆使して国軍に圧力をかけるべき」と提言する。
ミャンマー情勢に関する報道は少なく、正確な状況は見えにくい。ただ、圧制が続いていることは間違いない。内政不干渉を原則とするASEAN(東南アジア諸国連合)でさえ首脳会議への国軍トップの出席を2年連続で拒否、国軍に対して暴力の即時停止を求めている。そうした中でのトヨタの経営判断である。もちろん、あらゆるリスクは検討済みであろう。トヨタフィロソフィーには “1秒1円にこだわる” とある。なるほど、である。しかし、“人の幸せについて深く考える” との記述もある。新たに生産される『ハイラックス』が後者につながるものであると願いたい。

第210回国会の所信表明演説、岸田首相は「原発の再稼働と次世代原発の開発・建設の議論を加速させる」と明言した。今夏、政府は7年ぶりに企業と家庭に対して節電要請を発した。円安、資源高、そして、長期化するロシアの軍事侵攻の中、電力の安定供給に不安は残る。
とは言え、電力供給の安定化に向けてなすべき施策は “東日本大震災” が提示してくれたはずだ。2011年7月、国土交通省は電力供給の安定に向けて、地域間連系線の増強、周波数変換所の増設、自立分散型ネットワークの必要性を指摘している。そして、そこから11年、政府の検討会では未だにこれらが “検討課題” のままである※1。
なぜ提言は実現していないのか。もちろん、安全基準の強化は前提であろうが、そもそも行政や産業界の中に “電力行政の根幹は変わらないだろう” との暗黙の前提があったのだろう。原子力に関する政策判断が中途半端なまま、結果、電力供給の脆弱性は変わらず、かつ、洋上風力、水素、電池など日本が優位とされた技術領域における国際競争力は相対的に低下した。とりわけ、洋上風力の世界シェアは中国の47%に対してわずかに0.1%である※2。
所信表明で首相は繰り返し「安全保障」について言及した。経済安全保障、食料安全保障、エネルギー安全保障、、、国際情勢の緊張が高まる中、「安心」「安全」への不安は募る。そして、ロシアの暴挙はまさにエネルギー危機を身近な問題として顕在化させた。と同時に、ウクライナのザポリージャ原発は、「原発は侵略者に核兵器を与えることと同等のリスクを孕んでいる」ことをあらためて世界に示した。いかなる独裁者であっても原発は攻撃対象としないだろう、などというお花畑な安全神話はあてにならないということだ。
さて、成長力を取り戻す近道は基幹産業のイノベーションである。自動車と同様に電力はその筆頭候補だ。大きな歯車が回るほど波及効果は大きく、スタートアップのチャンスも広がる。その意味で原子力というテクノロジーも選択肢の一つである。ただ、“福島” は、原発に内在するリスクとコストは、電力会社はもちろん、私たちの世代だけでは負いきれない事実を突き付けた。
成長戦略の基軸をどこに置くのか、国民の安全をどう担保するのか、費用は、そしてリスクを誰が負うのか、脱炭素に向けての数値目標も重要課題だ。私たちは将来世代に何を残すのか、電力需給の問題を越えた次元において正面から原子力を議論する必要がある。
※1 「電力需給ひっ迫、自立分散型ネットワークの構築を急げ」 今週の“ひらめき”視点 2022.6.12 – 6.16
※2 「出遅れた洋上風力産業、海洋国家日本の潜在力を引き出すために戦略の再構築を」 今週の“ひらめき”視点 2022.7.31 – 8.4

9月22日、日銀の黒田総裁は金融政策決定会議後の記者会見で「大規模な金融緩和を “当面” 継続する」と表明、直後、円は対ドル145円90銭まで一気に下落した。政府はこれを受けて「過度な変動を押さえる」として24年ぶりに円買いの市場介入に踏み切った。投じた資金は3兆円規模と推計され、円は一時140円31銭まで戻された。しかし、米国、EUが協調介入を即座に否定したこともあり、連休明けには再び144円台に戻った。円安の基調に変化はない。
そもそも金融緩和の維持は見込まれていた。にもかかわらず起こった急激な下落の引き金は、来年4月に任期を終える黒田氏が発した「当面というのは数か月ではなく今後2~3年という意味だ」との一言だ。これは次期総裁の政策オプションを縛るものであり、金融政策の硬直化を宣言したようなものである。“当面は政策の変更はない” との安心感を市場が共有したとすれば、市場介入はむしろ投機的な動きを呼び込み易くなる。市場への牽制効果という意味でもまさに余計な発言であった。
円安の背景に日米の金利差拡大があることは言うまでない。したがって、主要国にあって唯一極端な低金利を続ける日銀は政策の転換をはかるべき、との声も聞こえてくる。ただ、そう単純ではない。要は外貨に対してドルが強すぎることが問題であり、つまり、米国のインフレに歯止めがかかり、ドル高のピークアウトが見通せるまで相場のトレンドを反転させることは難しいと思われる。加えて、円もまた構造的な問題を抱える。2013年からの “異次元緩和” は目標とした2%の物価上昇に届かなかった。“実質賃金が増えない中での円安、資源高を背景とした物価高” という状況を鑑みるとこのタイミングでの金融引締めは景気の腰を折るばかりか、コロナ禍の後始末が残る中小企業にとって死活問題となる。
さて、通貨の強さは稼ぐ力、言い換えれば未来への信任という側面もあろう。その意味で円そのものの成長期待が相対的に低下しているとも言える。グローバル企業の海外売上高を円に換算すればその分が嵩上げされる。円安は大手企業にとって業績好調の一因だ。しかし、ドル建てベースでみると円安は国力低下以外の何物でもない。1ドル140円で日本のGDPは1990年代初頭へ逆戻りだ。もちろん、インバウント需要は拡大するし、輸出における価格競争力も高まる。しかし、“安い日本” のままでいいのか。高い付加価値による生産性の向上と持続的な成長があってこそ日本のプレゼンスは高まる。つまり、金融政策だけの問題ではないということだ。今こそ、長期的視点に立った産業政策の大胆な転換が求められる。
