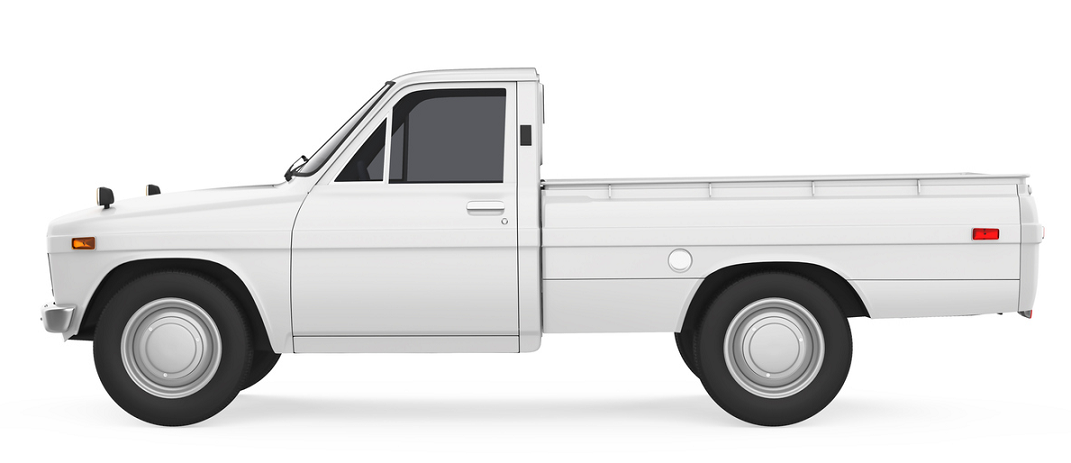
10月12日、報道各社は「トヨタ自動車がミャンマーの自動車組み立て工場でピックアップトラック『ハイラックス』の生産をスタート、今月から販売会社が予約の受付を開始した」と報じた。
トヨタは2019年、ヤンゴン近郊の経済特区に豊田通商と合弁で現地法人を設立、2021年2月の開業を目指して準備を進めていた。しかし、その直前、国軍による軍事クーデターが発生、工場の稼働は無期限延期となっていた。
とは言え、ミャンマー情勢は安定したわけでなく、ましてや民主派の復権などほど遠い。10月12日、反国軍デモを取材したとして拘束された日本人のドキュメンタリー作家に対する裁判が結審した。扇動罪、通信法違反、入国管理法違反を合わせて計10年の禁固刑である。また、同日、民主派指導者アウンサンスーチー氏も新たに2件の有罪が確定、刑期は合計26年となった。言論や表現の自由は完全に封殺されている。国軍の強権的姿勢はむしろ強まっていると言えよう。
10月10日、世界の人権状況を監視している国際NGO(非政府組織)「ヒューマン・ライツ・ウォッチ」(本部ニューヨーク)は、日本がODAの一環として供与した旅客船3隻が軍事転用されていると指摘した。そのうえで、「日本政府は人道支援以外の開発支援を停止し、深刻な人権侵害に関与した国軍に対して制裁を課すべき」と声明した。日本はクーデター以降、新規ODAは停止した。ただ、既存のODAは継続している。同NGOはこうした状況を「経済制裁に対して中途半端」と評価したうえで、「あらゆる外交手段を駆使して国軍に圧力をかけるべき」と提言する。
ミャンマー情勢に関する報道は少なく、正確な状況は見えにくい。ただ、圧制が続いていることは間違いない。内政不干渉を原則とするASEAN(東南アジア諸国連合)でさえ首脳会議への国軍トップの出席を2年連続で拒否、国軍に対して暴力の即時停止を求めている。そうした中でのトヨタの経営判断である。もちろん、あらゆるリスクは検討済みであろう。トヨタフィロソフィーには “1秒1円にこだわる” とある。なるほど、である。しかし、“人の幸せについて深く考える” との記述もある。新たに生産される『ハイラックス』が後者につながるものであると願いたい。

第210回国会の所信表明演説、岸田首相は「原発の再稼働と次世代原発の開発・建設の議論を加速させる」と明言した。今夏、政府は7年ぶりに企業と家庭に対して節電要請を発した。円安、資源高、そして、長期化するロシアの軍事侵攻の中、電力の安定供給に不安は残る。
とは言え、電力供給の安定化に向けてなすべき施策は “東日本大震災” が提示してくれたはずだ。2011年7月、国土交通省は電力供給の安定に向けて、地域間連系線の増強、周波数変換所の増設、自立分散型ネットワークの必要性を指摘している。そして、そこから11年、政府の検討会では未だにこれらが “検討課題” のままである※1。
なぜ提言は実現していないのか。もちろん、安全基準の強化は前提であろうが、そもそも行政や産業界の中に “電力行政の根幹は変わらないだろう” との暗黙の前提があったのだろう。原子力に関する政策判断が中途半端なまま、結果、電力供給の脆弱性は変わらず、かつ、洋上風力、水素、電池など日本が優位とされた技術領域における国際競争力は相対的に低下した。とりわけ、洋上風力の世界シェアは中国の47%に対してわずかに0.1%である※2。
所信表明で首相は繰り返し「安全保障」について言及した。経済安全保障、食料安全保障、エネルギー安全保障、、、国際情勢の緊張が高まる中、「安心」「安全」への不安は募る。そして、ロシアの暴挙はまさにエネルギー危機を身近な問題として顕在化させた。と同時に、ウクライナのザポリージャ原発は、「原発は侵略者に核兵器を与えることと同等のリスクを孕んでいる」ことをあらためて世界に示した。いかなる独裁者であっても原発は攻撃対象としないだろう、などというお花畑な安全神話はあてにならないということだ。
さて、成長力を取り戻す近道は基幹産業のイノベーションである。自動車と同様に電力はその筆頭候補だ。大きな歯車が回るほど波及効果は大きく、スタートアップのチャンスも広がる。その意味で原子力というテクノロジーも選択肢の一つである。ただ、“福島” は、原発に内在するリスクとコストは、電力会社はもちろん、私たちの世代だけでは負いきれない事実を突き付けた。
成長戦略の基軸をどこに置くのか、国民の安全をどう担保するのか、費用は、そしてリスクを誰が負うのか、脱炭素に向けての数値目標も重要課題だ。私たちは将来世代に何を残すのか、電力需給の問題を越えた次元において正面から原子力を議論する必要がある。
※1 「電力需給ひっ迫、自立分散型ネットワークの構築を急げ」 今週の“ひらめき”視点 2022.6.12 – 6.16
※2 「出遅れた洋上風力産業、海洋国家日本の潜在力を引き出すために戦略の再構築を」 今週の“ひらめき”視点 2022.7.31 – 8.4

9月22日、日銀の黒田総裁は金融政策決定会議後の記者会見で「大規模な金融緩和を “当面” 継続する」と表明、直後、円は対ドル145円90銭まで一気に下落した。政府はこれを受けて「過度な変動を押さえる」として24年ぶりに円買いの市場介入に踏み切った。投じた資金は3兆円規模と推計され、円は一時140円31銭まで戻された。しかし、米国、EUが協調介入を即座に否定したこともあり、連休明けには再び144円台に戻った。円安の基調に変化はない。
そもそも金融緩和の維持は見込まれていた。にもかかわらず起こった急激な下落の引き金は、来年4月に任期を終える黒田氏が発した「当面というのは数か月ではなく今後2~3年という意味だ」との一言だ。これは次期総裁の政策オプションを縛るものであり、金融政策の硬直化を宣言したようなものである。“当面は政策の変更はない” との安心感を市場が共有したとすれば、市場介入はむしろ投機的な動きを呼び込み易くなる。市場への牽制効果という意味でもまさに余計な発言であった。
円安の背景に日米の金利差拡大があることは言うまでない。したがって、主要国にあって唯一極端な低金利を続ける日銀は政策の転換をはかるべき、との声も聞こえてくる。ただ、そう単純ではない。要は外貨に対してドルが強すぎることが問題であり、つまり、米国のインフレに歯止めがかかり、ドル高のピークアウトが見通せるまで相場のトレンドを反転させることは難しいと思われる。加えて、円もまた構造的な問題を抱える。2013年からの “異次元緩和” は目標とした2%の物価上昇に届かなかった。“実質賃金が増えない中での円安、資源高を背景とした物価高” という状況を鑑みるとこのタイミングでの金融引締めは景気の腰を折るばかりか、コロナ禍の後始末が残る中小企業にとって死活問題となる。
さて、通貨の強さは稼ぐ力、言い換えれば未来への信任という側面もあろう。その意味で円そのものの成長期待が相対的に低下しているとも言える。グローバル企業の海外売上高を円に換算すればその分が嵩上げされる。円安は大手企業にとって業績好調の一因だ。しかし、ドル建てベースでみると円安は国力低下以外の何物でもない。1ドル140円で日本のGDPは1990年代初頭へ逆戻りだ。もちろん、インバウント需要は拡大するし、輸出における価格競争力も高まる。しかし、“安い日本” のままでいいのか。高い付加価値による生産性の向上と持続的な成長があってこそ日本のプレゼンスは高まる。つまり、金融政策だけの問題ではないということだ。今こそ、長期的視点に立った産業政策の大胆な転換が求められる。
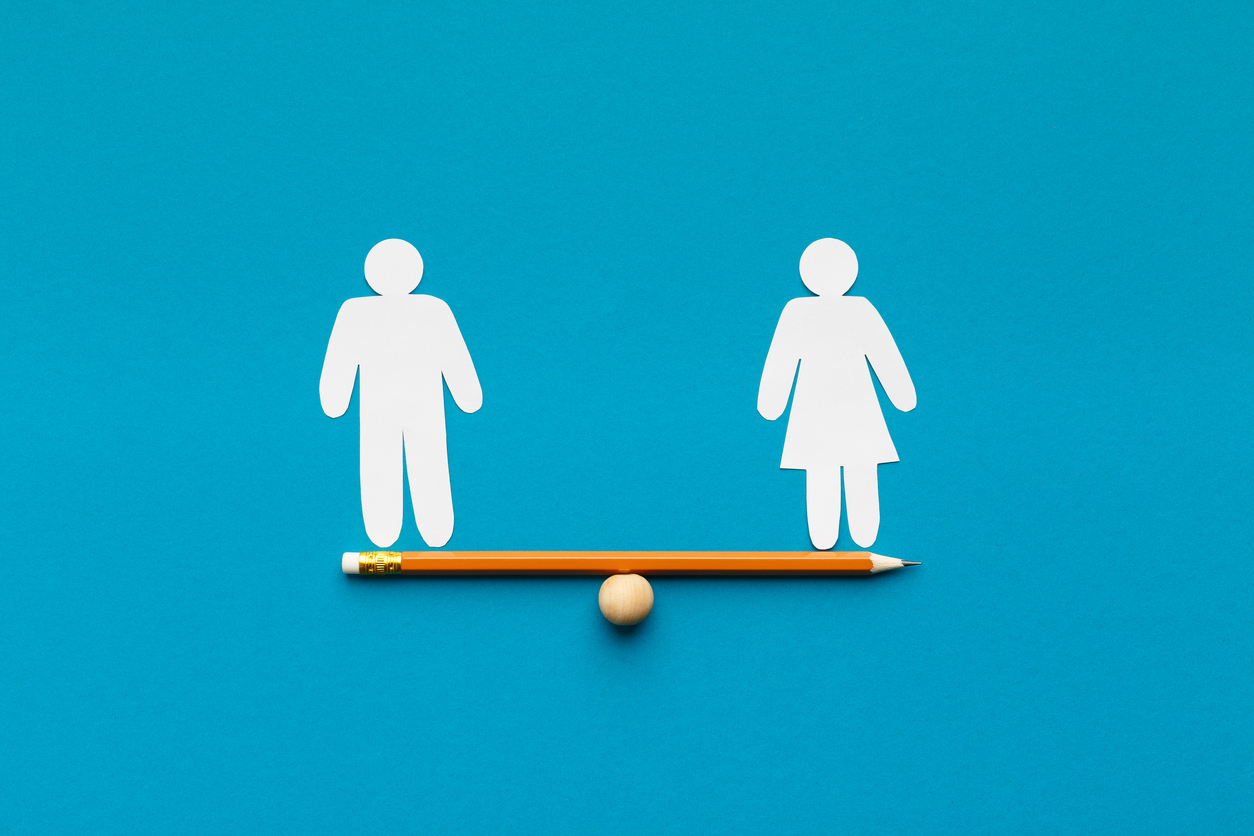
9月13日、当社は女性ヘルスケアマーケティングの「WOMAN'S」(ダブルコレクション社)をパートナーにジェンダード・イノベーションをテーマとするセミナーを開催した。参加者は856名、この分野への産業界の関心の高さが伺えた。とは言え、“ジェンダード・イノベーション” は2005年、米スタンフォード大学のLonda Schiebinger氏が提唱した比較的新しい概念であり、初めて耳にする方も多いだろう。要約すると、生物学的、社会学的な視点から性差を研究し、性差による不利益が解消された平等な社会を創造する、ということである。
セミナーでは清水 由起氏(当社主席研究員)がフェムテック市場の現状について、●女性特有の健康課題に関する社会的な関心が高まる中、市場機会が拡大している、●医療サービス、医療用医薬品を除く2020年の国内市場規模は597億円、成長率は前年比103.9%、●2021年は参入企業、参入分野が増えたこともあり、市場規模は636億円に拡大、成長率も106.5%と勢いが出てきた、●一方、男性の女性の健康課題に対する理解は依然低く、女性のヘルスリテラシーにも課題が残る。社会全体の理解が浸透するにはまだまだ時間を要する、●しかし、欧米を中心にジェンダード・イノベーションの流れは加速しており、日本においても後退はない、と調査結果にもとづく報告を行った。
続いて登壇した矢野 初美氏(当社上級研究員)は、運転操作やキャビン内のプライバシーに配慮した女性ドライバー向けの大型トラック、女性の平均身長を基準に設計されたキッチンを男性でも使い易いように可変式にしたシステムキッチンなど、性差に着目した商品開発の事例について解説した。これらは、ドライバーは男性、料理は女性といったバイアスを乗り越えることで市場の拡大と利便性の向上を実現させた好例である。つまり、ここで示唆されるのは、フェムテック市場の裏側には同規模のメイルテック市場も存在する、ということだ。「ジェンダード・イノベーションの潜在市場は10兆円!」との清水氏の推計も頷けよう。
一方、性差研究には危うさも伴う。1つは家父長制型社会への退行を正当化するための言説として利用されかねないこと、もう1つは、性差分析は民族や人種といった遺伝的な分析軸を呼び込み易いということだ。こうしたミスリードを回避するためにも、「性差マーケティングは、あくまでも個人の生き易さを実現するためのメソッドであり、ゆえにジェンダーフリーやジェンダーレスとの相反はない」ことを強調しておきたい。多様性を受け止め、違いを認識することで、性差による不平等と機会損失を失くす、そのために何をすべきか、何が出来るか。当社はこの視座に立ってジェンダード・イノベーションに取り組んでゆきたい。

日本時間9月9日未明から、米国主導による「インド太平洋経済枠組み」(IPEF)の閣僚級会合が開幕する。2021年10月、米バイデン氏は東アジアサミットの席上、アジア太平洋地域で急速に影響力を強める中国に対抗するための新たな経済圏構想を提唱、これに日、韓、印、豪、ニュージーランドにラオス、ミャンマー、カンボジアを除くASEAN7ヵ国を加えた13ヵ国が参加を表明、5月23日、東京で第1回の会合を開催した。その後、フィジーも加わり、参加表明国は全14ヵ国、今回は各国閣僚がロサンゼルスに集結、「正式交渉開始の宣言」を目指し、対面での会議に臨む。
IPEFは、TPPへの加盟を見送った米国が、この地域における影響力の維持を狙って構想した国際的な枠組みで、貿易、サプライチェーン、クリーン経済、公平な経済の4分野を柱とする。とは言え、電子商取引におけるデータの取り扱いや人権、環境、腐敗防止等について高いレベルで合意を取り付けるのは容易ではない。加えて、そもそも米国は、自国市場の開放に消極的であるがゆえにTPPへの参加を拒否したわけで、したがって、米国市場へのアクセスというインセンティブもない。
中国はそのTPPに参加を表明、RCEPには加盟済だ。それだけに対中包囲網づくりを急ぎたい米国は、IPEFへの参加に際して「参加国は参加分野を自由に選択できる」とハードルを下げた。この辺りは、必ずしも米国と中国の二者択一を望まないアジア諸国を取り込むための苦肉の策とも言える。台湾が加わっていないことも同じ理由であろう。ただ、参加国の参加分野があまりにも限定的であると経済圏としての一体性、実効性に疑問が生じかねない。米国のリーダーシップと調整力が問われるところだ。
一方、参加国が共通して関心を寄せているのがサプライチェーン分野であろう。新型コロナウイルスやロシアによる軍事侵攻はグローバル経済の脆弱性を露呈させた。IPEFは国際調達網におけるリスク低減をはかるべく、半導体、医療物資、食料、資源といった重要物資を緊急時に参加国間で融通できる仕組みの構築を目指す。尖閣問題でレアアースの供給を止められた日本にとって、対中リスクの軽減を国際間協定の中で担保できることの重要性は言うまでもない。サプライチェーン分野への期待は大きい。ただ、そうは言ってもアジア各国にとって最大のモチベーションとなり得るのは“米国市場の開放”である。IPEFの経済圏としての影響力を高めるためにもTPPへの米国の早期復帰を望む。

24日、政府は新型コロナウイルス感染者の全数把握を見直すと発表した。重症化リスクの高い人を除き、各自治体の判断で届出内容を簡素化出来る。これに対して、軽症患者の病状急変や自宅療養者への行政サービス低下に対する懸念、更には自治体への責任転嫁との批判が噴出する。政府は直ちに「全国一律導入を原則とする」旨の声明を発表、火消しにかかるが、当初予定した31日の運用開始に向けて通知した期限までに “見直し”の受け入れを表明したのはわずかに4県、10都県はこれまで通り、33府県は判断を保留した。
事務作業の負担軽減を望む現場の声は理解できる。しかし、そもそも「データ」は科学的な政策判断を行うための基本統計として、医師や防疫の専門家自らが設計したものではなかったのか。飲食店の営業自粛、移動制限等の効果検証はもちろん、感染症の医学的、疫学的な研究や非常時の医療連携の在り方を考えるためにも“ビッグデータ”は有効だ。まずやるべきは入力インタフェースの改善、事務処理代行など現場支援の強化であって、未来の危機に備えるためにも科学的検証に耐え得るデータの取得体制は可能な限り維持すべきではないか。
一方、政府は陽性者の療養期間の短縮、無症状者の外出容認、水際対策の緩和へ舵を切る。これらは“第7波”が既に減少局面にあるとの認識にもとづくものだ。しかし、陽性者の外出が許可されて尚、感染症の区分は「2類」のままであるのか、いやいや、そもそも陽性者に対する措置が緩和される中にあって、なぜ全数把握の見直しなのか。同じデータにもとづいて政策決定がなされているとは俄かに信じ難い。医師会、知事会、経済界の要望を、声の大きい順に場当たり的に受け入れているのではないか、と勘繰りたくなる。
報道によれば、厚労省は全数把握の見直しに対応したシステムへの改修が完了するまでファックスやメールで代用させるとのことである。コロナ禍で露呈した構造問題の一つがデジタル化の遅れであったはずだ。少なくとも外部から見る限り、意思決定プロセスの不透明さを含め、行政のアナログ体質は一向に変わっていない。筆者は2021年1月29日付の本稿で「コロナ禍克服に向けて工程表を示せ」※と書いた。自身の立ち位置が不明のまま未知の敵とは戦えない。国内で感染者が確認されてから2年8カ月、この間の経験と最新の科学的知見を踏まえた、収束に向けての全体シナリオを早急に策定し、共有させていただきたい。
※コロナ禍を克服するために。社会の正常化に向けての工程表を示せ | 今週の"ひらめき"視点 | ニュース・トピックス | 市場調査とマーケティングの矢野経済研究所 (yano.co.jp)
