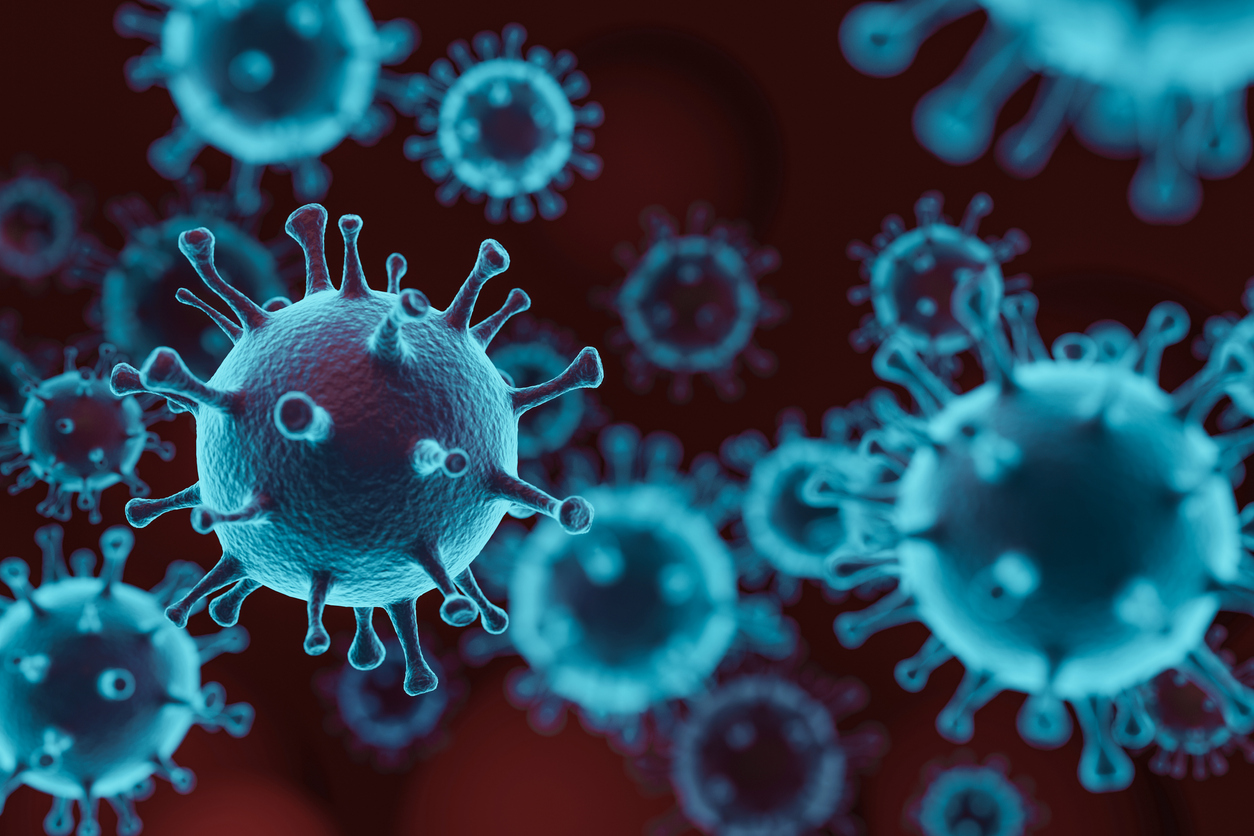
中国当局による「ゼロコロナ」政策の影響は、懸念されていた通りの規模と深刻さをもって顕在化しつつある。上海、深圳、瀋陽、東莞、長春、西安など厳しい統制を強いられた都市は3月以降、20を越えた。本来、消費を牽引すべき都市部における厳格な行動規制の長期化は、内需全体を委縮させるとともに全土のサプライチェーンに深刻な影響を与えつつある。
自動車販売がこれを象徴する。中国自動車工業協会によると4月の新車販売は前年の5割程度に落ち込んだ。封鎖地域における工場の停止、物流の混乱、顧客の不在が原因だ。
こうした中、4月下旬になると上海でも生産再開に向けての動きがみられた。とは言え、工場と外部との出入りは依然制限されている。つまり、事業所内に一定規模以上の宿泊設備がなければ本格稼働は出来ないということだ。一方、物流でも「重点物資輸送車両通行証」制度がスタート、省を越えたモノの輸送が動き出した。ただ、こちらも人員不足等により運送費は通常の数倍に達している。正常化には程遠い状況だ。
「ゼロコロナ」による影響は中国国内に止まらない。中国税関総署によると4月の輸出は3月の前年同月比14.7%増から同3.9%増へ急減、2020年6月以来の低い伸び率となった。一方、輸入も低調に推移、2020年8月以来のマイナスとなった3月の2287億ドルを下回る2225億ドルとなった。つまり、Made in Chinaの出荷額が落ち込むと同時に中国向けのモノの流れも低調だった、ということだ。そもそも海外向けの荷物が港に届かない。加えて、作業員不足による荷揚げ作業の停滞、輸送力低下による貨物の滞留など港湾システム全体の機能不全が効いている。日本企業への影響も大きい。
さて、事態の長期化に伴い「ゼロコロナ」への異論が国外はもちろん国内からも出始めた。しかし、秋の共産党大会を前に「現指導部が自らの誤りを認め、方針を転換することはない」との見方は根強い。当局が発した「職務怠慢による感染拡大に対する責任は厳しく問う」とのメッセージは地方官吏にとって絶対的な行動指針だ。「ゼロコロナ」が続く限り正常化は遠いと言わざるを得ない。とは言え、中国経済の急回復も世界にとってのリスクだ。巨大な需要の戻りはエネルギー、食料、資材、物流における世界的な供給不足を招来するはずであり、ロシアの軍事侵攻に伴う物資の高騰に拍車をかけることになるだろう。いずれにせよ目の前の混乱への対処と並行して “その先” にやってくるリスクを想定した戦略シナリオを準備しておく必要がある。

2021年10月に公開された映画「Shari」(監督・出演:吉開菜央)をご覧になった方はどのくらいいるだろうか。「羊飼いのパン屋、鹿を狩る夫婦、海のゴミを拾う漁師、、、、彼らが住むのは、日本最北の世界自然遺産、知床」、「2020年、この冬は雪が降らない。流氷も、なかなか来ない。地元の人に言わせれば、異常な事態が起きている」(映画の公式サイトより抜粋)、そこにダンサーでもある吉開監督が扮する「どくどくと脈打つ血の塊のような空気と気配」を身にまとった “赤いやつ” が現れる。
え? “赤いやつ” って何? うーん、これは映画を観ていただかないと分からない、と言うか、映画を観ても何だかよく分からない、というのが正直な感想である。吉開監督の言葉を借りると、それは「人と獣のあいだ」のようなやつで、「人と自然、自分と他者、言葉にならないこと、夢と現実、さまざまな境界線を彷徨う、命の渦の一粒」とのことである。
「他者との関係があなたの中に入り込み、あなたをあなたという存在にしている」と述べたのは社会人類学者ティム・インゴルドであるが、他者を自然あるいはShariと置き換えてみると吉開監督の想いに近いのかもしれない。ただ、私はその逆で、“赤いやつ” とは「入り込むことが出来ない “外部” の象徴」のように感じた。いずれにせよ写真家 石川直樹氏が撮った映像の美しさと音のすばらしさは圧巻であり、機会あれば是非とも鑑賞いただきたい。
そのShari、すなわち、斜里の産業を支える観光船で悲劇が起こった。報道を見る限り運航会社「知床遊覧船」に重大な過失があったことに異論はないだろう。そして、安全が蔑ろにされた背景には極度の業績不振があっただろうことも推察できる。斜里への道外からの観光客入込数は、2019年の839千人からコロナ初年度の2020年には344千人へと激減している(斜里町商工観光課)。加えて燃料費の高騰だ。とは言え、他社は安全を優先させているわけで、当該企業の責任が免責される理由は何一つない。
ただ、やはり構造的な問題を看過してはならない。斜里の高齢化率は30.0%、出生率は1.17%、前者は全国平均を上回り、後者はそれを下回る。人口、世帯数、就業人口は減少の一途だ。町は労働生産性の向上が喫緊の課題であるとし、昨年、中小企業庁の改正経営強化法にもとづく先端設備の導入促進計画を策定した。しかしながら、そもそも足りないのは需要だ。生産性向上を否定するものではないが、支援内容、支援条件が全国一律である必要はない。各地域に固有の状況に対応できるような制度設計が望ましい。知床観光への依存度が高い斜里に必要な施策はまずは安全投資へのインセンティブ、そして、需要の回復、すなわち “外部” の取り込み策である。

4月18日、経団連と大学関係者による協議機関「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」は、インターンシップで取得した学生の情報を採用活動に利用することを容認すると発表した。従来、文部科学省は「インターンシップは教育活動の一環であり、広報活動や採用選考への活用は認めない」との立場であったが、これを受けてルールの見直しに着手する。
お互いを知るという意味において職場での就業体験は企業、学生双方にメリットは大きい。通年採用、職種型採用など新卒の採用方法が多様化しつつある中、今回の決定は前進である。
協議会は学生のキャリア形成に関する産学協働の取り組みを、①会社説明会の実施、②キャリア教育プログラムの導入、③汎用的または専門性にもとづく就業体験、④高度専門型就業体験、の4つに分類したうえで、一定の条件を満たした就業体験について採用への活用を認めるとした。具体的には、汎用型であれば参加期間5日間以上、専門型は2週間以上とし、うち半分を越える日数が実際の職場体験にあてられること、夏休みなど長期休暇中に行うこと、募集要項等における情報の開示、そして、情報の活用は “採用活動開始以降” に限ること、などが提示されている。
昨年、政府は「令和4年度卒業の採用選考活動開始は6月1日以降、内定日は10月1日以降」とするよう経団連に要請、これを受けて経団連は「政府からの要請の趣旨を踏まえた採用選考活動を行って欲しい」旨、会員各社に通達した。しかしながら、今年度の就職内定率は4月1日時点で既に38.1%(株式会社リクルート、就職みらい研究所調べ)に達している。もちろん、これは経団連の非会員企業も含めての数値であるが、新卒の採用活動に関する “日程” は完全に形骸化していると言って良いだろう。
2018年10月、経団連は「2021年度以降入社対象の“採用選考に関する指針”を策定しない」ことを決定、政府に下駄を預けた。産業界はもちろん会員企業を統制する権威も、その意義も薄れたということである。一方、引き継いだ政府の “お達し” にも効力はなかった。インターンシップも同様だ。既に少なからぬ企業が採用選考に組み込んでいる。それでもあえて “採用選考活動開始日以降” を条件付けすることにどれほどの意味があるのか。建前と現実はちがう、それが大人だ、なんてことを体現し、経験させるのが就業体験であっては興ざめだ。昭和が染みついた “Society5.0人材” など見たくない。

対露制裁の反動が世界で顕在化しつつある。資源高による物価の急騰は、経済はもとより社会全体を揺さぶる。フランス大統領選挙では「EUと距離を置くべき」、「自由貿易より国内産業を」、「移民が国民を貧しくしている」と訴え、身近な物価対策を前面に掲げる右派のルペン氏が現職の中道派マクロン氏を猛追、24日の決選投票の行方はまったく分からなくなった。現実の問題として家計を圧迫された人々はより内向きに、そして、自国主義に傾く。ロシアの軍事侵攻は国際社会のみならず、その内側の分断も加速させつつある。
パキスタンでも首相のカーン氏に対する不信任案が可決した。資源のないパキスタンにとってエネルギー価格急騰のダメージは深刻であり、これが反首相派を勢いづかせた。失職したカーン氏は支援者に対して抵抗を呼び掛けており、中国寄りで米国批判を繰り返してきたカーン氏の今後の動向次第ではインド、アフガニスタン、中国などを巻き込んで地域全体の不安定さを助長する恐れもある。
加えて中国経済の停滞も懸念材料だ。ゼロコロナ政策に伴うリスクは年初の本稿でも指摘したが、人口2500万人を擁する上海でそれが現実のものとなった。上海は3月28日からロックダウン、当初期限の4月5日には延長を発表、外出禁止を呼びかけながら無人の市内を走り回る犬型ロボットの姿はまさに近未来のディストピアさながらだ。
今週に入ってようやく一部地域で封鎖が解かれたとのことであるが、完全な収束には時間を要すると思われ、社会活動の正常化はまだ先になろう。長期化が心配される。
11日、日銀は「地域経済報告-さくらレポート」を発表、全国9地域のうち8地域の景気判断を引き下げた。急激な円安、資材の高騰、サプライチェーンの混乱など、要因は複合的である。加えて新型コロナウイルスだ。政府、医師会は「第7波」に警鐘を鳴らす。しかし、重症化率の高い高齢者の85.3%が3回目の接種を終えている。ウイルスも当初のものとは異なる。一体いつまでこれを続けるのか。ウイルスはもちろんリスクだ。しかし、不安と不満の根源は施策への不信にある。この2年間、多くの犠牲を払って獲得してきた知見があるはずだ。一刻も早く明確な “出口” 戦略を提示していただきたい。今の戦い方では情勢の急激な変化を勝ち抜くことは出来ない。

4月4日、東京証券取引所は60年ぶりに市場を再編、新たな上場区分による取引をスタートさせた。世界の証券取引所を時価総額で比較すると、東京はニューヨーク、ナスダック、ユーロネクスト、上海に次ぐ世界第5位、しかしながら、ニューヨークの時価総額は東京の4.5倍、ナスダックは4倍と大きく水を開けられており、売買代金でも遥かに及ばない。国際競争力の強化は急務だ。
新区分の銘柄イメージは「プライム」が機関投資家向けのグローバル企業、「スタンダード」は内需型の優良企業、「グロース」は高い成長性を期待できる新興企業。東京市場の魅力を高め、海外勢の資金を呼び込むためにも最上位「プライム」の差別化が期待された。
しかしながら、東証旧1部上場企業2177社のうち1839社がプライムに移行、結果的にこれまでと代わり映えのしない銘柄構成となった。そもそも流通株式数2万単位以上、流通比率35%以上、時価総額100億円以上といった「プライム」の基準自体決してハードルが高いとは言えないが、その基準すら満たさない295社に経過措置が適用されるなど、“改革” の中途半端さは否めない。
せめて、経過措置には “期限” があって然るべきであるが、東証は「上場会社が、選択先の市場区分の上場維持基準を充たしていない場合、上場維持基準の適合に向けた計画及びその進捗状況を提出し、改善に向けた取組を図っていただくことで、当分の間、経過措置として緩和された上場維持基準を適用します」(日本取引所グループHPより)と言うに止まる。
萩生田経済産業大臣は3日のNHK「日曜討論」で「過去を振り返って、イノベーションは起きなかった。日本経済が成長出来なかったのはそのためである」との認識を示した。つまり、異次元緩和による円安誘導によって現出された株高は “成長” につながらなかった、ということだ。
世界の投資家の目を東京に向けさせるためにも市場改革は不可欠だ。今回の再編はその第一歩である。しかし、彼らの関心事は市場区分ごとの上場会社の数ではない。調達した資金を持続的に成長投資に振り向け、成果を社会に還元出来るガバナンスの高い企業の多寡である。問われているのは企業のイノベーション力であり、そうした流れを作り出し、投資家とつなぐための質的な改革を進めて欲しい。

国土交通省からエンジン4機種の形式指定の取り消しを通告されていた日野自動車は、25日、「意見なし」の陳述書を提出、道路運送車両法の施行以来はじめてとなる形式指定取消の行政処分が確定した。
この決定を踏まえ同社は2022年3月期の業績予想を修正、当期最終損益を前回予想の150億円の黒字から540億円の赤字に下方修正した。
日野自動車によると2018年に北米向けエンジンの認証手続きに不備が発覚、これを受けて総点検を実施したところ国内向けエンジンの排出ガスの性能試験や燃費性能の測定において意図的な不正行為が確認された。
2016年、三菱自動車で燃費測定におけるデータ改ざんが発覚、国土交通省は全メーカーに点検を指示、結果、スズキでも不正が確認された。この時、日野自動車は「不正なし」との報告を国土交通省にあげている。問題の一端はここにある。要するに甘い点検でお茶を濁した、言い換えれば、品質責任そのものを舐めていたと言うことだ。
もちろん、そもそもの根本は環境性能における技術力であるが、同時に「検査」という工程を常に低位にみてきた業界全体の体質を指摘できよう。
日産自動車、スバル、マツダでも検査不正はあった。2021年7月にはトヨタ系ディーラーでもデータ不正が見つかっている。日野自動車では2021年3月までエンジンの開発と認証が同じ部門に属していた。組織は経営の意志そのものである。まさに経営陣が検査や認証を軽んじてきたことの証左である。
今回の問題は北米向けエンジンを担当する社員の気づきが発端になったとのことである。現場の声が総点検につながったことはせめてもの救いである。この6月1日には改正公益通報者保護法が施行される。内部公益通報対応業務担当の独立性の確保、通報者を特定する行為の禁止、通報者の範囲を役員および退職後1年内の退職者へ拡張させる、といったことが常時雇用者300人を超える会社に義務づけられる。法令への対応は言うまでもない。しかし、品質に対する誠実さを役員、社員一人一人が取り戻すことこそ再発防止のスタートラインであり、かつ、技術の底上げをはかるための必須条件である。日野自動車、そして、業界はあらためて原点に立ち返り、再発防止に取り組んで欲しい。
