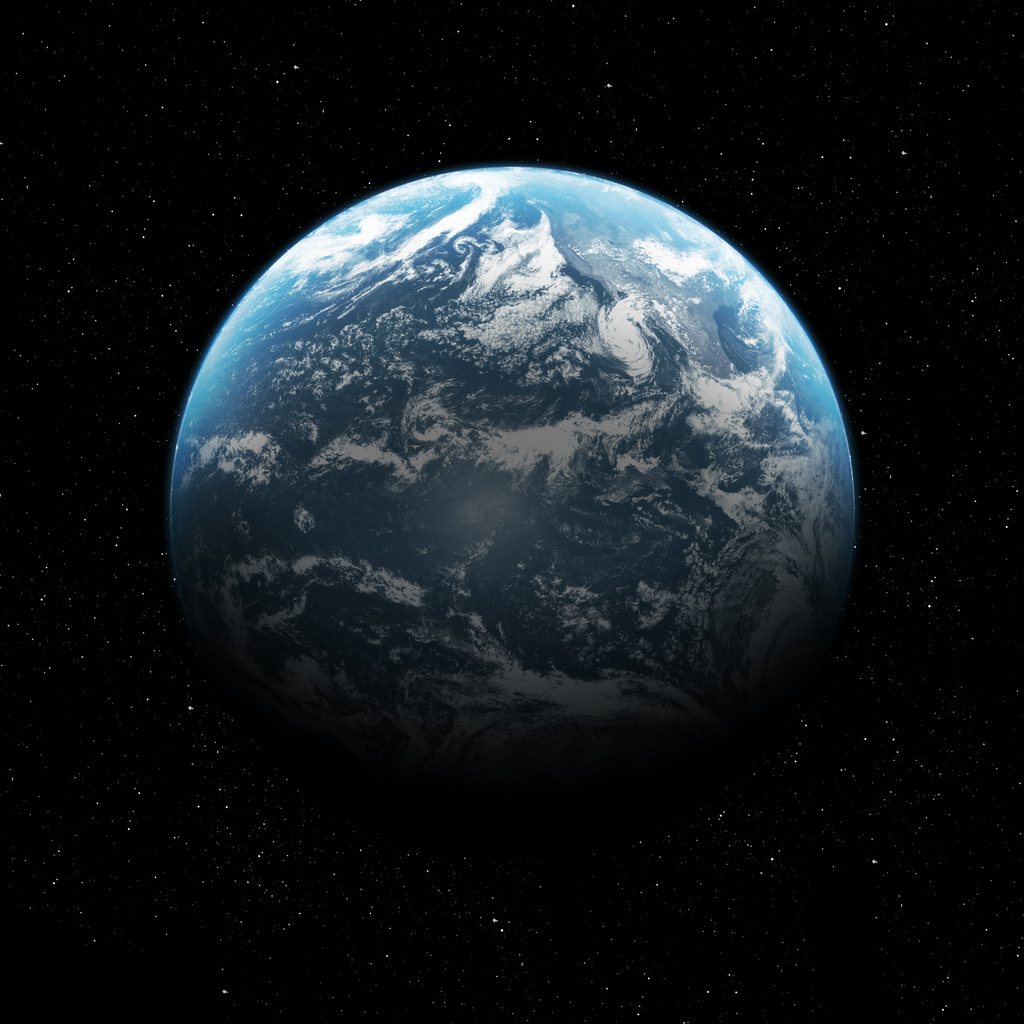
12日、国際通貨基金(IMF)は2021年の世界経済見通しを更新、前回7月時点における見通しから0.1ポイント引き下げ、5.9%とすると発表した。
今、世界経済は全体として回復基調にある。しかし、ワクチンへのアクセスが不十分な途上国と先進国の格差拡大が止まらない。IMFはこれを「深い分断が回復の足かせ」と表現、格差の広がりが世界経済にとってのリスクであり、あわせて「政策のトレードオフがより複雑になっている」と指摘する。
実際、一次産品の価格上昇、原油価格の高騰、サプライチェーンの目詰まり、労働市場の回復の遅れ、インフレ、通貨安など、世界経済における不確実性とリスクは高まっている。
とりわけ、急激な原油高と米国の経済回復に伴うドル高のインパクトは大きい。もちろん資源を輸入に依存する日本にとっての影響も小さくないが、財政基盤が弱く対外債務比率の高い低所得国にとってドル建て債務の返済負担増は国民経済を揺るがしかねないだけに深刻だ。
そうした中、今月末には第26回国連気候変動枠組み条約締結国会議(COP26)がグラスゴー(英)で開幕する。会議に先立ち国際エネルギー機関(IEA)は「世界エネルギー見通し2021」を発表、2050年のゼロエミッションを達成するためには途上国への更なる支援が不可欠であり、2030年までに現在の3倍以上、年間4兆ドルの投資が必要であるとする。そのうえで、投資が軌道に乗れば風力タービン、ソーラーシステム、リチウム電池、燃料電池など再生可能エネルギー関連産業の累積市場機会は27兆ドルに達するとし、2050年単年度だけでも現在の石油産業の市場規模を上回る収益が獲得できるとの試算も公表した。
今、世界は争うように新型コロナウイルスからの経済再生を急ぐ。格差が広がる一方、一早く消費を回復した先進国の需要にエネルギー供給が追いつかない。石炭火力回帰の動きも出始めた。経済成長と気候問題の相反を主張する声も再び聞こえてくる。しかし、大きな流れは変わらない。経済見通しを下方修正したIMFも「世界にとっての緊急優先事項は気候変動による負の影響を抑えることにある」と明言する。パンデミックは、世界共通の危機を克服するための最大の障害が格差と分断にあることを浮き彫りにした。COP26の利害対立は更に複雑だ。それゆえに、それを解きほぐすための多国間協調が必須だ。地球の命を2050年から先へつなぐためにも世界の正気と知恵に期待したい。

中国雲南省昆明で開催中の国連生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)は、13日、「昆明宣言」を採択、2030年までに生物多様性の損失を逆転させ、回復すると宣言した。オンラインとの併用で開催された今回の会議は、来年4月に予定されているリアルでの本会議に向けた言わば “前哨戦” だ。公表された目標は21項目、2030年までに陸域と海域の30%を保護地域とすること、農薬の使用制限、侵略的外来種の侵入防止、途上国に対する支援策などが協議される。
COP15は、2010年のCOP10「愛知目標」の成果を踏まえて、次の10年間の目標を採択する重要会議である。とは言え、その愛知で合意した20項目は “一部達成” が6項目、14項目は “未達” という状況だ。昆明の21項目はそれを更に上回るものであり、実現に向けてのハードルは高く、かつ、経済成長を優先させたい発展途上国と先進国との溝を埋める作業の困難さも想像に難くない。
また、生物資源を安価で買い付け、利用し、消費する先進国と途上国の対立も根深い。COP10では “遺伝子資源の取得とその利用から生じる利益の公正な配分” を主題とした「名古屋議定書」も採択されたが、そもそも医薬やバイオ産業の利益を守りたい米国がCOPに参加しない理由がここにある。
オンラインで会議に参加した習近平氏は途上国支援のために15億人民元を拠出、「昆明生物多様性基金」を設立すると発表した。米国不在の国際会議において、とりわけ途上国に対して中国の多国間主義をアピールする外交戦略の一環とも解せる。とは言え、例えそうであっても、合意形成に道筋をつけることが出来るのであれば歓迎だ。
生物多様性の喪失は、生態系全体の微妙なバランスを崩すことにつながる。結果、人間社会と野生動物との不自然な接点が増え、そこが新たな感染症の発生源になる。SARSや新型コロナウイルスも動物由来との説が有力だ。
名古屋議定書はその第8条で “人の健康に損害を与える差し迫った緊急事態であると国際的に認められた事態” に対して “特別な考慮” を要請している。つまり、動物由来とされる病原体に関する情報の共有や研究成果の公正な分配も重要テーマであるということだ。
議長国である中国には生物多様性の回復に向けての実効性の高い枠組みづくりと、今、まさに世界が戦っている動物由来の感染症に関する情報開示を期待したい。
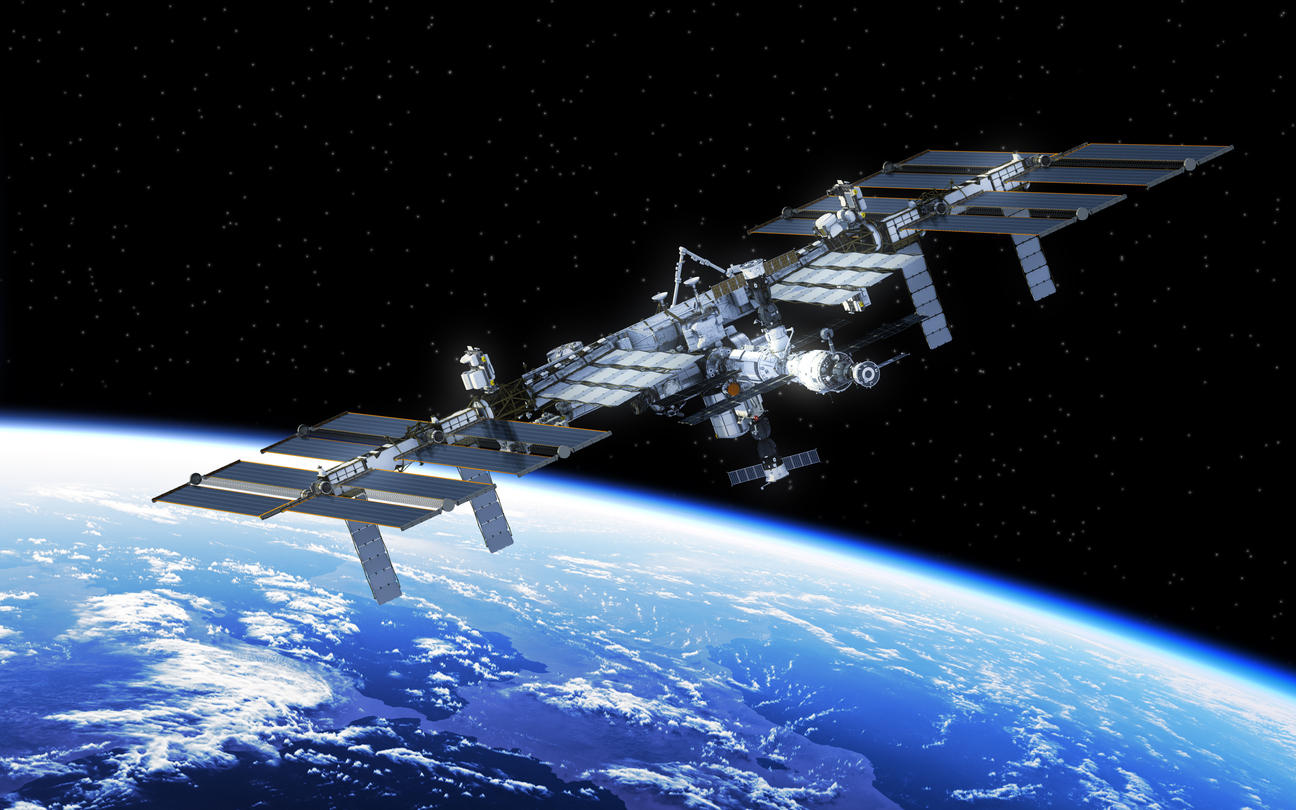
2021年夏、地上における移動の自由が新型コロナウイルスによって奪われる中、民間による宇宙への扉が大きく開かれた。7月11日、ヴァージン創業者リチャード・ブランソン氏らを乗せた有人宇宙船「ユニティ」が試験飛行に成功した。その10日後にはアマゾン創業者ジェフ・ベゾス氏が、自らが創業した宇宙ベンチャー「ブルーオリジン」社の「ニューシェパード」に乗船、5分間の無重力を体験した。そして、先月、テスラ創業者イーロン・マスク氏の「スペースX」社が民間人のみを乗せた宇宙船「クルードラゴン」の打ち上げに成功、3日間の地球周回旅行を楽しんだ後、無事地上に帰還した。
「有人」という壁はあるものの、日本勢の可能性も大きい。ロケット、人工衛星、ソフトウェア、通信・放送、観測、デブリ除去など、製造から利用サービスまで、日本の技術は世界有数のレベルにある。そこに新たな「本命」が加わる。30日、Hondaが宇宙事業への参入を表明した。2020年代の打ち上げを目指し、小型ロケットを開発する。ロケットは低軌道向け小型人工衛星を搭載、自動運転技術で培った制御・誘導技術を活用し再利用型とする、とのことである。
また、電動化技術を応用した電動垂直離着陸機(Honda eVTOL)や分身ロボット(Hondaアバターロボット)の開発も強化する。
前者のコンセプトは、都市内移動にとどまらず都市間移動を実現することにある。そのためには長い航続距離が必要であり、これを実現すべくガスタービンとのハイブリッド方式を採用する。あくまでも実用本位で電動に拘らないあたりがホンダ的だ。独創的な設計思想で世界を驚かせたHonda Jetの技術が活かされる。後者は、言うまでもなくASIMOの技術と経験が土台となる。こちらは月面遠隔操作ロボットへの応用も想定される。
“宇宙“ は、国の威信を競う場であり、また、安全保障上の要衝でもある。とは言え、「地球の子供たち、聞いてくれ。かつては私も星を見上げる少年だった。しかし、今、大人になって、ここにいる」と屈託なく感動を表現するブランソン氏の笑顔や「人類を多惑星種にしたい」などと語るマスク氏の夢と自信こそがイノベーションの原動力である。
Hondaの宇宙開発も「コア技術を生かして小型ロケットをつくりたい」という若手技術者の発案がきっかけであったという。「チャレンジを恐れるな。何もしないことを恐れろ」、宗一郎氏の他界から30年、創業者の想いが継承されていることが嬉しい。

総額33兆円、中国の名目GDPの2%に相当する巨額債務を抱える不動産大手「恒大集団」の経営不安が深刻化しつつある。
変調の転機は昨年夏、中国当局は市場の過熱を抑えるべく融資条件の厳格化と住宅ローンの総量規制を導入、新たな資金調達を封じられた同社の拡大戦略は反転、今月から年末にかけて社債利払いが集中する中、経営危機が一気に表面化した。
中国版バブルの起点は2008年、リーマンショック後の世界不況を救った4兆元(約57兆円)の財政出動である。ここから民間債務は一挙に、そして、一貫して拡大を続けてゆく。恒大集団の香港証券取引所への上場はその翌年、以後、高騰を続ける不動産を担保に資金調達と再投資を繰り返し、プロサッカークラブから観光、金融、EV事業まで年商10兆円、従業員300万人を越える巨大企業集団へ成長する。まさにバブルの申し子である。
ただ、恒大集団の財務リスクは既に社債利回りなどに織り込み済であり、また、ドル建て債務は全体の6%程度と言われている。同社のデフォルトが世界の金融システムに与える影響は限定的であろう。問題は、過剰債務は恒大集団に固有のものではない、ということだ。不動産関連産業はGNPの1/4を占める。加えて企業、家計、政府の債務残高は2020年7-9月期でGDP比285.1%(国際決済銀行)に達している。恒大集団の破綻が信用収縮の連鎖の起点になること、ここにリスクの本質がある。
とは言え、国内の格差拡大を背景に “共同富裕” の理念を掲げる習指導部が恒大集団を公的資金で救済するとは考え難い。一方、処理を誤ると経済全体の停滞を招く可能性があり、結果的に社会不安を増大させかねない。世界の実体経済にとって総額2兆556億ドル(2020年輸入実績、中国税関総署)の “買い手” である中国経済の低迷が与える影響は大きい。しかし、それ以上の懸念は、国内に溜まった不満の矛先が “外” に向けられることである。俎上にあるのは台湾だ。双方からほぼ同じタイミングで表明されたTPPへの加盟申請はその火種になりかねない。適応、譲歩、特例、懐柔、分断、排除、攪乱、、、交渉に際してはあらゆるシナリオが想定されているはずだ。しかしながら、TPPは “ルールの統一” と “例外なし” が原則である。既存加盟国はこれを愚直に固守し、TPPを強権的な行動の契機とさせないよう望む。

9月9日、東京電力は、増設多核種除去設備(増設ALPS)の排気フィルタ25箇所のうち24箇所で損傷が確認されたこと、作業員に身体的汚染がなかったこと、周辺環境への影響は確認されていないこと、引き続き原因調査を行うことを発表した。
これに対して原子力規制委員会は、同様の損傷が2年前にもあったこと、それが公表されなかったこと、原因分析や対策が取られないまま運転が継続されていたことを問題視し、東京電力の安全に対する姿勢をあらためて批判したうえで、再発防止を指示した。
東京電力は、2002年に発覚した点検記録の不正問題を受けて、情報公開、透明性の確保、企業倫理の遵守、社内監査の強化を公約した。東日本大震災も経験した。それでも社風は変わらない。今年3月には柏崎刈羽原子力発電所でテロ対策の不備が発覚、原子力事業者としての適格性が再び問われた。この時、筆者は本稿で「原子力産業に根付いた安全神話という“聖域”の除去こそが最優先課題である」(2021年3月19日)と書いた。東京電力もまた「高い緊張感をもって安全に対する文化を再構築」したはずだった。
5月、会計検査院は、環境省が実施してきた除染モニタリング事業について、「福島県内56万地点のうち1万3千地点で除染効果を確認できなかった」と発表、同省に測定方法の改善を要請した。本来、測定は除染作業終了後、半年から1年内に実施されるべきとされていたが、測定間隔は90日未満から700日以上までと大幅な差異が生じており、1年以上の地点も全体の22%に及んでいた。
また、汚染土壌の保管台帳にも事実と異なる記載が見つかっている。汚染土壌の埋設地に住宅が建設されるなど、不適切な管理実態も浮き彫りになった。
福島第一原子力発電所の処理水や汚染土壌の問題はもっともデリケートな事案であるはずだ。風評被害の問題も、その根底にあるのは情報の正確性と透明性に対する不信だ。にもかかわらず事業者も行政もどうしてここまで、そして、いつまでも杜撰かつ不誠実であり続けるのだろうか。かつて“聖域”であったがゆえの驕りなのか、あるいは、安全神話の残像への妄信なのか。いずれにしても発表される情報の正確性はもちろん、“すべての情報が公開されている”ことに対する信任を社会が取り戻さない限り、フクイチはいつまでたっても“科学”の議論になってこない。

8月30日、香川県三豊市の須田港と粟島を結ぶドローンによる定期貨物便の運航がはじまった。運航を担うのは離島が抱える物流課題の解決に取り組む高松市のベンチャー「株式会社かもめや」、この6月に三豊市と協定を締結し、定期運航の実現に向けて準備を進めてきた。
須田港の沖合4.2キロに位置する粟島は、132世帯、216人の島民が暮らす。高齢化率は83%、人口は10年前と比べると4割減少し、高齢化率は10ポイント増えた(平成27年国勢調査)。定期船の航路はあるが、過疎化が進行する中にあって生活インフラの維持が大きな課題だ。
スタートしたばかりの定期便の積載量は1㎏まで、購入できるのは提携コンビニの商品に限定される。運行は週5日、1日3便、手数料は500円、午前に注文すれば午後には商品が届くという。品物はスタッフが戸別配送、注文は電話や専用の注文票で行えるなどITに不慣れな高齢者に配慮した事業モデルとなっている。
計画では年度内に雨天でも運航できるよう機体の防水化をはかるとともに、来年中には積載量を5㎏まで増やすという。将来的には医薬品の輸送や無人操縦船の導入も視野に入れる。
日本の有人離島数は416島、うち離島振興法の対象は254島、そこに37万6千人が暮らす(平成27年国勢調査)。急速な過疎化と定期航路の縮小が続く中、医療体制や日常生活における利便性の維持は共通の問題である。ドローンによる定期貨物便の就航は他の島民にとっても大きな希望となろう。
問題はいかに事業を継続させるかという点にある。言うまでもなく需要量そのものの安定した確保が不可欠である。定住人口の拡大は容易ではない。まずは観光振興、そして、地域特性を活かした関係人口づくりが求められる。そのためには自然や歴史、暮らし、文化など地域資源の再発見にもとづく島の魅力の再定義が必須であろう。
その意味で先端テクノロジーの活用はそれ自体が新たな地域資源になるはずだ。単なるコストや効率化とは異なる視点で、豊かな自然と共生する「過疎」におけるテクノロジーの新たな可能性を引き出して欲しい。
