
4月21日、日本郵政は豪の物流子会社トール社の豪州国内とニュージーランドにおける企業向け物流と宅配事業の売却を発表した。売却額は7億円、2021年3月期連結決算で特別損失674億円を計上する。業績低迷が続いたトール社については2017年には既に4,000億円を超える減損処理を行っている。残ったトール株の簿価は1,000億円、負債は2,000億円、鳴り物入りでスタートした成長戦略は完全に頓挫した。
日本郵政がトール社買収を発表したのは2015年2月。投資額は6,200億円、主導したのは東芝時代にウェスティングハウス買収を手掛けた故西室 泰三氏(当時社長)だ。氏は買収発表の会見で「内需で成長できる時代は終わった。グローバル企業への第1歩を踏み出す」と高らかに宣言するとともに「責任は経営陣がとる」とも明言した。
しかし、結果は上記のとおりで、かつ、大型買収、巨額減損、負の遺産の中で発覚する不正問題、という流れも東芝と類似する。西室氏への批判は小さくない。しかし、根底には氏の決定を是とした “時代の空気” があった。グローバル化、選択と集中、強いリーダーシップへの称揚は “失われた20年” を取り戻すための日本全体の焦りであったと言えるかもしれない。
さて、西室氏がトップを務めた東芝と日本郵政はいずれも国策の一端を担う企業である。しかし、決定的な違いは日本郵政のオーナーシップは国が持っている点にある。国は日本郵政株式の6割を保有する大株主であり、つまり、日本郵政による投資の失敗は国民にとっての損失ということだ。
先月、日本郵政は楽天グループとの資本業務提携を発表した。日本郵政は1,500億円を楽天に出資、出資比率8.32%の大株主となる。一方、楽天は中国IT大手「騰訊控股(テンセント)」からの出資も受け入れる。同社は子会社を通じて657億円を出資、出資比率は3.65%となる。これに対して、日本と米国の両政府は経済安全保障上の観点から楽天グループを共同監視下に置くとの報道があった。そうなると監視者である国を株主とする日本郵政が、監視対象である楽天グループの大株主として警戒対象企業であるテンセントと “同居” していることが新たな問題となる。
政府は昨年、安全保障上の懸念を有する企業への出資に対して、外資に義務づけた事前届出の出資率基準を10%から1%に引き下げた。しかし、テンセントは楽天への出資に際して株式の保有目的を「純投資」であると表明、純投資であれば事前届出は免除される。規制は強化したが運用上の課題が残ったということだ。ここに利益相反の懸念が生じる。テンセントを介した中国への情報流出は国益の損失と言えるが、そうした行為が実際に行われ、それを国が捕捉し、何らかの措置を講じたとすれば、楽天の企業価値は棄損する。つまり、その場合、日本郵政を通じて楽天に投資された国の資産は目減りするということだ。
今回の楽天との一件は、改正外為法の運用上の課題と日本郵政のガバナンスの問題を浮き彫りにした。あらゆる投資スキームを想定したうえで、こうした不透明さと矛盾の解消を急いでいただきたい。

英投資ファンドCVCキャピタル・パートナーズが東芝に対して非上場化を前提とした買収提案を行ってから1週間、東芝は車谷社長の辞任と綱川会長の社長復帰を発表した。
会見では「あくまでも本人の意思による辞任」と説明されたが、“物言う株主” との対立や社内における求心力低下に業を煮やした取締役会から何らかの圧力があっただろうことは想像に難くない。また、車谷氏の “元CVC日本法人会長” という経歴が「古巣のファンドを使った資本市場からの逃避」との批判につながったことも無視できなかったはずだ。辞任は実質的な更迭と言っていいだろう。
東芝の転落は2015年の「会計不正問題」が起点となる。ここから歴代3社長の辞任、米原発子会社の巨額損失、債務超過、東証2部への降格、と迷走が続く。そして、2017年12月、債務超過を解消し上場を維持すべく6千億円の増資を実行、約60社におよぶ海外ファンドが株主に加わった。その陣頭指揮に立ったのが当時のトップ、綱川氏である。
翌2018年、経営を引き継いだ車谷氏は不採算部門からの撤退など構造改革を断行、業績回復に道筋をつける。2020年11月、こうした流れの中で氏は新たな中期計画と資本配分政策を発表、この1月には東証1部への復帰も果たした。しかし、株主還元より戦略投資に軸足を置いた新たな経営戦略が「物言う株主」との対立を先鋭化、それが今日の導火線となる。
その東芝を再び綱川氏が率いる。就任に際して氏は「ステークホルダーと良好な関係を築く」とコミュニケーション重視の姿勢を表明、社内外からの信頼回復を目指したい、と抱負を語った。とは言え、ステークホルダーの利益は一様ではない。それぞれの意向を組みとるだけではいずれの側にも不満が残る。「原子力や国防を担う東芝が外資の傘下に入っていいのか」など政治の声も聞こえてくる。改正外為法の問題もある。産業革新投資機構、日本政策投資銀行といった政府系金融も何らかの役割を担うことになるだろう。それぞれの思惑が交差する中、東芝は真に独立、自立した企業として成長戦略を描くことが出来るか。すべてのステークホルダーを納得させ、統治能力を自らの手に取り戻すにはこの1点しかない。
綱川氏は、東芝メモリの買収を巡って日米韓連合と米半導体ウエスタンデジタルが争った際、「決められないトップ」と揶揄されたことがある。件の増資の折には「東芝を外資に売った」とも評された。会見では「反省すべき点は反省し、社風も変え、次世代につなぎたい」と述べた。「経営陣も株主も同じ目線」との発言もあった。ただ、信頼回復は目標ではない。結果だ。“目線”は徹底して「東芝ファースト」であってほしい。綱川氏の覚悟に期待したい。

4月6日、国際通貨基金(IMF)は2021年の世界成長率予測を1月発表の+5.5%から+6%に上方修正した。IMFは「コロナ対策関連の大規模な経済対策効果もあり、経済の崩壊は阻止された」と声明、ワクチン接種の進展によってこれまで押さえられてきた累積需要が顕在化すると予測する。また、米バイデン政権による210兆円規模の追加経済対策も米国内のみならず貿易相手国への波及効果が大きいと評価した。
その1週間前、世界貿易機関(WTO)も2021年の世界貿易について「欧州、北米、中国を中心に貿易量は回復、前年比+8%を見込む」と発表、景気回復に自信を見せた。しかし、新型コロナウイルスの変異種の拡大など感染終息の見通しが立たない状況を踏まえ、「財政出動だけでは危機は終わらない」との懸念も表明、「新興国、途上国を含むワクチンの公平な普及が最良の経済策である」と指摘した。この点はIMFも言及しており、低所得国、新興国の感染対策への支援を先進諸国に強く要請する、としている。
一方、IMFは増大した財政支出の圧縮や増税など財政再建に向けての急激な政策転換による景気後退懸念も表明、各国にソフトランディングを求めた。財政問題については、米イエレン財務長官も別の視点から言及した。イエレン氏は危機対応には大型の投資が不可欠であり、そのためには十分な財源が必要であると指摘したうえで、「法人税率の過度な引き下げ競争は止めるべき、国際的な最低税率の導入を」と呼びかける。
多くの国で感染は未だ進行形である。欧州や日本も再拡大の只中にある。一方、世界経済の回復もまた確かなものになりつつある。世界はパンデミックを押さえ込むために更に大きな資金と強い規制を必要としつつ、一方で出口戦略に向けて歩みを速める。
こうしたちぐはぐさとワクチンをめぐる利権と国力差が、新たな不均衡と分断を生み出す。分断は否が応でも大国の対立構造に組み込まれる。アフターコロナの世界にとっての最大リスクがここにある。
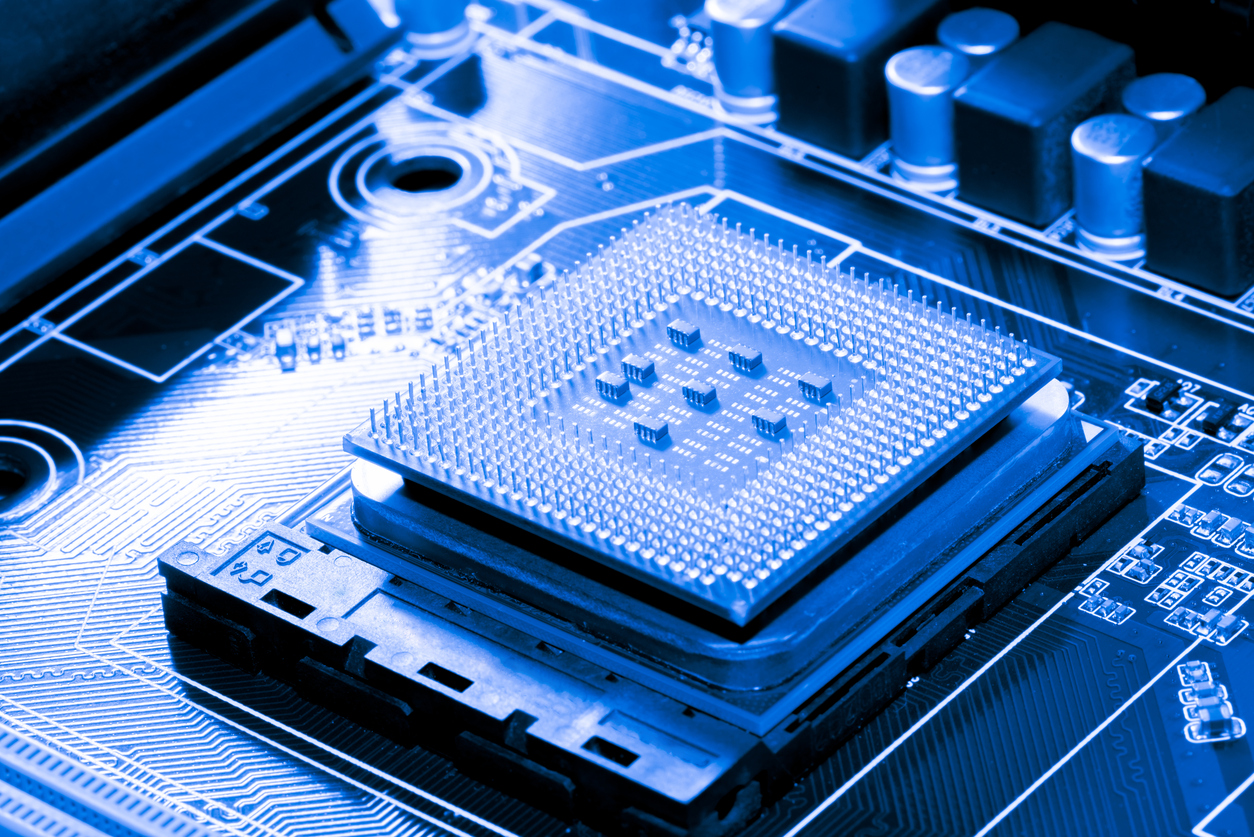
3月30日、ルネサスエレクトロニクスは火災により生産停止中の那珂工場について「1か月以内に生産を再開する」としつつも、被害を受けた製造装置の台数を11台から23台に修正、「火災前の出荷水準の回復には3-4か月かかる」との見通しを発表した。しかし、使用不可となった製造装置の納入時期は「現在、交渉中」とのことであり、世界的な半導体不足の中、大幅な生産調整を余儀なくされている自動車業界の不安が解消されたとは言い難い。
そもそも自動車メーカー向けの世界的な半導体不足はなぜ起こったのか。原因の一端は、やはり米中対立と新型コロナウイルスである。米国は中国の半導体受託生産メーカーに制裁を適用、これにより注文は台湾メーカーに集中した。一方、台湾メーカーは世界的な感染拡大を受けて自動車需要の低迷を想定、社会のリモート化や5G投資の拡大を見込んだ生産計画を立てた。ところが、中国市場がけん引する形で自動車向け需要が急回復、結果、極端な需給ひっ迫状態に陥った。そこに北米の寒波、停電が追い打ちをかける。
こうした状況を受け、米国や日本、ドイツなど各国政府も外交ルートを通じて、台湾政府経済部に車載半導体の増産を要請、台湾側も半導体受託生産メーカーに対応を指示してきた。メーカー側もこれに応じ、「生産能力のフル稼働を維持するとともに自動車向けを優先する」と表明している。とは言え、最大手の台湾積体電路製造(TSMC)でも自動車向けの比率はもともと数%程度に過ぎない。主力の需要先はスマートフォン、ゲーム機、PC、データセンター向け高性能サーバーである。そもそも取引条件が厳しく、利幅の薄い自動車メーカーは彼らにとって “上顧客” ではない。自動車メーカーに先んじて発注をもらった大事な顧客を後回しには出来ない、というのが本音であろう。
電気自動車(EV)、先進運転システム(ADAS)など、テクノロジーの進化とともに自動車産業は大きな構造変化の渦中にある。変化とは、単に内燃機関の技術をもった下請企業がエレクトロニクス関連のそれにとって代わるだけではない。やがてサプライチェーンにおける最上位の地位そのものが危うくなるということだ。半導体不足による減産はクルマを頂点とした産業ピラミッドの “綻び” と言って良いだろう。トヨタは、2018年のアニュアルレポートで「クルマをつくる会社から、モビリティカンパニーに変革する」と宣言、「CASE、MaaSの時代の競合相手はGAFA」と明言した。「100年に一度の大変革」とはつまりそういうことであって、今、目の前で起こっている事態は決して一過性のものではない。

2020年、主要国で唯一プラス成長(+2.3%)を達成した中国は、2021年の成長目標を「6%を上回る水準」に設定した。はたして中国経済は当局の発表どおり回復しているのか。実態はどうなのか。当社上海現地法人から最新の報告が届いた。報告書は「個々の産業や企業活動において相違はある」「当社現地法人のネットワークの範囲内での見解」としつつも、「中国経済は確実にV字回復している」と結論づけた。以下にその一部を紹介させていただく。
・2020年、素材関連企業の出荷量は前年水準を回復、出荷金額は前年比30~40%増・大型工作機械や生産ラインの自動化など生産部門における投資が活発化、日系の現地法人の中には受注が満杯で納期遅延を余儀なくされるところも出てきた。
・船便、コンテナ輸送の需給がひっ迫、海上輸送費は2019年比200~250%へ高騰
・輸出型のローカルアパレルの業績は低迷、一方、百貨店も苦戦、ECへのシフトが加速している。
・国民の一人当たり可処分所得は名目32,189元、前年比104.7%(実質102.1%)。一方、一人当たり消費支出額は名目21,210元、前年比98.4%(実質96.0%)
・物価は衣料品を除き軒並み上昇、この2月は新型コロナウイルス拡大前の2019年2月比で、食材150~170%、タクシー代110~115%、光熱費110~120%
・上海市内の日常生活はほぼ正常化したが、会食や旅行の自粛は続いている。しかし、5月連休には需要は大幅に戻るものと予測する。
・感染対策は依然として強力。ある団地で感染者が発生すると団地全体を2週間ロックアウト(封鎖)し、政府費用で住民全員にPCR検査を受診させる。封鎖期間中は食料品など生活必需品に対して補助金を出すなど一定の補償策を講じることで隔離の徹底をはかっている。
・上海では3月25日から高齢者向けのワクチン接種がスタート、4月1日からは上海在住の外国人向け接種もはじまる予定。上海市の区体育所には突如テントが設置され、わずか1日でワクチン接種会場に早変わりした。
新型コロナウイルスはグローバル・サプライチェーンのリスクを露呈させた。チャイナプラスワンの流れは加速するだろう。一方、“市場” としての中国への投資は今年に入ってからも旺盛だ。武田薬品工業は2031年までに中国を含む新興国売上を現在の2倍、1兆円に引き上げると表明した。既に海外売上高の5割を中国に依存する大王製紙は新たに生理用品市場へ参入する。高級品市場への「選択と集中」を発表した資生堂の戦略市場は中国である。ファナックは260億円を投じて中国国内向け産業用ロボットの生産強化をはかる。トヨタもまた中国におけるEVの生産能力の増強を発表、更にFCVの基幹システムの現地生産も視野に入れる。
米EV大手、テスラも中国に積極投資してきた一社だ。市場での人気は高く、購入予約は常に満杯状態である。2020年には世界の販売台数の3割を中国市場が占め、同社初の黒字化に貢献した。中国側も用地取得や融資などを通じてテスラを優遇してきた。しかし、19日、米中が真っ向から対立したアンカレッジでの米中外相会談の直後、中国当局は「軍人と政府職員のテスラ車利用を禁止、制限する」と発表した。理由は軍事機密、国家機密の流出懸念である。ただ、一般消費者はこれを冷静に受けて止めており、現時点では市場の動きに変化はない。
22日、米、英、カナダ、EUは中国によるウイグル族への人権侵害を理由に、新疆ウイグル自治区当局者に対する制裁措置を発表した。中国は直ちに反発、報復を表明した。米バイデン政権は「同盟国との連携」を対中政策の基本とする。今、G7で態度を留保しているのは日本だけである。一方、中国も「中日関係の破壊」に対する懸念を表明するなど名指しで日本を牽制する。早晩、日本は決断を迫られるだろう。その時、日系企業は新たなリスクに向き合うこととなる。

東日本大震災による原子力災害から10年、日々増え続ける膨大な放射性汚染水の処分が課題だ。現時点では海洋放出が有力視されているが、風評被害を懸念する漁業者がこれに反発する。
汚染水は多核種除去設備(ALPS)によってトリチウムを除く62の放射性核種が取り除かれる。一方、トリチウム水の海洋放出は世界の原発で半世紀以上にわたって行われており、したがって、ALPSで処理された汚染水の安全性は国際的に認められるという。トリチウム水の安全性判断は専門家に委ねるとして、懸念されるのは、そこに他の放射性物質が “本当に” 含まれていないか、ということだ。
2018年、東京電力はALPS処理水の8割強で基準値を越えたトリチウム以外の放射性核種が検出されたことを公表した。ALPSの性能が不安定な時期があったこと、吸着材等の交換が適切に行われていなかったことなどが原因の一つであると説明された。そう、問題はここだ。設備や機器は正しく運用されるのか、情報は遅滞なく公開されるのか、ということである。
不信の根源は原子力技術への盲目的な信仰が「安全神話」という聖域を作り出したことにある。聖域ゆえに異論は封じられる。2006年12月、第165回国会で原発の安全性に関する議論があった。「巨大地震に伴って発生する津波によって冷却機能が失われる可能性がある」「大地震に備えたバックアップ電源の強化が必要」と野党議員から指摘された安倍氏は「我が国では過去にそうした事例はなく、安全には万全を尽くしており、そうした事態が発生するとは考えられない」などと答弁し、追加的な安全対策の必要性を否定した(平成18年12月、質問第256号、答弁第256号)。神話がそのまま現実に適用されたということだ。結果は指摘するまでもない。
また、繰り返されるトラブルの隠蔽やデータ不正も “聖域は不可侵” との驕りが根底にあるのだろう、美浜1号機の燃料棒折損事故の隠蔽(関西電力)、敦賀1号機の冷却水漏れ隠し(北陸電力)、福島第1、第2、柏崎刈羽の点検記録の改ざん(東京電力)、敦賀2号機のデータ書き換え(日本原子力発電)など、電力会社を問わずきりがない。そして、この16日、原子力規制委員会は柏崎刈羽のテロ対策の不備が長期間にわたっていたことについて「極めて深刻」との評価を下したうえで、「驚くような不具合、不始末、不正が続く東京電力の体質が問われる」と断じた。
福島第1の汚染水問題について、菅首相は「適切な時期に政府が責任をもって決断する」と述べた。おそらく、海洋放出が念頭にあるものと推察する。他に選択肢がなく、放出される汚染水の安全性が科学的に担保されるのであれば異論はない。しかし、漁業者、国民、世界を納得させるためにはまずは “聖域の除去” こそが最優先課題である。ムラ社会の閉じた因習を断ち、かつ、原子力行政の責任の所在を明確にしておくことが肝要だ。ここに対する信任がない限り、不信と分断、風評被害は終わらない。
