
2月24日、政府は、今国会での承認を目指すべく東アジアの地域的な包括的経済連携(RCEP)協定案を閣議決定した。RCEPはアジア15ヵ国が参加する広域経済連携協定で中韓と日本が締結するはじめてのEPAでもある。発効すれば世界のGDPの3割を占める経済連携協定となること、デジタルデータに関する域内流通や進出企業に対する技術移転要求を禁じるといった共通ルールに中国が参加したことの意味は小さくない。
同じ日、その中国は、環太平洋経済連携協定(TPP)加入に向けて加盟国と非公式折衝を開始したことを明らかにした。TPPについては昨年11月に習近平氏自ら「積極的に検討する」旨の声明を出しており、今回の発表はそれが実務レベルで進んでいることをアピールしたものと言える。とは言え、知的財産、労働者の権利、環境、国有企業条項を含むTPPは中国にとってハードルは高い。しかし、検討そのものが米国復帰への牽制との見方もあるし、TPP加盟国の中には中国との関係が深く、かつ、RCEPに参加する国もある。中国はこうした国との水面下での折衝を通じて、一定の例外規定を取り付けることの可能性を探っているのかもしれない。
そして、米国。やはり同日、バイデン氏は半導体、鉱物資源、電池など重要部材の供給網を見直す大統領令に署名した。日本、台湾、韓国、豪州などアジアの同盟国と連携し、中国への依存度を引き下げる。バイデン氏は「価値観を共有できない国に調達を依存すべきでない」と発言、脱中国の姿勢を鮮明にする。
トランプ氏が去り、国際社会への復帰を急ぐ米国であるが、対中国のスタンスは変わらない。対立が先鋭化すればするほど、“ディール” における損得が基準であった前政権より、大義や原則により忠実な現政権の方が “後に引けない” 状況に陥り易いかもしれない。
こうした中、新疆ウイグル自治区における中国の人権問題への批判が高まる。欧米企業に続き、日本企業も少数民族の弾圧に関与した現地企業との取引を中止する、との報道があった。RCEPへの参加で更なる成長が期待された “アジア最後のフロンティア” 、ミャンマーの混乱も続く。米国は国軍によるクーデターを直ちに非難、一方の中国は「ミャンマー国内の内政改革」との立場を貫く。
自由、民主主義、人権、ジェンダー、環境、そして、安全保障。多国間経済連携の枠組みは経済合理性を越えた “価値観” を軸に実質的な再編に向かいつつある。未来のシナリオはもう一段複雑になった。

2月16日、曙ブレーキ工業は国内で製造する自動車用ブレーキ製品の検査に不正行為があったと発表した。不正は国内4工場で約20年にわたって行われてきたとし、完成車メーカーに報告された19万件の約6割、11万件で不正が確認された。
国内メーカーの品質不正が後を絶たない。近年では2017年に発覚した神戸製鋼所のアルミ製品の事案が記憶に新しいが、これ以降も日産、SUBARU、宇部興産、日立化成、スズキ、KYB、東洋ゴム、住友重機、IHIなど、日本を代表するメーカーやその関連会社においてデータの改ざん、試験条件の逸脱、試験の未実施が相次いで発覚する。いずれも一定期間以上の長期に及んでおり、 “メード・イン・ジャパン” に固有の構造問題であるとの批判は免れまい。
不正発覚直後の、「多大なるご迷惑とご心配」を詫びる経営トップの姿はもはや日本産業界の風物詩とも言えるが、繰り返される “お詫び” も一向に他山の石とはならないようだ。
今回、曙ブレーキの記者会見では「製品の性能に問題はなく、リコールには発展しない」とのコメントがあったが、検査不正を起こした多くの企業に見え隠れするのは「機能的に必要な品質は担保されており、ゆえに問題はない」との自己正当化の論理である。もちろん、過剰品質を要求する側にも問題はあるが、所謂 “擦り合わせ” に象徴される日本のものづくり業界特有の取引慣習が双方に甘えと驕りの風土を醸成させてきたと言える。
2018年11月、日立化成の調査委員会もこの点に言及した。その一部を要約すると、「日立化成では “規格値を外れても実際の性能には影響がない” との慢心のもと顧客の要求には表面上従っておくという、言わば面従腹背の姿勢で不正が行われていた」と顧客に対する背信行為を指弾、過去の独禁法違反を引用しつつ、「顧客からの要求やプレッシャーに正面から向き合うことを避け、安易に顧客に迎合する姿勢が、一方で従業員をカルテル行為に走らせ、他方で検査データの改ざんに走らせた」と断じる。
そのうえで、「顧客の側にもサプライチェーンを展望した責任を果たすことと相容れない態度があり、日立化成も対応に苦慮したケースがある」と優越的地位にある顧客側の問題点を指摘、「サプライチェーンを構成するすべての当事者が協働して、我が国のものづくりの信頼回復を実現して欲しい」と結ぶ。まさにその通りである。しっかりしてくれ、日本製造業。

2月1日の軍事クーデター以降、ミャンマーでは軍事政権に対する市民の抗議デモが続く。時計の針を戻したくない、との必死の思いが報道から伝わってくる。
1988年、民主化運動は四半世紀に及んだネ・ウィン政権を退陣に追い込む。しかし、その直後、軍は民主派勢力を武力で制圧、政権を奪う。そして、2015年、再び四半世紀を経て非暴力民主化運動の象徴アウン・サン・スー・チー氏が国政トップの座につく。政治家としての彼女の評価は分かれる。しかし、軍への反発はその是非を越えて内外に広がる。民主主義そのものが再び暴力で封じられた理不尽さへの抵抗である。
欧米は即座に非難声明を発表、バイデン氏は軍の行動を「民主主義への攻撃」と断じたうえで経済制裁に言及した。ただ、欧米による経済制裁はミャンマーの中国への回帰を促す。スー・チー政権は対中債務の削減など中国の影響力拡大に一定のブレーキをかけてきた。しかし、それでも貿易の3割を中国に依存するなどつながりは深い。よって、経済制裁はミャンマーを完全に中国の側に押しやることになるだろう。しかし、それでも行動を起こさなければ軍事独裁を容認することとなる。日本もまた “自由で開かれたアジア太平洋” の理念にもとづく明確な行動が求められる。
キリンビールはいち早く軍の影響下にある企業との合弁解消を表明した。もちろん、米国の制裁対象に連座される可能性を回避するとの狙いもあるだろう。それでも同社の経営姿勢は内外に伝わった。「明治維新を経て、日本人は “プリンシプル” を失った」とは吉田茂の右腕、白洲次郎氏の言葉である。氏の言う “プリンシプル” とは原理原則の意に近い。もちろん、企業にとって撤退だけが選択肢ではない。とは言え、SDGs、ESGを標ぼうするのであれば、企業はその行動基準を自社の “プリンシプル” としてメッセージする必要がある。
さて、それにしても東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会、森会長の言動を巡る混乱にはほとほと辟易する。この騒動自体が時代錯誤であると言っていい。失言への不寛容を嘆くことで異論の封じ込めを試みる者、ムラの掟に阿(おもね)り、沈黙を通じて保身をはかる者たちの多さに今更ながら驚かされる。一方、少しずつではあるが当事者たちからも声が上がり始めた。ただ、スポンサー企業の動きは概して遅く、抑制的だ。新型コロナウイルスの終息に見通しが立たない中、多くの国民が東京2020大会の開催に疑問を持っている。企業も大々的な販促活動を控えざるを得ない。そうした中で起こったこの騒動は、五輪憲章の “プリンシプル” に対する自社の経営姿勢を行動で示す絶好のチャンスであったはずだ。逆説的ではあるが、企業は最大にして最良のブランディング機会を逸した。

2月2日、パナソニックは2021年3月期第3四半期決算を発表、「実質ベースで増収増益となった」としたうえで、通期業績見通しを上方修正した。
同社のセグメント業績は新型コロナウイルスに翻弄された “2020年” をストレートに反映している。第1四半期はオートモーティブ部門を筆頭に全部門が前年割れとなったが、第2四半期に入ると自動車販売の復調を受けてオートモーティブがV字回復、アプライアンスやホームソリューションは空調空質、除菌衛生、巣ごもり需要に押し上げられ、インダストリアルソリューションも通信インフラ、蓄電システム関連が伸長した。一方、コネクテッドソリューションは航空機用電子機器の落ち込みをカバー出来ず減収減益を余儀なくされた。
パナソニックは長く構造改革に取り組んできた。2019年には液晶パネル事業と半導体事業からの撤退を表明、今回も上記決算発表のタイミングで太陽電池事業からの撤退を発表した。決算説明会ではこうした一連のリストラを踏まえて「経営体質強化の取り組みが着実に進捗、加えて、社会変化を捉えた事業の増販が寄与した」と胸を張った。
また、テスラ事業も黒字化に見通しが立った。パナソニックは2,100億円を投じてテスラ向け車載電池工場「ギガファクトリー1」(米ネバダ州)を建設、2017年から供給を開始したがこれまで赤字が続いていた。昨年7-9月期、主力車種「モデル3」の好調を受け、ようやく黒字に転換、通期黒字の達成が確実となった。昨年6月には百数十億円規模の追加投資を決定している。
とは言え、そのテスラも電池の内製化に動いており、中国のCATL、韓国のLG化学も車載電池事業への投資を強化する。パナソニックとしては中韓勢との価格競争は避けたいところであるが彼らの技術力も侮れないし、やがて普及期に入るEV市場にあって価格は重要な競争要件である。消費者に届かない “高品質” に意味はない。グローバル市場を戦い抜くための長期戦略が問われる。
パナソニックは2022年度にはカンパニー制を再編し、持株会社制に移行する。大胆な権限移譲、自主責任経営の徹底をはかることで「専鋭化」を加速するとのことである。とは言え、各事業会社には、効率一辺倒の “選択と集中” で小さくまとまって欲しくない。グローバル市場の中で真に力強い成長を実現するためにも持株会社の戦略的な “覚悟” に期待したい。

今やすっかり定着した “コロナ禍” という言葉が使われ始めたのは昨年の2月中旬、スポーツ紙やタブロイド判の夕刊紙が起源だそうだ。「専門家会議」の初会合が2月16日、都知事が大規模イベントの中止を要請したのが21日、まさに感染拡大が “対岸の火事” ではなくなりはじめた頃である。さて、筆者はこの “コロナカ” という語感がどうも馴染まない。あまりにも茫洋として、あまりに他人事で、それでいて自分も危機の当事者であることを伺わせるように使われることが多いこの言葉が好きになれない。確かに便利な言葉である。パンデミックによる社会的危機、経済的損失を一言で総称する見事な合成語である。しかし、企業や個人はそれぞれの事業、それぞれの生活において、個々に “禍” と戦っているわけであり、つまり、一括りにされることへの嫌悪が、筆者が感じる違和感の正体なのかもしれない。
さてそれはさておき、その “コロナ禍” の長期化は、特定業種を越えて日本経済の土台を蝕みはじめつつある。2020年の休廃業・解散社数は約5万件、過去最多である(東京商工リサーチ)。自営業者の休業者は11月時点で26万人、前月の23万人から26万人へ再び増勢に転じた(総務省)。緊急事態宣言が続く中、彼らは事業を再開できるであろうか。一方、大企業の体力も奪われつつある。上場会社の希望退職募集数が2万人を越えたとの報道もあった。信用保証付き融資の新規承諾件数も依然として高水準を維持、11月は約9万件、前年比167%となった。保証債務の残高は39兆円(前年比189%)に達している(全国信用保証協会連合会)。
今、“コロナ禍” に向き合う事業者に必要な兵站は、構造改革を後押しする投資資金、眼前の苦境を乗り越えるためのつなぎ融資、そして、再び立ち上がるまでの生活を保証するセーフネットである。これらの制度的な簡素化と拡充を急ぐとともに、政府には終息に向けてのグランドデザインの開示を求めたい。感染終息に向けての医療施策と各種支援策の全体像を時間軸に添って示していただくことで、我々は「今」の立ち位置を把握することができる。時短要請はいつまで続くのか、外出自粛はいつ解除されるのか、いつまで耐えればいいのか、未来が見えないことの不安の払しょくこそが最大の希望であり、勇気となる。

国・地方の債務残高は1,200兆円、GDPの2倍に達する。PB(基礎的財政収支)の赤字は2019年度の14.6兆円から2020年度は69.4兆円に膨らむ。財政はひっ迫している。しかし、アメリカ大統領選の異様さを思い出してほしい。豊かさから取り残され、社会から置き去りにされたと感じる人が一定の勢力を形成し、そこに陰謀論やフェイクを操る強権的な指導者が現れた時、民主主義はあっという間に危機に陥る。1930年代のドイツを想像できなかった人も目の前のアメリカを見て実感できたと思う。因小失大、“小によりて大を失う” ことがあってはならない。財政規律が「小」であるとは言わないが、自由社会の基盤が壊れたら元も子もない。感染終息、生活支援、経済再建は一体だ。筋の通った、思い切った政策に期待する。終息すれば必ず飛躍できる、この確信をもって “コロナ禍” に挑みたい。
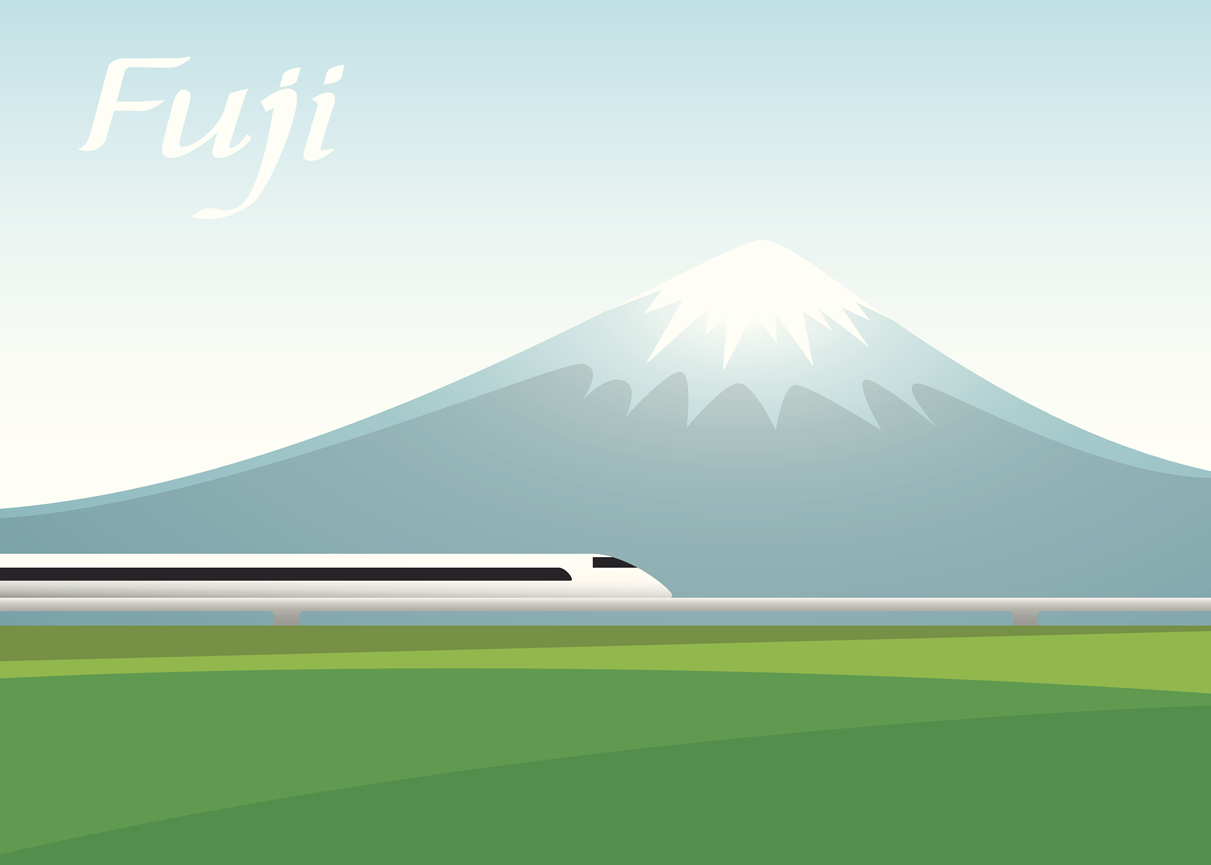
1月18日、JR西日本は新幹線による貨物輸送の事業化を目指すと発表した。JR東日本と連携し、金沢から首都圏向けに鮮魚などを運ぶ。また、JR九州とも連携、鹿児島-新大阪間における実証実験にも着手する。
新幹線を使った貨物輸送は、これまでも物産展のためのイベント運行として実施されたことがある。しかし、今回の実験は高速輸送を将来の成長分野と位置付けたうえでの取り組みであり、戦略的意味は異なる。
貨客混載の実証実験はJR北海道が先行、佐川急便をパートナーに在来線(宗谷本線)では一昨年の4月から、北海道新幹線(新函館-新青森)での実験も今月からスタートする。JR九州も昨年8月26日に佐川急便と提携、九州新幹線(博多-鹿児島中央)を活用した速達貨物需要の開拓を目指す。ただ、両社はいずれも自社の営業線内で完結しており、JR西日本の取り組みは会社間を跨ぐ高速物流ネットワークの構築に向けての第1歩である。
苦境に喘ぐ航空業界も貨物輸送の強化に舵をきる。日本航空の2020年4-9月期は売上収益が前年同期比74.0%減という大幅減収となったが、貨物郵便セグメントの収入は同18.4%増となった。コロナ禍による旅客便の運休、減便は同時に貨物スペースの容量も縮小させた。結果、航空貨物の運賃は高止まり状態にある。もちろん、パンデミックによる旅客売上の減少をカバーするにはまったく足りない。とは言え、航空各社は旅客機を貨物専用便に転用するなど貨物便の運航強化で経営の下支えをはかる。
ヒトの移動が大きく制限される状況にあって、モノの動きは拡大を続ける。社会のデジタル化とリモート化がこれを後押しするとともに、小口化と多頻度化への要求はこれまで以上に高まる。こうした環境変化を前提とすれば高速公共交通の強みであるスピードと定時性は十分にコストを吸収できるはずだ。航空機、新幹線といった高速輸送ネットワークと在来線、トラック網、ラストワンマイル自動走行を統合した物流MaaSの実現は、“地方” の可能性を引き出すプラットフォームとなるだろう。とりわけ、鉄道事業者の本格参入は「駅」のモビリティハブ化を促す。そして、そうなった時、駅は再び “町の中心” としての輝きを取り戻すはずだ。“中心の再生” は町そのものの求心力向上につながる。官民一体となった取り組みが望まれる。
