
改正新型インフルエンザ等対策特別措置法は「緊急事態宣言」の発出、解除を国の権限としたうえで、感染防止策の実行を都道府県に委ねた。結果、地方自治体の首長たちの存在感が高まる。
社会活動、経済活動における自粛や休業要請の対象業種、範囲を決定するのは都道府県の首長たちである。私権の制限と経済損失を伴う「要請」は知事の名で発せられ、同時に独自の補償や支援策が発表、実行される。
新型コロナウイルスは人口の過度な集中がもたらす社会的リスクの大きさとともに、国民生活における地方自治の役割と機能を国全体で見直す契機となったと言えよう。
19日、政府の地方制度調査会(地制調)は将来の人口減に対応した地方自治の在り方に関する答申案をまとめた。焦点となったのは「圏域構想」の扱いだ。これは「個々の市町村は行政のフルセット主義から脱却、一定規模を持った中枢都市とその周辺の市町村を一つの生活圏、経済圏を形成する新たなマネジメント単位とし、行政機能のコンパクト化とネットワーク化をはかる」ことを狙いとする。
ベースとなったのは総務省の有識者会議が提唱した「自治体戦略2040年構想」、国もこれを後押しする。しかし、全国知事会、全国市長会など地方6団体はこれを現行市区町村制度の解体を目指すものとして反発、「自治体間連携はテーマごとに進めるべき」との主張で一致する。地制調はそうした立場に配慮、広域連携の必要性を強調しつつも「圏域構想」に関する具体的な言及を見送った。
20日、全国知事会は「緊急事態宣言」の解除を見据え、政府への提言をとりまとめた。提言では、臨時交付金の積み増し、ワクチンの早期実用化、検査体制の確立、観光振興に向けての支援などを要望するとともに、宣言の解除に際しては「圏域の一体性への配慮」を求めた。
ウイルスにとって行政区分など何の意味もなさない。その押さえ込みには多くの人々にとっての日常的な移動範囲、つまり、「圏域」単位における対策が必要ということである。
そう、現実の生活に根差した地域の範囲を考える時、また、人口の絶対縮小が避けられない地方の将来を考える時、「圏域」という単位は極めてリアルであり、行政単位としてのメリットは小さくない。
もちろん、“町” は経済と行政における合理性だけで括られるべき “区画” ではない。歴史、文化、ことば、自然、そして、それを継承してきた人々の精神性が重要な構成要素である。とは言え、経済、教育、医療、交通、防災、治安、上下水道など社会インフラの維持は人々の暮らしの前提でもある。その意味において国と地方、地方における地域と地域の関係性についてあらためて問い直す必要があるだろう。“圏” の効率性と “町” の独自性をどう両立させるか。圏の重複、圏からの漏れによる非効率への最適解はあるか。新型コロナウイルスがもたらした “非日常” は未来に先手を打つための戦略をじっくり考える絶好の機会である。

世界規模での新型コロナウイルスの猛威は企業業績に重大な影響を与えつつある。12日、トヨタ自動車は2021年3月期の連結営業利益が前期比8割減になるとの見通しを発表、経済界に衝撃を与えた。しかし、そもそも当期業績への影響を見極めることが出来ない企業も少なくない。5月6日までに決算短信を発表した上場企業の6割が2021年3月期の見通しを「未定」とせざるを得なかった。
中小企業の状況は更に深刻だ。外出自粛と休業要請が長期化する中、宿泊、飲食、サービスなど個人消費関連事業者の資金繰りが限界に近づく。帝国データバンクによると5月13日までに確認された新型コロナウイルスの影響による倒産は破産74件、民事再生13件、事業停止が55件でそのほとんどが自己破産の準備に入っている、という。
しかし、これは氷山の一角であろう。問題は法的整理に至る前の廃業である。
2017年、経済産業省は今後10年間で245万人もの中小企業経営者が70歳を越えると推計、そのうえで、こうした企業の休廃業によりGDP22兆円、雇用650万人が失われると試算した。
今、政府系金融はもちろん民間金融機関も返済据え置き期間を2年から5年に延長、最長返済期間を15年~20年に設定するなど新型コロナウイルス対策の特別貸付枠を拡充、中小企業の資金繰りを支援する。
しかし、後継者の不在率が6割を越える中小企業において、果たして高齢の経営者が新たな長期負債を背負う決断をするであろうか。
多くの医療関係者が「新型コロナウイルスの収束には1~2年はかかるだろう」と言う。「否、完全な終息はない」とする専門家もいる。いずれにせよ、もはや新型コロナウイルス以前の世界に立ち返ることはないだろう。働き方、消費行動、教育、サプライチェーン、金融、医療、移動、物流、、、すべての領域でデジタル・トランスフォーメンションが加速する。
上記した経済産業省予測は「2025年頃まで」に起こり得る事態として推計されたものである。今、新型コロナウイルスがその時間を一挙に短縮しつつある。構造変化の負の側面をいかに最小化出来るか、未来に向けての投資をどこまで維持出来るか、新型コロナウイルスは私たちにこの2つの課題を突きつける。

29日、政府は5月6日を期限とする「緊急事態宣言」を延長する方針を固めた。延長期間は1ヵ月、対象は全都道府県、最終判断は5月1日に予定されている専門家会議を踏まえ、決定するという。
ご承知のとおり、日本の「緊急措置」は国民に危機の共有と要請への従順を求めるものであり、特措法にもとづく休業要請にも罰則規定がない。
このことが、収入や生活品質の低下を受け入れ、自身に自粛を課す大多数の人たちの一部に、要請や協力に応じない者、収入や日常に影響が出ない人に対する極端な不寛容を生じさせつつある。
「協力に応じない者は、取材され、顔が晒されることを後悔すればよい」、「県の職員に給付された10万円は県の財政として活用する」など、刺激的で強面な発言で “強い指導者” を装う軽い政治家が後を絶たない。幸い日本の民度はこうした質の悪い同調圧力に与しない健全性を維持している。
しかし、長期化する経済活動の自粛と感染への不安は、強力な社会統制を求めるポピュリズムの温床となりかねない。
問題の根本は自粛を要請し、収入の自主的な放棄を命じる側の責任が曖昧なことに尽きる。社会を同調圧力で覆い、善意の無償奉仕に頼るやり方はいかにも狡いし、ましてや財政事情の異なる自治体に対応を委ねるべきものではない。
公共の利益と国民の生命、自由、幸福追求の権利をどうバランスさせるか。これは統治の在り様の問題であり、つまり、国家のカタチそのものである。
26日、イスラエルで注目すべき司法判断があった。ネタニヤフ政権は治安機関が保有する対テロシステムを活用し、感染者の行動を過去2週間に遡って追跡、感染者と接触した人に自主隔離を要請する。これに対してイスラエル最高裁は「治安機関が一般市民の行動履歴を本人の同意なしに活用することは問題」としたうえで、政府に対して「個人情報保護に配慮した立法措置がない状態での監視の継続は認めない」と判決した。
対テロにおいて世界最強硬・最右翼のイスラエルにあって、それでも新型コロナ対策において明確な一線を引いた。危機にあって守られるべき価値は何か、私たちはここを問われている。

国境が閉ざされ、モノと人の流れが止まる中、20日、ニューヨーク商業取引所の原油価格(WTI先物)が史上はじめてマイナスとなった。5月物の終値は1バレルあたりマイナス37.63ドル、6月物も1999年以来の安値水準で推移する。影響は債権、株式、為替市場に波及、実体経済から金融システムに至るまで、世界のあらゆる経済活動において信用リスクが高まる。
20日、ロイター通信は米ニーマン・マーカスが週内に米破産法の適用を申請すると報じた。翌21日には豪ヴァージン・オーストラリア航空が任意管理手続きに入ったことを発表した。日本ではANAが1.3兆円、リクルートが4,000億円、三越伊勢丹が800億円など、大手企業が続々と融資枠の設定を銀行に求める。中小企業は更に深刻だ。中小企業庁によると緊急融資に関する相談件数は2月末までで7千件、3月に入ると急増、4月1日時点で30万件に達した。
インバウンドを牽引してきた中国人観光客は春節明けを境に反転、2月が▲87.9%、3月が▲98.5%となる。一方、国内の感染拡大も歯止めがかからず政府は3月13日には改正特措法を成立させる。
4月に入ると自動車など大手メーカー各社が相次いで生産調整の拡大、延長を発表、そして、4月7日の緊急事態宣言の発出となる。
中小企業の手元資金は平均で2.5ヵ月、まずは観光関連、続いて飲食、小売、サービス、自粛関連、そして、6月末にかけて商社、製造業で資金不足が本格化する。
当初4月24日の成立を目指していた、2兆3,176億円の中小企業・個人事業者への現金給付を含む補正予算は、「30万円の低所得者支援から一律10万円給付」への組み替えに伴って国会提出が27日にずれ込む。地方自治体向けの総額1兆円の臨時交付金についても「使途」を巡って、現場を背負う自治体との思いがすれ違う。政府は「協力金や支援金は認めるが、休業補償や損失補填は認めない」との立場を崩さない。予算成立後、制度の詳細を検討し、そのうえで説明会を開催、各自治体から実施計画を募り、6月中に事業内容と交付額を決定するという。
東京都は5月上旬の支給を目指して22日から休業協力金の受付を開始した。他の自治体も続く。金融機関も緊急融資体制を敷いた。もはや調整や手続きに時間をかけている猶予はない。今、危機にあってまさに国の本気度が問われている。
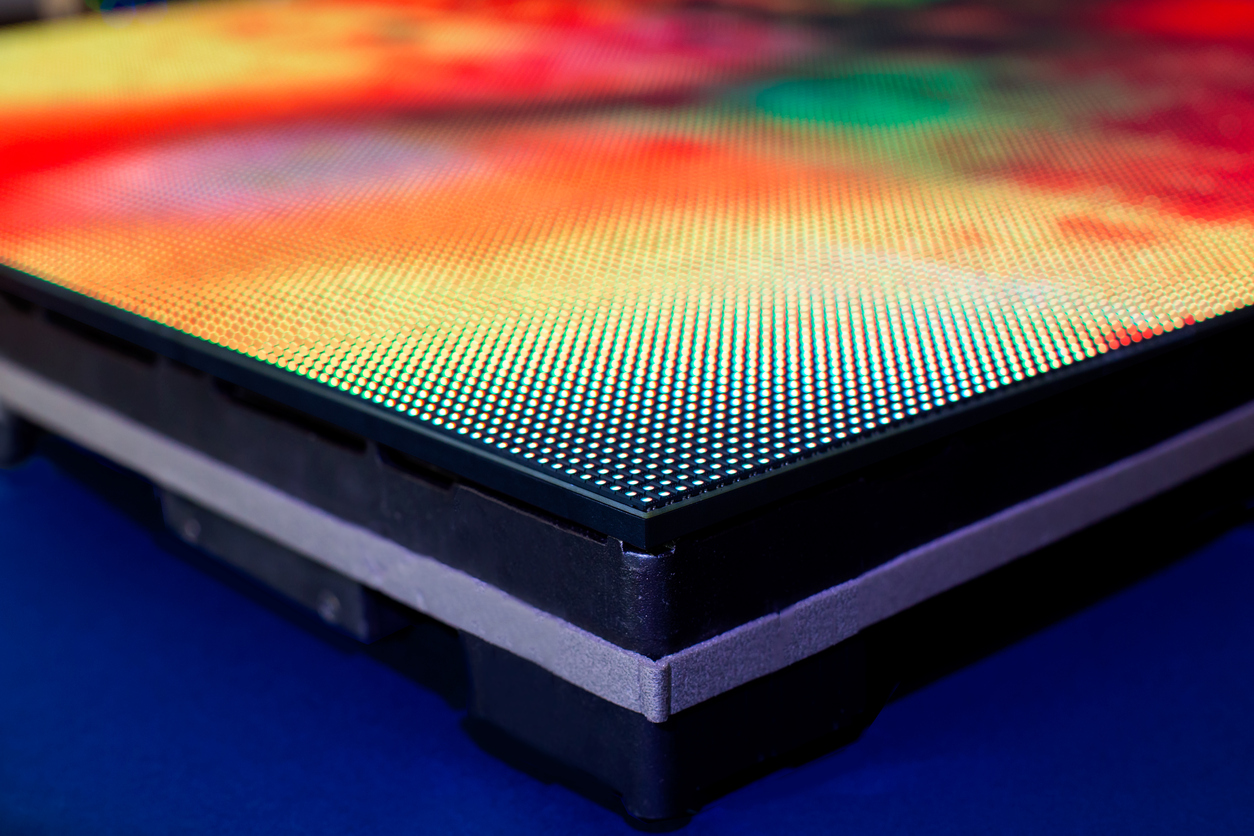
4月13日、経営再建中の液晶パネルメーカー、ジャパンディスプレイ(以下、JDI)は、会社資金の着服を事由に懲戒解雇され、昨秋、自殺した元経理部門社員が告白した「不適切な会計処理」に関する第三者委員会による調査結果を公表した。
確認された不正とは、期末在庫の架空計上、費用の先送りや資産化による利益操作などで東証1部上場後の2014年3月期から2019年上期まで続けられていた。過大計上された在庫は決算処理後、翌期に減損処理、最終損益に与えた影響は累計16億円とのことであるが、2016年3月期では102億円の不正利益が上乗せされていた。
JDIは粉飾決算が常態化した理由について、「不適切会計処理の多くは、不適切会計処理の通知を行った元従業員が主導した」ものであり、直接的な要因は「当該元従業員に経理部門の権限が集中し、上位者や経理部門内部での牽制が十分に機能しなかった」こと、「業績達成に向けた上位者からのプレッシャーが存在していた」ことにあると説明した。また、間接的な要因として、「当社の長年の業績不振、営業利益を最重視する社風、取締役会による監視監督機能や内部統制システム機能の不十分性等も背景にある」と総括した(4月13日付け、同社リリース資料より)。
しかしながら、長期にわたって繰り返された不正な会計処理が経理部門の一社員判断で行われていたとは考え難いし、そこまで追い込まれるほどの業績達成プレッシャーを当該社員が負っていたとの説明も違和感が残る。とは言え、例えその通りであったとしても、トップや経理担当役員がこれを見抜けなかったとすればそれはそれで経営者としての資質と能力に問題があったと言わざるを得ない。
JDIは2012年4月、経済産業省主導のもとでソニー、東芝、日立のディスプレイ部門が統合、官民ファンドのINCJ(旧産業革新機構)から2,000億円の出資を受けて誕生した国策会社である。しかし、上場後も5期連続で赤字を計上、昨年4-6月期には債務超過に転落、出資を検討していた中国・台湾の企業連合からも見放された。
そうした中での不正発覚である。数千億円の公的資金を投じてきたINCJ、最大顧客のアップル、新たな支援者となったいちごアセットマネジメント、個人株主、一般従業員、、、JDIを支えてきたステークホルダー全員が粉飾された経営数値を見せ続けられてきたということだ。
不正会計の公表とともに発表された2019年4~12月期の業績は売上387,775百万円(前年同期比83.3%)、最終利益は110,885百万円の赤字(前年同期は9,814百万円の赤字)となった。
13日の会見で菊岡社長は「ご心配をおかけし、深くお詫びする」と謝罪したとのことであるが、2千社を越える下請け会社のためにももはや後はない。今期の厳しい経営環境は誰も同じだ。これを乗り越え経営再建の道筋を “結果” をもって示すこと、それ以外に信頼回復と投じられた公的資金に応える道はない。
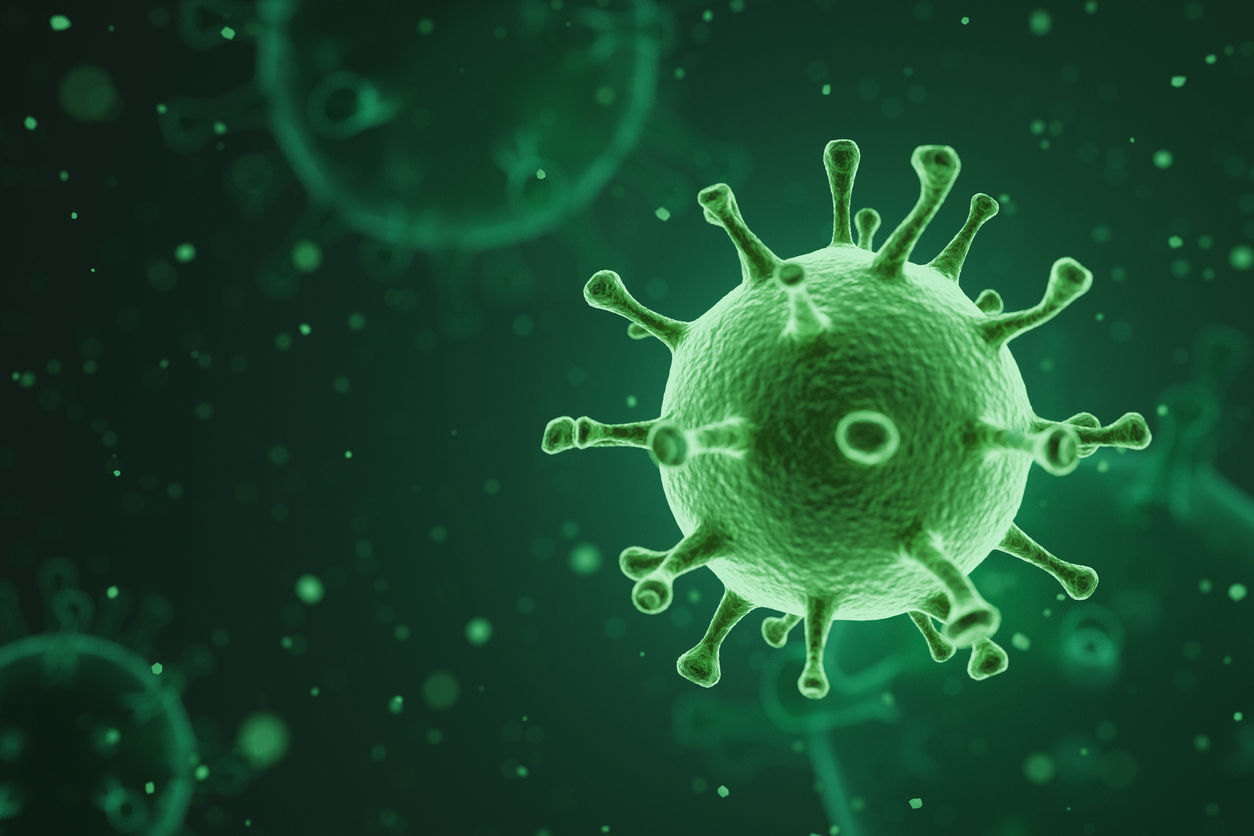
9日、IMFのゲオルギエワ専務理事は新型コロナウイルス感染拡大の影響を「リーマンショックを上回る大恐慌以来の落ち込み」との認識を表明したうえで、2020年は170ヵ国以上で一人当たりの所得がマイナスになると指摘した。また、各国による財政出動は「世界のGDPの9%に相当する8兆ドルに達する大規模なものであり、経済は徐々に再開してゆく」としながらも、2021年も「部分的な持ち直し」に止まるだろうとの見通しも示した。国、地域、都市間における移動制限と行動制限の影響は想定以上に長期化する可能性が高いということだ。
その前日、2か月半ぶりに武漢の封鎖が解かれた。東風汽車集団と合弁するホンダの現地稼働率は50%に回復、半導体大手「紫光集団」グループの長江メモリー・テクノロジーの生産量も封鎖前の水準を取り戻すなど、企業活動の再開が急ピッチだ。欧州でも規制解除に向けての動きが始まった。オーストリア、デンマーク、ノルウェーでは店舗や学校の再開準備が進む。ドイツ、イタリア、スペインでも復活祭明けを目途に一部の規制緩和が検討されているという。
一方、陰性者が再び陽性化するなど新型コロナウイルスには不明な点も多い。無症状の感染者の実態も掴めていない。性急な緩和は第2派、第3派の感染拡大を起こす可能性もあり社会的リスクは高い。
4月7日、政府は新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急経済対策を発表、翌8日には首都圏、関西圏、九州の7都道府県に「緊急事態宣言」を発出した。経済対策における財政支出は昨年12月に閣議決定された総合経済対策9.8兆円に緊急対応策の0.5兆円と新たな追加分29.2兆円を加えた総額39.5兆円、総事業費で108.2兆円となった。対応のスピード感、地方自治体との調整不足、経済支援の内容や制度設計への疑問は残る。しかしながら、収入の急減に見舞われた家計や事業者には一刻の猶予もない。まずは迅速な実行を、そして、不備があれば直ちに見直し、必要な追加措置を講じて欲しい。
強制力を伴わない行動規制への批判も強い。一部自治体では警察の投入が表明されたようだ。しかし、危機にあって試されているのはまさに民主主義の成熟度であり、問われているのは社会の民度そのものである。首長判断による警察の投入が、罰則を伴わない自粛の効果を疑問視する “大きな声” を背景にした単なるリーダーシップの演出であることを願う。
他国の制度や対策がすべて正しいわけではない。選択された方法で結果を出す、そのために何をすべきかだ。成果がついて来なければ科学的な検証を通じて軌道修正の是非を問えば良い。とにかく、着手すること、行動することが先決だ。とは言え、「レストランに行ってはいけないのですか」、「私のような国会議員は収入に影響がない」、「責任をとれば良いということではない」、トップが発したこれらの言葉に覚悟は萎える。残念だ。
