
新型コロナウイルス感染拡大を受け延期が決定した東京2020大会の新たな日程が発表された。アスリートや大会関係者はもちろん、楽しみにしていた多くの人が安堵したことと思う。しかし、この状況下にあって “延期” は正しい選択であったのか。
社会のムードを盛り上げるという意味でも、また、経済貢献という視点からみても大会開催の意義は大きい。東京都オリンピック・パラリンピック準備局の試算によると東京2020大会の需要創出額は1兆9,790億円、生産誘発額は5兆2,162億円に達する。新国立競技場建設など施設関連の整備費は既に支出済みとしても、大会運営費、参加者や来場者の消費支出、TVの買い替え需要などこれから新たに発生する消費額は大きい。
当然、“中止” になればこうした需要は失われる。宿泊、外食、旅行業界をはじめ影響は甚大だ。しかし、だからといって消費のすべてが失われるわけではないし、そもそも社会全体が恩恵を受けるわけではない。
帝国データバンクが実施したアンケート調査では、「東京2020大会が自社の業績にプラスの影響をもたらす」と回答した企業は全体の15%に止まる。56.1%の企業が「業績に影響はない」とし、「悪化する」と回答した企業も10.5%あった(「東京五輪に関する企業の意識調査」、2019年10月、有効票1万113社)。例えば、大会期間中にメディアセンターとなる東京ビッグサイトでは展示会200本以上が開催出来ない。出展社8.2万社、2.2兆円の売上が犠牲となる(日本展示会協会)。一方、大きな投資を実施したであろうインバウンド業界も大会期間中の需要増だけでの回収は見込んでいないはずだ。
経済効果とは言うまでもなく売上である。すなわち、誰かの支出、ということである。では誰が開催費用を負担するのか。東京2020大会ではスポンサー料やチケット販売などを収入源とする組織委員会が45%、東京都が44%、国が11%を負担する。つまり、全体の55%は税金だ。
“1年間の延期” には更に数千億円の追加費用が必要となる。今、首都の封鎖さえ取り沙汰される状況にあって、大会延命のために莫大な公的資金を投入すべきか。そもそも本当に開催できるかどうかも不透明であり、いつの時点で、世界の感染状況がどうなっていたら実施できるのか、その条件さえ示されていない。
リオデジャネイロ五輪では205の国・地域が参加した。現時点で新型コロナウイルスの感染は177の国・地域に拡大している。例え、日本や先進国の感染が終息したとしてもそれだけでは開催条件が整ったとは言えない。
医療機関への支援、治療薬の開発は緊急課題だ。生活者や事業者への経済支援も猶予出来ない。物資の確保、社会インフラの維持にもお金が必要だ。発表の場を失った演劇人、音楽家など文化の担い手たちも困窮している。まずは感染の終息と社会活動全体の正常化が優先されるべきであり、予算も人もここに集中投下すべきである。
スポンサー企業をはじめグローバル大企業にも期待したい。広告宣伝費、利益剰余金の一定額を拠出、大型の基金を組成し、治療薬の研究開発支援、中小企業への信用供与、新興国支援などに貢献いただきたい。最大のCSR効果が得られるはずだ。
今、最大の不安要因は将来が見通せないことに尽きる。未来に向けて進むためにも不確定要件を一つでも減らすことが肝要である。
大会関係者のお気持ちは察して余りある。しかし、判断は先延ばしにすればするほど損失が拡大する。損失とは経済的な意味だけではない。“オリンピック・パラリンピック” そのものの社会的価値を棄損させないためにも名誉ある撤退を選択すべきである。
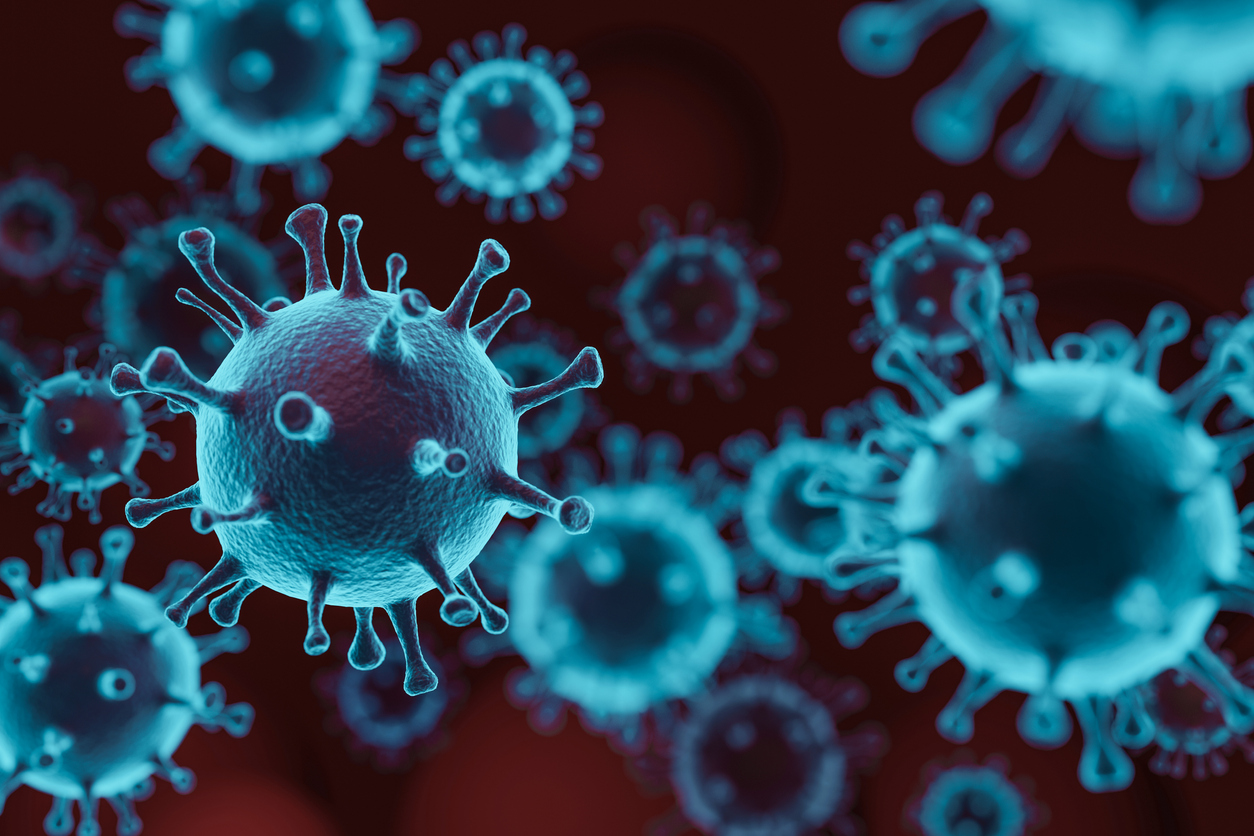
資源価格が急落している。国際原油相場は1バレル30ドル前後と年初の半分の水準まで落ち込んだ。暴落のきっかけは原油市場におけるサウジアラビアとロシアの価格競争であった。しかし、相場の先行き懸念は「実体経済における需要減」に変わった。言うまでもなく要因は新型コロナウイルスの感染拡大である。
世界に拡散した国境閉鎖、都市封鎖、外出制限の影響は、運輸、小売、サービス業にとどまらず、川上から川下まであらゆる産業活動に急ブレーキをかける。グローバル経済は完全に機能不全に陥りつつある。
政府は50兆円規模の緊急経済対策の準備に入った。現金給付、商品券、雇用助成、納税猶予、延滞税免除、政府系金融機関を通じての各種制度金融の拡充などが検討されている。民間金融機関も支援策を具体化する。三井住友銀行はサプライチェーンの維持に使途を絞った2,000億円規模の大手企業向けファンドと中堅中小企業を対象とする特別ファンドを組成する。三菱UFJ銀行も法人、個人事業主向けに新型コロナに対応した「災害等特別融資」を開始した。
生活支援、経営支援、消費喚起、需要創出、、、政策目的を明確にした施策の迅速な実行が望まれる。もちろん、優先課題は治療薬の開発である。国や研究機関のメンツや利益を越えた次元での国際的な開発、生産、配給体制の確立を急いでいただきたい。
26日、東京都の小池都知事は突如「首都の封鎖」に言及した。東京オリンピック・パラリンピック延期決定直後に表明した「今後3週間が重大局面」との危機認識は、習近平氏の来日延期の正式決定直後に発表された「中国全土からの入国規制強化」と同様に、例えそれが医学的必然性ゆえのタイミングであっても政治的都合、あるいは自身の “やってる感” の演出という違和感を残すものとなった。
つまり、行政への不信を助長させたという意味で、また、メッセージ効果を軽減させたという意味において時を逸したと言える。社会全体に漂う先行き不透明感を払拭するためにも情報の共有と政治的決定におけるプロセスの透明化は必須である。行政、情報への「信頼」があって、はじめて政策効果は最大化する。

新型コロナウイルス感染症が世界に広がる中、各国は一斉に金融緩和に舵を切った。16日、日銀もETFの買い入れ額を倍増すると発表、翌17日には1日あたりの過去最大1,800億円を投じた。しかし、株価下落の歯止めにはならず、返って、増大する含み損が明らかになることで政策効果への不信が募った。日銀は「リーマン・ショックほど経済は落ち込まない」との見解を表明したが、18日に発表された貿易統計の速報がそれを打ち消す。2月、中国からの輸入は前年比マイナス47%と激減した。文字通り中国からの部品、製品の仕入れが半減したということであり、国内の生産、販売への影響はこれから顕在化する。今、流行は欧州、米国、アジアへ拡散した。国境の封鎖や行動制限が世界に広がる中、世界規模で生産が滞り、市場が縮小しつつある。 “行き過ぎたグローバリズムへの反動” といった文脈を飛び越えて、世界は一挙に閉じつつある。
こうした中、12日、英国のボリス・ジョンソン首相が発表した対策が注目される。まず、「英国はイタリアより4週間遅れている、これから大規模な感染が予想される、多くの家庭で家族や親友が失われる」としたうえで、「英国は封じ込めではなく、ピークを遅らせ、ピークを50%に抑えることでリスクを最小化する。よって、当面、学校は閉鎖しない、イベント禁止は効果が小さいので行わない、渡航制限も追随しない」とした。そして、「新型ウイルスは感染しても多くの場合、軽症である。ゆえに高齢者や持病を持つ人など重症化しやすい弱者対策に集中する」との医療方針を示した。
こうした考え方は、人口の6割程度の人が感染し、免疫保持者となることで感染を収束させる集団免疫理論にもとづくという。ジョンソン氏は最高医療責任者と主任科学顧問を伴って、政策選択の根拠を示したうえで、「自粛行動は長期にわたって維持できない。ゆえに社会リスクを疫学的に最小化する」ことを国民にメッセージした。
集団免疫理論の採用には反対意見も根強い。「制御不能」となる事態を懸念する専門家も多く、「当面はしない」とした学校閉鎖は、「感染スピードが予想以上に速い」との理由でわずか6日後に撤回、方針転換を余儀なくされている。しかし、トップがその責任において選択した政策を、その根拠を明示したうえ国民に説明したことは、政策評価の基準を持つという意味において正しい。
ウイルスとの戦いはまだ第1コーナーを回ったばかりだ。各国の知見や経験を共有しつつ、最高レベルの専門家を交えたオープンな議論の中で、タイムラインを伴った総合的なウイルス対策を策定していただきたい。それこそが経済の不透明感と社会不安を払拭する最良のメッセージとなる。

2011年3月11日から9年が経過した。明日から「復興・創生期間」の最終年となる。「東日本大震災からの復興に向けた道のりと見通し」(令和2年3月版、復興庁)によると災害公営住宅、防災集団移転事業の計画達成率は99%、復興道路は76%の整備が完了、海岸対策も99%が着工、66%が完成済みだ。双葉町では帰還困難区域の避難指示が一部で先行解除、これにより全町が避難状態にある自治体は無くなった。14日にはJR東日本の常磐線が全線開通、特急 “ひたち” が仙台と都心を結ぶ。バス高速輸送システム(BRT)に転換した路線も含めると被災路線のすべてが復旧することになる。
宮城、岩手、福島3県の県内総生産は震災前の水準を取り戻した。津波によって被災した農地の92%が営農可能に(2019年3月)、被災水産加工施設も96%が再開した(2019年1月)。昨年9月には気仙沼の造船所4社が合併した新会社「みらい造船」の新工場が完成、漁船の造船・修理に特化した東北最大級の造船所がスタートした。月内には福島イノベーション・コースト構想にもとづくロボット実証実験施設「福島ロボットテストフィールド」も全面開所する。50㌶におよぶ敷地には500m級の無人航空機用の滑走路や水中・水上の実験施設が備わる。双葉町や大熊町でもエネルギーの地産地消プロジェクトが立ち上がる。“2011年時点” からの延長線上にはなかった新たな事業が被災地の可能性を拓く。
一方、依然として4.8万人が避難状態にある。避難の長期化に伴う災害関連死も3,757人に達した。復興はまだまだ道半ばであり、“被災” は終わっていない。切り裂かれた日常は置き去りにされたままである。その象徴がフクシマである。昨年末、政府は1、2号機の使用済核燃料の搬出開始を2023年度から5年遅らせることを決定した。工程表の改定はこれで5回目だ。中間貯蔵施設の整備も遅れている。放射性汚染土を収めたフレコンバッグ412万袋が仮置き状態のままである。日々増え続ける膨大な汚染水の問題もある。海洋放水が現実的であるとの流れに傾きつつあるものの漁業者の反対は根強い。
昨年10月、台風19号によって氾濫した河川が多数の汚染土入りフレコンバッグを押し流した。その一部は未だに個数も所在も不明のままである。汚染水の海洋放出問題ではトリチウム以外の放射性物質が基準値を越えて残留している可能性も指摘される。そうであればそもそもの前提が危うい。
先月、原子力規制委員会は、敦賀原発2号機の再稼働審査において日本原子力発電から提出された書類の中に “データの書き換え” や “削除” があったと発表、「考えられないことだ」としたうえで「審査の根幹が揺らぐ」と批判した。関西電力の金品不正授受の問題も記憶に新しい。原子力災害は目に見えない。ゆえに政府、行政、企業、技術、データに対する “信頼” がすべての根幹となる。まずは「アンダーコントロール」という嘘を捨て去り、事実を公開し、共有すること、福島の復興はここが原点でなければならない。

3月2日、米ゼロックスは米HPに対してTOBを宣言した。これに即座に反応したのはキヤノンだ。同社会長の御手洗氏は、ゼロックスによるTOBが成立した場合、HPとの提携関係を終了させる可能性がある、とメッセージした。キヤノンはHPのレーザープリンターに基幹部品を納めるサプライヤーだ。HPとの取引額は売上の14%に達する。2019年決算が減収減益となったキヤノンにとって重要顧客を失うことのインパクトは大きいだろう。しかし、それでもゼロックス=HP連合の誕生はキヤノンにとってより大きな脅威になるということだ。
ペーパーレス化が進展する事務機器市場は成熟市場である。しかし、ITソリューションのプラットフォームとなる複合機市場とアジア市場は商品開発力、サービス提案力、営業力による開拓余地が残る。
従来、世界の複合機市場は、ゼロックス+富士ゼロックス連合、リコー、キヤノン、コニカミノルタの4グループがそれぞれ15-18%のシェアで拮抗してきた。しかし、昨秋、ゼロックスと富士フィルムが資本提携を解消、これによりゼロックスはアジア市場の独自開拓が可能となる。
とは言え、販路やアフターサービス体制の構築は容易ではない。そこでHPである。HPは企業向けサーバーやプリンターがアジアで伸長、日本を除くアジア大洋平エリアの売上は全売上の11%を越える。複合機以外の製品ラインアップが厚いHPと絶対的なブランド力を有するゼロックスの組み合わせは既存プレーヤにとって侮れない。キヤノンとしては敵の傘下となるHPに「塩を送り続ける」ことは出来ないということだ。
ところで、そもそもの発端は富士フィルムHDによるゼロックス買収の頓挫であり、当然ながら富士ゼロックスも戦略の修正を迫られる。昨秋の会見では、「富士フィルムグループ内のシナジーを加速する。富士フィルムの画像処理技術と富士ゼロックスの言語処理技術を応用し医療分野を強化する」ことが強調された。とは言え、商標使用や販売エリアを規定したゼロックスとの契約が終了する2021年4月時点での主力事業はやはり複合機を軸としたドキュメント関連事業である。ゼロックスブランドに依存しない戦略が問われる。
この1年間で市場環境はどう変化するか。現時点でHP経営陣はゼロックスの提案を拒否、「ポイズンピル」の導入、150億ドル規模の自社株買いで対抗する。TOBの成否は不明であり、また、例え成立したとしてもPMIで失敗する可能性もある。あるいは成否に関わらず今回の動きが京セラや東芝テックなど第2グループを巻き込んでの業界再編に発展する可能性もある。いずれにせよ業界再編の鍵はHPの既存株主が握っている。TOB、そして、総会に向けて本格化するプロキシーファイトの行方を注視したい。

中国の湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルスは、今や世界にとって「対岸の火事」ではなくなった。既にアジアから欧州、中東、北米、南米、アフリカへ感染範囲は広がっており、WHO健康危機管理プログラムの責任者マイク・ライアン博士は「パンデミックに備えるべき段階にある」と警告する。「世界の生産額が全体で1兆1千億ドル減少する」(オックスフォード・エコノミクス)との予測も発表された。
日本経済への影響ももはや「サプライチェーンの機能不全」や「インバウンド消費の喪失」といった “限定的” なものではない。まさに感染の当事国として、その内側からじわじわと “停滞” が進行しつつある。
26日、首相は国内のスポーツや文化イベントの開催を2週間中止するよう要請した。ただし、判断は主催者に委ねられた。地方自治体、民間はそれぞれの責任において続々とイベントの中止を決定する。初動対応が後手に回った現状にあって、大規模集会の中止は一定の効果があるだろう。しかし、問題は、いつまで自粛を続けるのか、ということだ。政府専門家会議は「この1、2週間が瀬戸際」であると指摘するが、この期間での収束を本気で目指すのであれば果たしてこの “要請” だけで十分であろうか。とは言え、Jアラートを鳴らすことで「やってる感」を演出するようなパフォーマンスは勘弁願いたい。2週間であればリカバリーできる。事業者支援、事後対応を含むあらゆる施策を準備、総動員し、総合的で集中的な施策パッケージを実行して欲しい。
25日、IOCのディック・パウンド委員が東京五輪の「開催判断の期限は5月下旬」との見解を表明した。開催可否の判断時期としては適切であり、かつ、それがギリギリのタイミングであろう。これに対して日本側は「公式見解ではない」「予定通り開催する」と反発する。
しかし、“絶対安全” が絶対でなかったゆえの悲劇が未だに続く日本にあって、絶対開催などと叫べば叫ぶほど、そのリアリティは失われてゆく。
絶対でないことを前提にいかなる事態にも対応できるシナリオを用意することこそ主催国、主催都市の責任である。関係者には目の前の現実を正しく受け止め、世界と未来に誇れる判断をしていただきたく思う。
