
29日、賃貸アパート大手レオパレス21は一連の施工不良問題に関する外部調査委員会の最終報告書を公表した。
報告書は2018年に表面化した界壁(=屋根裏に設置すべき延焼防止用の仕切り壁)の未設置問題について、「建築基準法にもとづく建築確認申請を不正に取得した」と断じ、違法建築と施工不備への長年にわたる組織的関与を認定した。
そのうえで、創業者によるワンマン体制が、順法意識の欠落と品質軽視の企業風土を招いた原因であると結論づけ、経営体制の刷新とガバナンスの強化を求めた。
同社は独自の製販一体型のサブリース商法を開発、「敷金・礼金ゼロの部屋探し」を掲げて事業拡大をはかってきた。一方、事業資金の不正流用や一括借り上げ契約を巡るアパートオーナーとの訴訟などトラブルも後を絶たない。そうした中で発覚した今回の問題を受けて、レオパレス21は創業家出身の現社長を含む7人の取締役の退任を決定、社内取締役と社外取締役を同数とするなどガバナンスの強化と再発の防止に努めるとする。とは言え、引き続き現社長が相談役として経営に関与するとのことであり、創業家の影響力が温存される中、企業体質の改善がどこまで進むか疑問が残る。
ここへきて賃貸アパート大手の不祥事が相次ぐ。2018年12月、札幌で起きた消臭スプレー缶による爆発事故を契機に「アパマンショップ」一部店舗のクリーニング役務の不履行が発覚した。大東建託では、契約成立前に受領した申し込み金について、契約が不成立となっても返金してこなかった実態が表面化した。これに対して同社は、5月24日、NPO法人「消費者機構日本」からの是正要求を受け入れてすべての対象者に返金する旨、発表した。一方、強引な営業手法、苛酷なノルマに対する批判も根強い。
業界は急激な成長と競争の熾烈化、そして、需要の飽和を経験した。短期間に変動した経営環境に対する唯一の打開策としての“拡大至上主義”、言い換えれば経営トップの独善と組織全体の思考停止が問題の根源にある。
今後、内需は縮小に向かう。経営は過去の成功体験を捨て、オーナーとユーザー本位の新たなビジネスモデルを構築できるか。ここが企業としての存続条件となる。

20日、政府は2019年度が最終年度となる「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の第2期目の基本方針を示した。「民間との協同」、「人材の育成」、「ソサイエティ5.0」といったアプローチに加えて「関係人口の創出」が明記されたことを評価したい。
関係人口とは定住や観光ではなく、都市部の住民がボランティア等の能動的な活動を通じて地方と継続的な関係を構築することをいう。
2015年にスタートした第1期は、①地方に仕事をつくる、②地方へのひとの流れをつくる、③若者の結婚、出産、子育て支援、④時代に合った地域づくりと地域間連携、を戦略目標として掲げた(2018年改訂)。4月20日、内閣官房に設置された本部事務局は基本戦略の進捗に関する検証結果を発表したが、東京への一極集中が加速するなど政治的成果は決して満足できる水準にない。要因は地域によって異なるし、国の側や制度上の問題も指摘できよう。しかしながら、地方の側の企画力、戦略策定力、政策実行力の低さや首長の問題意識や資質によるバラツキが成果未達の背景にあることも否定できない。
もちろん、高い企画力と事業展開力に支えられた成功事例も多い。山梨県北杜市を拠点とするNPO法人「えがおつなげて」(代表:曽根原久司)はその好例。三菱地所グループのCSR部門をパートナーに限界集落地区の耕作放棄地を再生、収穫された米でオリジナル地酒を醸造し、販売する。やがてこの協業は県を巻き込んでの森林資源の活性化に発展、三菱地所ホームは山梨県産間伐材を2×4住宅の構造材として標準採用するに至る。また、同法人は全国で農村起業塾を運営、既に1千人規模の農村起業家を育成し、都市と田舎、田舎と田舎を結ぶ地域共生型ネットワークの構築を目指す。
地方再生のためには①地方と都市を分断させないこと、②行政区分の枠を越えて地方の資源や事業を構想すること、③未活用資源×無形資産(アイデア、経験、情熱)による新たな資本形成、が不可欠であり、第2期総合戦略ではこれまで以上に地方、地域、民間の独自性に軸足を置いた制度設計に期待したい。個々の地域、個々の事業に応じた権限や財源の移譲、そして、既存のルールや前例にとらわれない柔軟な事業環境づくりを望む。

トランプ政権による対中貿易制裁のもう一段の強化に加え、米国の中東政策における強硬姿勢が世界の不確実性を高める。
米国は4月に発動したイラン産原油の全面輸入禁止措置に対する報復を警戒、空母や爆撃機をペルシャ湾に派遣するなど軍事的な圧力を強めてきた。そうした中、航行中のサウジアラビア、UAE、ノルウェーの船舶がイランに支援された武装勢力から攻撃を受けたと報じられた。また、14日にはイエメンのシーア派武装組織“フーシ”がサウジアラビアの石油施設を攻撃、こちらもイランの関与が取り沙汰される。
イランは米国の制裁強化に対してホルムズ海峡の封鎖を示唆していた。しかし、海上封鎖のリスクはイランも承知しており、今回の攻撃はそれゆえの限定的な威嚇行動とみることもできる。もちろん、イラン政府は武装組織への関与を否定する。とは言え、偶発的な軍事衝突も含めペルシャ湾の緊張は高まる。15日、米国は隣国イラクの米国大使館、領事館員の一部に出国を指示したという。
ホルムズ海峡の緊迫化はすなわち世界の原油供給体制にとってのリスクである。米国は振り上げた拳の落とし所を見出すためにも、イラン核合意にとどまり続ける欧州からの支持をとりつけたいところであるが、英仏独との隔たりは大きい。
一方、トランプ政権は6月のラマダン明けのタイミングで新たな中東和平案を発表するという。2017年12月にエルサレムを首都と認定し、昨年5月に大使館を移転、今年3月にはゴラン高原をイスラエル領と認定するなど、中東和平に関する国際協調体制を一方的に崩してきたトランプ氏が「究極のディール」と予告する和平提案の中身が注目される。
国際社会が“唯一の解決策”としてきた「2国家共存の原則は維持される」との見方もあるが、2期目を目指すトランプ氏にとってユダヤ票の取り込みも念頭にあるだろう。そもそも「2国家には拘らない」と繰り返し表明してきたトランプ氏だけに中東情勢は予断を許さない。

8日、米国は中国製品に課している10%の追加関税を10日から25%に引き上げると正式に発表した。
その3日前、難航する交渉に業を煮やしたトランプ氏はツイッターで制裁関税の引き上げに言及、これを受けて米中合意に向けての市場の楽観は一挙に後退、株安が世界に連鎖した。それでも9日から再開される閣僚級協議が最後のチャンスとなるが、米国の強硬姿勢を受けて中国側ももう一段の報復を示唆するなど予断を許さない。
米中貿易戦争が実質的な覇権争いであることは言うまでもない。この3月、米国では各界の有識者で構成される「危機委員会(Committee on the Present Dangers)」が20年ぶりに設置された。これは国家的危機に対する政策提言機関であり、過去にトルーマン、レーガン時代にそれぞれソ連を対象に、ジョージ・W・ブッシュ政権時に対テロを対象に計3回設置されたことがある。中国に対する米国の危機感は単なる「貿易におけるwin-winの関係」では解消できない次元までに拡大しつつあるということだ。
米中は南米、中東でも対立、アジアでは台湾が“駆け引き”のカードとして浮上する。22日からジュネーブで開催されるWTO総会への招待状が6日時点で台湾に届いていない。背景には独立志向を鮮明にする民進党の蔡英文政権に対する中国側の圧力があると言われる。そうした中、台湾は中国による情報統制、世論誘導を警戒する。総統選挙を来年1月に控え、蔡政権は中国IT企業に対する規制強化に動く。一方、総統選挙では対中融和路線を掲げる国民党の優勢が伝えられる。そして、国民党の候補者には習指導部と関係が深い鴻海精密工業の郭台銘氏が有力だ。郭氏はトランプ氏ともつながる。2大国の駆け引きが続く中、台湾はどちらへ向かうのか。台湾は重大な歴史的岐路にある。
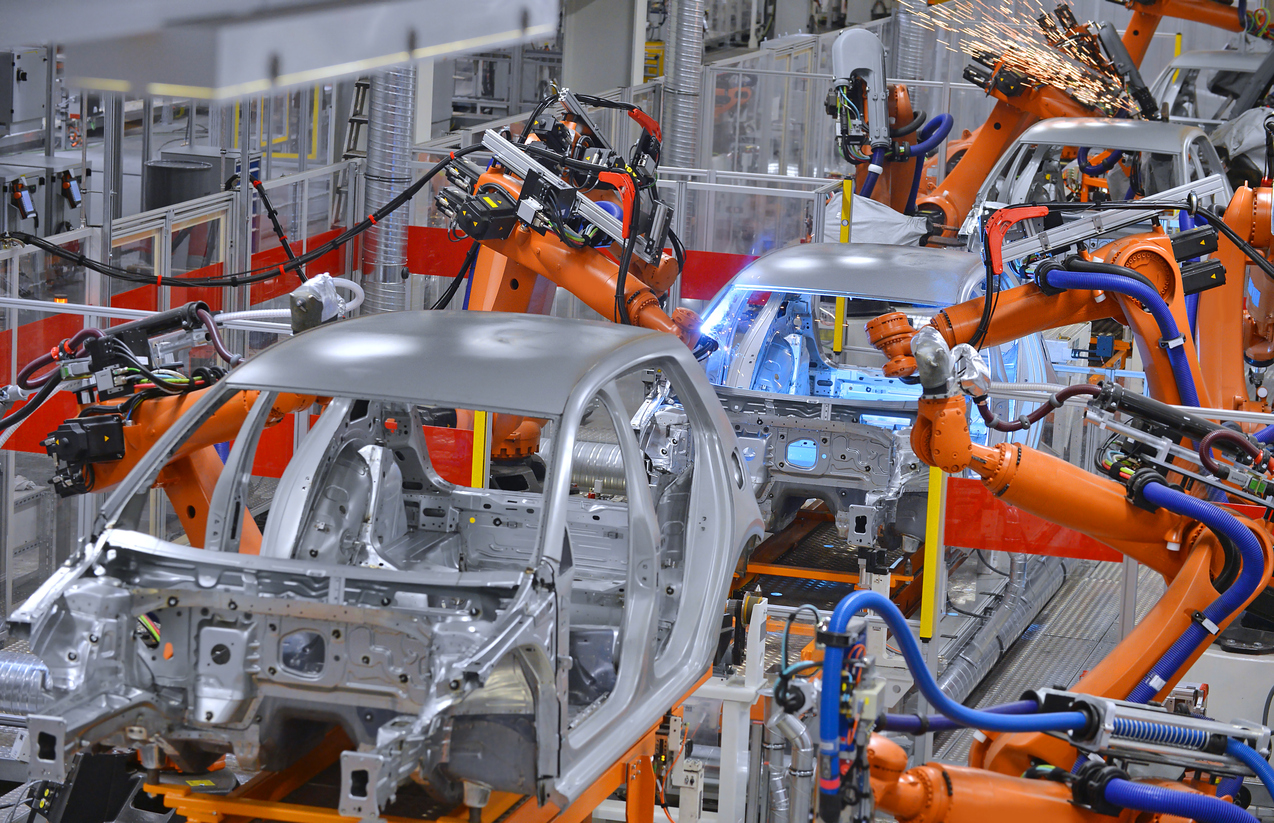
ルノーが日産に再び経営統合を打診した。昨年11月、両社をバランスさせてきた“カリスマ”の突然の不在を受け、両社の主導権争いが表面化する。4月12日、ルノー、日産、三菱自は、3社のトップで構成される新たな会議体を設置、グループの最高意志決定機関とすると発表した。ルノーのスナール会長も合議体によるグループ運営への移行を支持、経営統合問題は棚上げされた、はずだった。
しかし、実際には上記会議の前後にルノー側からあらためて経営統合が提案されていた。日産経営陣はこれを拒否、あくまでも独立企業としての提携関係を維持したい考えだ。
一方、ルノーにとって統合は言わば悲願である。2018年9月、ルノーはカルロス・ゴーン元会長を通じて経営統合を日産に提示した。今年1月にも大株主である仏政府から日本政府に統合の意向が打診されている。そして、4月というタイミングでの再提案は定時株主総会を前にした日産への牽制であることは言うまでもない。
確かに現時点における2社のポジションは業績、技術力ともに日産が上である。しかし、だからこそルノーは破綻した日産の“将来”に投資したとも言える。議決権ベース43.4%の資本の意味は軽くない。
国交省、経産省は2030年度までに2020年度目標から3割の燃費改善を義務付けるとともに次世代低燃費車の普及目標を引き上げる方針だ。環境規制、次世代自動車では欧州、中国勢が先行する。2018年3月期の研究開発投資は日産が4,958億円、ルノーが3,800億円、2社を合わせてもトヨタに及ばない。フォルクスワーゲングループの研究開発投資は1兆5千億円を越える。
今、未来の競争優位の確立に向けて、自動車市場は新たな提携、再編の波の中にある。主役はCASEを牽引する大手ITや新興ベンチャーだ。そうした中にあって“仏、日本、それぞれの国益”などと言う議論に両社の利はない。競争に取り残された時、次の買収者はもはや自動車メーカーではないだろう。日産は未来を生き抜くための統合シナリオの構築をこそ急ぐべきだ。資本の問題は統合戦略を主導し、結果を残してゆく中でいずれ解消できる。

15日、OECDは「対日経済審査報告書」で日銀のETF(指数連動型上場投資信託)の買入について「市場規律を損ないつつある」との懸念を表明した。これに対して、日銀の黒田総裁は「2%の物価安定目標を達成するための施策の一環」であるとしたうえで、「目標達成に向けて大きな役割を果たしている」と語った。
翌16日、衆議院財務金融委員会にて同様の懸念について問われた黒田氏は「さまざまな意見があることは承知しているが、“株価安定”の実現に向けての必要な措置である」と回答、直後、「株価ではなく物価」と言い直す一幕があった。
日銀が「物価安定目標」を“消費者物価の前年比+2%”と定めたのは2013年1月である。しかし、2019年4月にあって目標の達成は依然として遠い。もはや異次元緩和への期待が色褪せつつある中で問われた“副作用”に対する反論として、目に見えるポジティブな成果としての“株価”が黒田氏の頭を過ぎったのだろうか。もちろん、発言は直ちに修正されたが、本来の目標達成が見えて来ない現状にあって、市場の歪みと副作用に対する懸念が黒田氏の中でも大きくなりつつあるのかもしれない。
2018年、日銀によるETFの買入れは年間6兆5040億円に達した。同年12月における保有残高は23兆5497億円、これは東証一部上場会社の時価総額の約4%を占める。年明け以降も残高は増え続け、この3月末には28兆円を越えたとみられる。日銀のETF買入は黒田氏が繰り返し説明したとおり物価の安定が目的である。市場介入による株価操作が目的ではないし、ましてや純投資ではない。したがって、目標が達成されるまで売却はできない。ゆえに企業価値が適切に反映されるべき株価に歪みが生じる。
問題はこれだけでない。万が一、相場が急落し、時価が取得価格を割り込んだ場合、日銀は大きな含み損を抱えることになる。つまり、円の信任そのものが毀損する可能性がある。このリスクを回避するには残高を減らす必要がある。しかし、売却は相場の下落を誘発する恐れがある。まさに退くに退けない。
とは言え、日銀は実効性の高い出口戦略を準備し、一定の条件下で政策を転じる意志を表明すべき時期に来ているのではないか。それは金融政策における“手持ちのカード”を増やすという意味においても有効であるはずだ。
