
10月14日、中国税関総署が1-9月期の貿易総額が前年同期比+3.4%、うち輸出が前年比+4.3%、輸入が+2.2%となった、と発表した。今年上半期(1-6月期)の貿易総額の伸び率が+6.1%、輸出+6.9%、輸入+5.2%であったことを鑑みると、夏場以降の低迷が顕著である。とりわけ、輸入の落ち込みが大きく、9月単月では+0.3%へ鈍化している。
内需の低迷、デフレ圧力の強まりは国家統計局発表の物価指数でも確認できる。9月の消費者物価指数(CPI)は前年比+0.4%、食品が+3.3%となる一方、非食品価格は▲0.2%とマイナスに転じている。生産者物価指数(PPI)も減速、9月は▲2.8%とこの半年で最大の下落率となった。
こうした状況の中、当局も従来型の産業振興投資から個人消費の喚起に本腰を入れる。年内に発行が予定されている2兆元規模の特別国債のうち1兆元を家計に振り向ける。住宅購入時の頭金規制の緩和、ローン金利の引き下げなど住宅購入支援のもう一段の強化や子育て関連消費への補助なども対象とする。とは言え、単発的な景気刺激策では効果は限定的だ。地方と都市の格差を是正し、安定した内需の拡大をはかるためには雇用、税制、社会保障、地方政府の債務問題など、産業政策や社会基盤そのものの構造改革が急務である。
この7月、若者の失業率は17%に達した。そんな若者世代が支持するのは「消費降級」と呼ばれる消費スタイルだ。高級ブランドや新車の販売が失速する中、彼らが支持するのは中古品市場である。国慶節の大型連休、今年はコロナ禍前を上回る延べ20億3千万人が移動した。期間中の出入国者も1300万人を越えた。とは言え、国内旅行に限ってみると自家用車を使った近隣への節約型旅行が主流であり、国内線の航空運賃は軒並み下落した。中国の成長が1%鈍化すると近隣諸国のGDPも0.21%下がるとされる(世界銀行)。アジアへの不況の連鎖を防ぐとともに、政治的安定という意味においても実効性の高い構造改革に期待したい。

10月8日、厚生労働省は毎月勤労統計調査の8月速報を発表した。就業者の現金給与総額は名目ベースで296,588円(前年同月比+3.0%)、うち一般労働者は377,861円(同+2.7%)、パートタイム労働者が110,033円(同+3.9%)となった。前者の所定内賃金、後者の時間当り給与もそれぞれ2.9%、4.8%と前年同月を上回った。しかしながら、物価変動の影響を除いた実質賃金は同▲0.6%と3カ月ぶりにマイナスに転じた。
実質賃金のマイナスは8月の消費者物価が前年同月比+3.0%と賃金の伸びを上回ったことによる。とは言え、「27カ月ぶりのプラスとなった6月そして7月も夏季賞与による押上効果によるものであって、そもそもの “基調” は変わっていない」との見方も出来る。ただ、マイナス幅は縮小しており、それだけに “夏” への期待もあった。
そこに水を差したのが、南海トラフ地震臨時情報の発出とお盆休みのタイミングで警戒が呼びかけられた台風である。結果、8月の消費支出は実質ベースで1.9%のマイナスとなった。とりわけ、自動車販売、国内パック旅行の不振による「交通・通信」と「教養娯楽」が低迷、前者が▲17.1%、後者が▲6.9%と個人消費を押し下げた。一方、極端な伸びを示したのが記録的な猛暑に伴うエアコン需要(+22.7%)とコメ(+34.5%)、カップ麺(+18.1%)、トイレットペーパー(+17.2)といった災害備蓄関連の消費である(総務省「家計調査」より)。
8月の統計データは、日本中が巨大地震に身構え、猛暑に喘ぎ、物価高に苦しんだことを伺わせる。今、中東情勢の緊迫化に伴い原油市場の先行きが懸念される。米国は雇用情勢が好転、大幅利下げの観測が遠のく。為替の修正の遅れは輸入物価の高止りを意味する。アベノミクス、官製春闘、新しい資本主義を経て、未だ “デフレ脱却宣言” には至っていない。こうした中、牛丼大手3社が「並盛300円台」を謳った期間限定の値下げキャンペーンを一斉にスタートさせた。再び “安い日本” に閉じてゆくか、“金利のある世界” での成長に賭けるか、私たちは大きな岐路にある。

※ DIC川村記念美術館(筆者撮影)
9月30日、DICは “DIC川村記念美術館” の休館開始時期を2025年1月下旬から3月下旬に延期すると発表した。DICは2023年12月期決算における最終赤字を受け、外部による経営諮問機関「価値共創委員会」を設置、美術館運営の在り方について議論を重ねた。結果、「資本効率という面において有効活用されていない」として、8月27日、年明け1月下旬から休館すると発表した。しかし、これ以降、来館者が急増したため、今回の延期となった。
美術館がターゲットとなった背景には昨年12月28日時点で6.9%の大株主となった香港の投資ファンド「オアシス・マネジメント」からのプレッシャーがあっただろうことは想像に難くない。取締役会は、社会的価値と経済価値の両面から美術館運営の位置づけを再考するとし、「運営中止の選択肢も排除しない」としつつ、「ダウンサイジング&リロケーション」を具体的なオプションとして検討、年内に今後の運営方針を決定する(8月27日付、同社リリースより)。
所蔵754点、うちDIC所有は384点、簿価112億円、市場価値10億ドル超、と言われるコレクションは2代にわたる創業家社長によるもの。インキを祖業とし、色彩に魅了された創業家のアイデンティティそのものと言える。美術館に入って最初の展示室に飾られたレンブラントをはじめ、ルノワール、モネ、ブラックなど近代を代表する作家の作品は一級品揃いであり、ステラ、トゥオンブリー、ポロックといった現代美術の充実ぶりは傑出している。とりわけロスコの作品7点が常設展示されている “ロスコ・ルーム” は圧巻だ。因みに筆者のお気に入りはポロックの “緑、黒、黄褐色のコンポジション”(1951)である。
日本屈指の企業ミュージアムである同館の閉鎖、収蔵品の散逸は、美術界はもちろん、DICのコーポレートブランディングにとっても損失となろう。「進化した “Color&Comfort” の価値提供を通じて、株主利益を包摂する社会的利益を追求する」(DIC Vision2030より)との言葉どおり、経営の立て直しを急ぐとともに文化資産を保有するものとしての社会的責任の履行を願う。最後に、19世紀フランスの詩人・劇作家ゴーティエ(Gautier)の一節を。「美しいものは生活に必須ではない。しかし、花のない世界を望む人がいるだろうか?(モーパン嬢、1835)、「これが何の役に立つのか、ですって?美しくあるために役立つのです。それで十分ではないでしょうか」(アルベルトゥス、1831)。
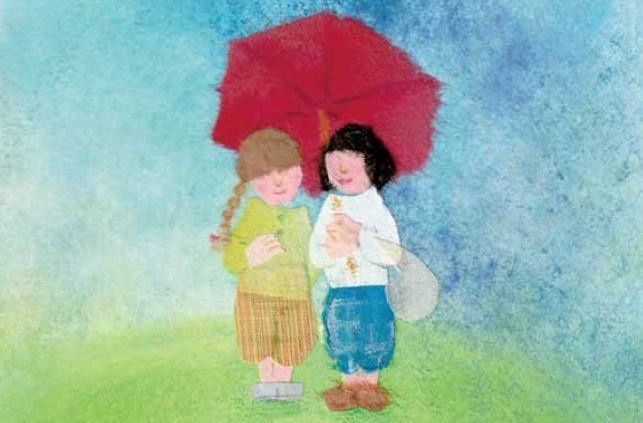
※ ももせいづみ 画(絵本「赤い日傘」より)
9月24日、国が定めた被爆援護対象地域外で被爆した “被爆体験者” の一部を被爆者と認めた長崎地裁の判決に対して、長崎県と長崎市が控訴した。地裁判決は、原告44人のうち被爆者援護法の指定地域外ではあるが「黒い雨」を浴びたことが確認出来た15人を被爆者と認定、残る29人の訴えは退けた。
判決を受け、国は残された “被爆体験者” に対して被爆者と同等の医療助成を行う新たな制度を創設すると表明、その一方で過去の判例と整合しないことを理由に控訴方針を固めた。当初、県と市は判決を受け入れる旨の意向を表明していたが、結果的に国の決定に従った。これに対して原告側も「被爆者を差別すること自体が不合理である」と控訴する方針である。
原告が発した「差別」という言葉の意味は重い。戦後20年を経てなお差別と後遺症に苦しむ広島を記録した「この世界の片隅で」(山代巴編、1965年7月発行、岩波書店)に描かれた被爆の実相は、79年後の今に至るまで続いているということだ。原告に残された時間は多くない。退陣まであとわずかとは言え、広島を選挙地盤とする現首相の政治決断に期待したい。
被爆者と共有できる時間が限られる中、被爆の記憶を未来へつなぐための様々な活動が市民レベルで始まっている。広島出身の筆者の妻も仲間とともに、7歳で被爆した水江顕子氏と姉の高梨曠子氏の被爆体験記「ヒロシマ」の英語版を2020年に出版、2023年には母校ノートルダム清心中・高等学校と広島女学院高等学校の生徒による英語による朗読動画を作成した。また、同書の多言語化に取り組むとともに、銅版画作家のももせいづみ氏に参画いただき、この夏、絵本「赤い日傘」を出版した。ももせ氏とは新たなプロジェクトもスタートしている。是非一度、朗読動画(日、英)をご覧いただき、それぞれのお立場にて記憶の継承にご協力いただければ幸いです。絵本も是非どうぞ。
※Team Akikoホームページ:https://team-akiko.jp/
※絵本のお申込みはこちら:https://team-akiko.jp/red_parasol_form/

9月18日、海上保安庁は2022年4月に知床半島で沈没し、乗客乗員20人が死亡し、6人が行方不明となった観光船「KAZU1(カズワン)」の運航会社「知床遊覧船」の社長を業務上過失致死容疑で逮捕した。事故から2年半、当時のニュース映像が伝えた同氏の不誠実さは記憶に新しい。本件では総額15億円の損害賠償を求める集団訴訟も起こされているが、杜撰な安全管理体制に対する刑事責任がようやく追及されることになる。
その前日、国土交通省はJR九州高速船(株)に対して、「輸送の安全の確保に関する命令」と「安全統括管理者及び運航管理者の解任命令」を発出した。処分は同社が博多・釜山間で運航する旅客船「クイーンビートル」が浸水の事実を隠蔽、当局への報告義務を怠ったうえ運航を継続していたことに対するもので、責任者である取締役2名を解任せよとの命令は全国初である。
「クイーンビートル」で浸水が確認されたのは2023年2月、当局や親会社に報告することなく数日間運航を継続、以後、ドック入渠と運航再開を繰り返し、同年6月、最初の「安全確保命令」が出される。しかし、2024年に入ってからも浸水隠しは止まず今回の措置となった。隠蔽はJR九州から派遣された前社長の指示のもと行われたとの報道もあるが、浸水警報が鳴らないようセンサーの位置を変えるなど、その手口は悪質だ。船舶の管理や航行の安全に対するルールは「KAZU1」事故の悲劇を受けて厳格化されたが、JR九州子会社の事案は海の安全を願う関係者へのまさに裏切り行為である。
さて、ここまで書いたところでJR東日本の東北新幹線で走行中の列車の連結器がはずれ、車両が分離した状態で停止したとのニュースが入ってきた。東北新幹線では年初に架線が破損するトラブルがあった。装置は交換の目安となる30年を越えていたという。JR貨物では検査不正だ。これを受けて全貨物列車の運行が止まった。東京メトロでも輪軸検査で不正が発覚した。自動車、船舶エンジン、自動二輪、建機、そして、鉄道。ジャパン・クオリティを代表する企業で相次ぐ不正行為に “停滞への怖れ” に委縮してゆく組織と個人の姿を見るようだ。まずは企業人一人ひとりが自身の判断と行動の基準を問い直すことことから始めていただきたい。再生とイノベーションの起点はそこにある。

9月10日、フォルクスワーゲン(VW)は「2029年まで雇用を保証する」とした雇用保障協定の破棄を労働組合に通知、コスト削減策の一環として「検討中」とされてきたドイツ国内工場の閉鎖が現実の問題として従業員に突き付けられた。国内工場の閉鎖は1937年の設立以来はじめてであり、国内約30万人の従業員に与えたインパクトは大きい。ドイツ最大の産業別労働組合「IGメタル」は直ちに反対を表明した。
VWの国内リストラの背景にはエネルギーコストの高止まりといったドイツ固有の問題もある。しかし、販売不振の要因は言うまでもなくEV市場の失速だ。VWはディーゼル車の排ガス不正問題を契機に一挙にEV投資に舵をきった。しかし、中国の新興専業メーカーの急速な台頭と低価格化、そして、中国、欧州、米国における成長鈍化が事業計画を狂わせた。“見込み違い” はVWだけではない。「2030年までに完全EV化」を宣言していたメルセデス・ベンツやボルボは達成時期の再考を表明、GMやフォードもEV投資の縮小を発表、テスラも当期業績見込みを下方修正した。
EV市場の低迷が顕在化する中、ハイブリッド(HEV)需要が伸長、トヨタの “全方位” 戦略への評価が高まる。とは言え、そもそもエンジン車(ICE)からEVへの “転換” が思惑どおり進まないのは欧米日など巨大なICE産業と成熟した市場を擁する地域の話であって、自動車産業の育成と本格的な市場形成が “これから” の国では様相が異なる。東南アジアは今がそのタイミングであり、地理的にも有利な中国EVメーカーにとって輸出と直接投資の恰好のターゲットだ。結果、これまで “日本車の牙城” と言われてきた東南アジアにおける日本勢のプレゼンスはEV比率の拡大とともに低下が避けられない情勢だ。
国際エネルギー機関(IEA)はEVの成長要因として①気候変動対策、②石油依存に対する経済安全保障上のリスク軽減、③イノベーション、の3つを挙げる。しかしながら、①脱炭素は大事だけどトータルコストはまだまだ割高だ。②電池材料に対する経済安全保障上のリスクも無視出来ない。とすれば③だ。EVはITやAIとの親和性が高く、したがって、自動運転のプラットフォームにも乗せやすい。既存のICE市場の “置き換え” に止まらない需要創造領域が新たな競争フィールドでもある。「やっぱりトヨタは正しかった」などと安堵している場合ではない。今こそ未来のその先に向けて、事業戦略の問い直しとイノベーション投資を加速すべきである。
※関連記事「EU、中国製EVの輸入関税引上げへ。中国発価格競争の波及を警戒」今週の"ひらめき"視点 2024.6.9 – 6.13
