
5月、米国はイラン核合意から一方的に離脱、対イラン経済制裁を再開、11月には原油を対象とする第2弾の制裁を発動する。こうした中、24日、EUのモゲリーニ外交安全保障上級代表は「イランとの貿易を継続、促進するための特別目的事業体(SPV)を設立する」と発表した。イランとの貿易を合法的に行なえる体制をEU内に整えることで、核合意に関する国際的な枠組みを維持する。イランのザリフ外相も同席した会見で、同氏は「SPVは欧州の企業だけでなく他の国々にも開かれるだろう」と発言、米国と一線を画すEUの姿勢を明確にした。
翌25日、トランプ氏は国連総会で「グローバリズムの拒絶」、「米国第一主義の推進」、「貿易不均衡の是正」を明言するとともに、“歴代大統領より多くの成果を成し遂げた”と自賛した。会場からは失笑も漏れたが、トランプ氏の自国至上主義と国際社会を軽視する姿勢への懸念と反発が目立った。とりわけ、中国、ロシア、中東、欧州との対立が顕在化、仏のマクロン大統領は「我々の価値の普遍性を攻撃するために、国家主権を利用すべきではない。そのような国家主義者に主権の理念を委ねることはない。我々は強者の掟を信じない」と言い切った。
トランプ氏はその前日、対中制裁関税の第3弾を発動、中国からの輸入品2000億ドル分に10%の追加関税を課した。中国も600億ドル分の米国製品を対象に直ちに報復関税でこれに応じた。米中貿易戦争は中国をして「首にナイフを突きつけられている」(王受文商務次官)と言わしめる段階まで来た。今度は日本が矢面に立つ。体裁はTAGである。しかし、交渉の土台とすべきは主権国家としての普遍的な価値そのものである。

19日、苫東厚真1号機が復旧、これを受けて北海道電力は節電要請を解除、繁華街ススキノにもネオンが戻った。一方、被災された方々にとって「日常」は未だ遠い。あらためて心よりお見舞いを申し上げます。
6日未明、胆振地方を震源とするM6.7の地震が発生、その18分後、日本では「起こりえない」とされてきた全域停電(=ブラックアウト)が起こった。事故の詳細は今後明らかになるだろうが、ブラックアウトに至る経緯は以下のとおり。
①苫東厚真2、4号機が地震直後に停止、全道の4割の電源が喪失
②停止した電源に見合う需要を切り離す「負荷遮断」を実施、道北、道南が停電
③本州からの「北本連携線」がフル稼動、需給バランスは一時的に回復
④苫東厚真1号機の損傷が悪化、自動停止。需給バランスが一気に崩れ電力供給網の
すべてが連鎖的に停止、全道停電へ
専門家はブラックアウトの要因として、地震発生時刻が深夜未明であったこと、北海道電力の主力電源が石炭火力発電であること、苫東厚真発電所が道内の電力需要の半分を担っていたこと、を指摘する。
石炭火力は石油や天然ガス火力と比べて負荷追従運転能力が低い。すなわち、3時8分という需要がもっとも小さい時間帯に、苫東厚真という集中電源の供給が停止、直後の需要変化に出力調整が追いつかず電力供給網全体が連鎖的に破綻したということだ。
北海道電力は出力57万キロワットの天然ガス火力発電所を石狩湾に建設中だった。北本連携線の増強工事も進んでいた。いずれも2019年の稼動を予定していただけにタイミング的には不幸だった。しかし、想定外のブラックアウトはこれからの社会インフラのあり方に一石を投じた。
発電所は高出力ほどコスト効率が高い。しかし、それゆえの脆弱性を内包しているわけであり、そのリスクは大きい。何もかもが右肩上がりの時代はもはや終わっている。とすれば、強大であること、一元的であることを理想とする“昭和”のシステムから、小規模、分散、柔軟をキーワードとするネットワーク型の社会システムを構想すべきではないか。
ブラックアウトからの復旧期間中、全道の14%の電力を下支えしたのは日本製紙、新日鉄住金、王子ホールディングスなど民間企業が保有する自家発電設備だった。地場のコンビニチェーン「セイコーマート」は全道停電下にあっても95%の店で営業を継続、非常用電源装置で照明やレジの電力を確保した。ここにヒントがある。

12日、西日本新聞は「給与所得、過大に上昇。政府の手法変更が影響、補正調整されず」との見出しで記事を書いた。骨子は“政府が発表する所得関連データの作成手法が変更された。これによって賃金の対前年比伸び率が大きすぎる状態が続いている。補正調整もなされていない。景気判断の甘さにつながる。専門家からも批判されている”というもの。
厚生労働省の毎月勤労統計調査は現金給与の支給実態を月次ベースで集計した基礎統計であり、経済の実勢を知るための重要指標の一つである。従来、調査対象事業所のうち30人以上の事業者は2~3年ごとに「総入替え」されてきたが、2020年から毎年1月に1/3ずつ入れ替える方式への変更を決定、今年はその経過措置として1/2が入れ替わった(4月20日付けの厚生労働省資料より)。
厚生労働省は“入れ替わっていない半分のサンプル”のみで集計した対前年比データを「参考値」として公表している。確かに「参考値」は変更後の正規統計を傾向的に下回る。6月の確報では正規統計の対前年比賃金上昇率+3.3%に対して参考値は+1.3%に止まる。2ポイントの差は小さくない。
この要因はどこにあるのか。まず入替え前の2017年12月と2018年1月のデータを比較してみる。多くの日本企業において1月は定期昇給の時期ではない。ところが、鉱業・砕石業の所定内賃金は前月比3%増、卸売・小売業も前月比プラスである。前述した6月のデータでは業種別の偏りが更に顕著となる。鉱業・砕石業は給与総額で前年比28%アップ、所定外(残業)が+21.6%、特別に支払われた給与(賞与)に至っては同+93.5%と倍増である。卸売・小売業、運輸・郵便業の賞与も2割以上アップ、総額も1割程度増えている。もちろん、人手不足等による待遇改善は想定できる。しかし、伸び率は過大で、すなわち業種ごとの標本の代表性が問われているということだ。
発表資料を見る限り厚生労働省が採用した新方式は納得できる。厚生労働省はサンプル入替えの影響を産業全体で“プラス0.8ポイント”と分析しているが、あわせてサブ母集団ごとの“歪み”の度合いも開示いただきたく思う。必要であれば補正も検討すべきだろう。
公文書の改ざん、隠蔽、そして、日本銀行による統計データの修正が問題になったばかりである。一方で計算方法の変更に伴うGDPの上方修正は“成長”にすり替えられる。余計な憶測を呼ばないためにも産業別、事業所別標本に関する統計検定の結果などもう一段の情報開示をお願いしたい。

経団連の中西宏明会長が新卒採用の解禁時期に関する経団連指針を「廃止すべき」との考えを表明し、波紋を呼んでいる。
指針は会員企業向けに提示する言わば内輪の紳士協定であり、外資や非会員はルールに拘束されない。また、身内のルール破りが横行していることは周知の事実であり、今年は面接解禁日の6月1日時点で7割もの学生が内定を得ているとのデータもある。実態に向き合えば廃止は必然とも言える。
一方、“協定”としての実効性が希薄化しているとは言え、指針は学生や大学にとって実質的な“タイムライン”として機能してきた。それだけに、ルールがまったく無くなることへの不安も大きく、“青田買いの熾烈化”や“学業への影響”を懸念する声もあがる。頻繁な変更や会員の不正すら防げないルールの在り方に対する不満もあるのだろう。唐突な廃止提案への大学側の反発は小さくない。
とは言え、形骸化したルールの廃止は、学業への影響や学生の負担をむしろ軽減するのではないか。確かに、就職を希望する学生全員が一定期間学業を離れ、それが更に長期化するのであれば問題は大きい。しかし、そもそも同一のタイミングで一斉にスタートするがゆえに、企業は“序列化”され、上から下へ向けての内定獲得競争となる。“抜け駆け”が発生する原因もここにある。
経団連指針は、「経団連企業が序列の最上位にある」ことへの暗黙の了解があってはじめて機能する。つまり、指針の形骸化はそれがもはや“内側”から崩れつつあることの証左であり、言い換えれば今回の会長声明は経団連自身がようやくその事実を受け止めたということかもしれない。
採用プロセスの事前開示とその誠実な履行を前提とするならば企業は自由に選考時期や選考方法を学生に問えばよい。学生の側もまた自分自身の価値観で企業を選択すればよい。従来型ポテンシャル採用を選んでもいいし、欧米型のスキル採用に挑戦しても良いだろう。企業も学生も、相手を選ぶ時期や基準が一律である必要などどこにもない。
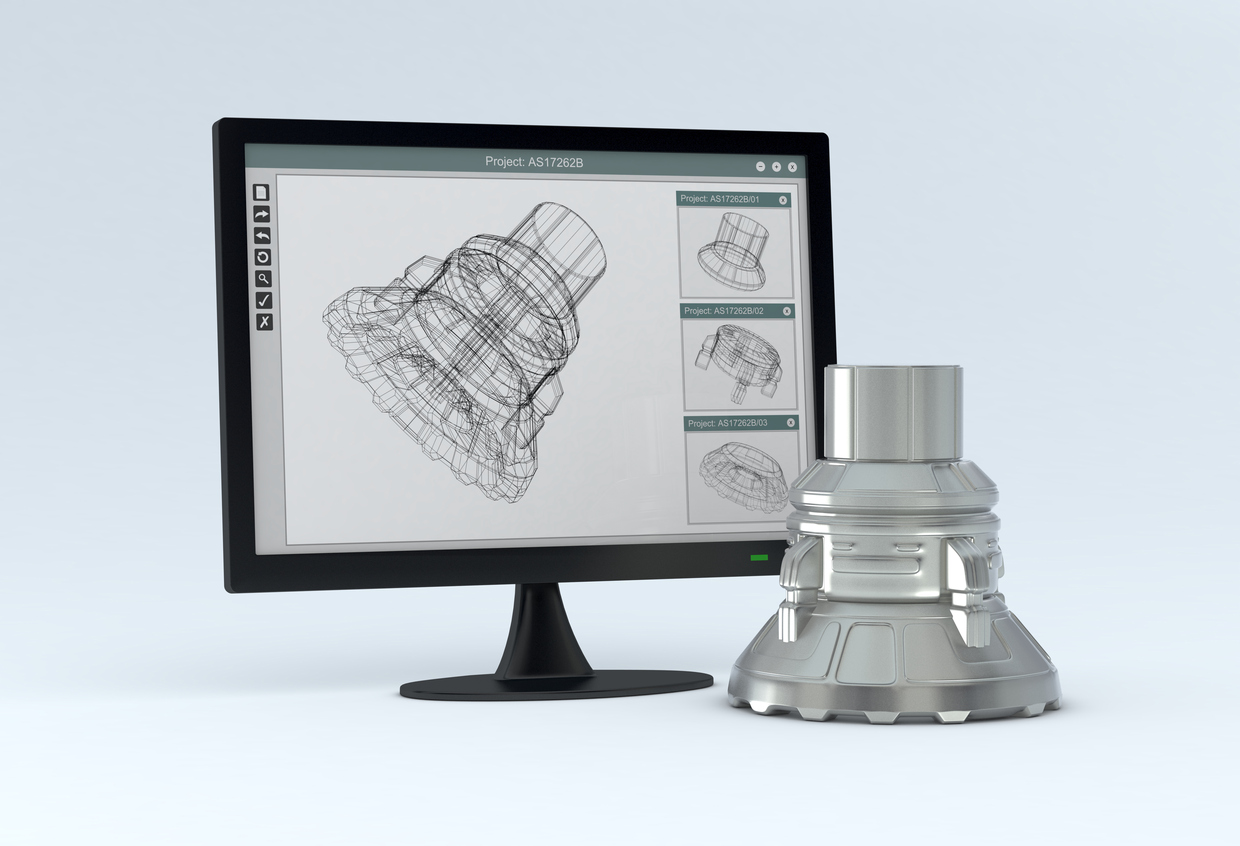
文部科学省は来年度予算の概算要求で人口知能(AI)など先端技術教育を担う実務家教員の育成やデータサイエンスなどの実務型講座の拡充に予算を計上するという。先端技術の急速な進歩はその応用領域を格段に拡大させる。しかしながら、現場サイドの技術者不足と知識レベルのギャップは大きく、したがって、“実践”にウェイトを置いた教育の強化に異論はない。
とは言え、技術教育が短期的な成果に極端に動機づけられることの弊害も大きい。国立大学法人における博士課程の入学者数はこの5年間で4割も減少した。施設設備の予算は過去最低の水準であり、科学研究費助成事業の1課題あたりの平均分配額も減額が続く。全米科学財団が発表した2016年の世界論文数ランキングでは日本は6位に後退、米国を抜いてトップとなった中国の22.6%に止まる。
日本のものづくり産業を支えてきたのは広範な基礎研究の厚みである。確かに欧米と比べて研究成果のマネタイズは得手ではない。しかし、産業の国際競争力を長期的に維持するためには実践と基礎研究をトレードオフの関係にすべきではない。
一方、日本の産業を支えてきたもう一つの厚み、中小企業もまた危機に直面している。2025年には経営者の7割が70歳を越え、その半数に後継者がいない。このまま放置されるとGDPの22兆円、650万人の雇用が失われる。経産省は2019年度予算に中小企業対策1352億円を計上するという。しかし、大企業のサプライチェーンに組み込まれたままのビジネスモデルを未来へ延長するための施策であっては衰退の引き伸ばしに過ぎない。外部資本の導入、非親族の経営参画、そして、世界に通用する技術と知材の獲得が中小企業の活性化を促す。
研究者と中小企業の多様性、自立、クオリティの維持、強化は、すなわち日本産業の厚みを維持、強化することと同義である。基礎研究投資と中小企業対策はまさに成長戦略の中核施策として一体的に議論されて然るべきであり、省庁と短期的な効率を越えた次元での予算枠と制度設計に期待したい。

2016年のクーデター未遂に関与したとされる米国人牧師の拘束を巡る問題でトルコと米国の対立が収まらない。トルコ通貨リラの対ドル下落率は5割近くに達しており、もう一段の混乱とその長期化による金融危機の連鎖が懸念される。
2017年のトルコの経常赤字はGDPの5.6%、外資金融機関のトルコ向け債権の総額は2233億ドル(約24兆5千億円)に達する。主要債権国はスペイン、フランス、イタリア、ドイツ。NATOの同盟国であるトルコと米国の対立はEUにとって座視できない状況となりつつある。
リラの急落に拍車がかかったのは、10日、トランプ氏がトルコに対して鉄鋼・アルミ関税の倍増を発表したことによる。しかし、これが問題の本質ではない。そもそもトルコの輸出総額における米国向け鉄鋼・アルミのシェアは1%にも満たない。通貨下落の最大の要因は、エルドアン大統領の強権的な政治手法を警戒した欧米企業がトルコ向けの直接投資を控えたこと、そして、ばらまき政策に象徴される財政規律の緩みにある。
こうした中、エルドアン氏は近隣の湾岸諸国から断交されているカタールと通貨スワップ協定を締結、更には中国からの金融支援も取り付けた。憲法を改正し、批判を封じ込め、言論を統制することで権力基盤を強化したエルドアン氏、米国に対して一歩も引かない構えである。
13日、独メルケル首相は「ドイツはトルコ経済の繁栄を望んでいる」としたうえで「中央銀行の独立性を確保するためにあらゆる手段を尽くさなければならない」と発言、“金利は悪”と公言するエルドアン政権に阿り、一向に引き締め策を講じないトルコ中央銀行に苦言を呈した。
さて、一方のトランプ氏も同様だ。中間選挙を直前に控えた今、トルコへの譲歩などあり得ないだろう。そして、彼もまた「低金利が好ましい」とFRBに圧力をかける。独善的な権力者の対立が世界の軋みを拡大させる。同時に独立性を失った中央銀行が“市場”を歪め、積み上がった金融リスクが先送られる。これはこの2国だけの問題ではない。
