
米トランプ政権による鉄鋼アルミ関税問題の波紋が広がる。EUは報復の一環として22日、米国製自動二輪やウイスキーに25%の追加関税を実行した。米はこれに対抗すべくEU製自動車に25%の追加関税を課すと表明、一方、カナダは米国に阻まれた安価な鉄鋼製品の自国市場への流入を防ぐため追加関税の検討に入った。
26日、トランプ政権は11月4日を期日にイランからの原油輸入を停止するよう世界に要求、イラン中央銀行と取引した金融機関には基軸通貨ドルの決済システムから除外する、と威嚇する。
中国は今年の3月から上海市場で取引を開始した人民元建ての原油取引を活用、米国の要請を拒否する構えだ。EUは域内企業が第3国による経済制裁に従うことを禁じた「ブロッキング規則」の発動準備に入った。インドもルピーによるイラン原油の取引実績がある。オバマ政権による経済制裁下にあってもイランとの取引を維持した日本もこれを受け入れる利はない。
対米外国投資委員会(CFIUS)の権限強化も懸念材料である。CFTUSは安全保障上の理由があれば大統領に投資中止を勧告する権限を有する。新法案では買収・合併のみならず合弁やマイノリティ出資も審査対象に加えるという。中国を念頭においた措置と言われるが、対象は中国企業に限定されない。鉄鋼アルミ課税と同様に「適用除外はない」だろう。
報復の連鎖は米国内の軋みも拡大させる。米自動車工業会はEU車への追加関税は米消費者にとって年間5兆円の負担となると発表した。知財侵害に対抗した中国ハイテク製品の輸入制限は部材や生産を中国に依存する米国の自動車、医療機器、EMS企業のバリューチェーンを毀損する。
こうした中、売上の2割弱を欧州に依存する米ハーレー・ダビッドソンが「生産拠点を米国外へ移転せざるを得ない」ことを表明した。アメリカを象徴する同社の方針にトランプ氏は「耐えろ。さもないと高額の税金を課す」と恫喝した。常軌を逸したトランプ氏の振る舞いに市場経済は行き場を見失いつつある。

15日、参院本会議は「改正海岸漂着物処理推進法」を可決した。洗顔料やボディソープといった化粧品や歯磨き粉には「マイクロビーズ」というプラスチック粒子が使用されており、こうした製品の廃棄物が河川や海に流れ込むことによる生態系への影響が懸念されてきた。本法案はこうした微細なプラスチックの使用制限について企業側に努力義務を課すものである。罰則規定は盛り込まれず、数値目標も書き込まれていない。業界サイドの取り組みによって使用制限が既に強化されている現状を鑑みると、法的対応における“周回遅れ”は否めない。
貿易問題における米国との対立がクローズアップされたG7首脳会議であったが、プラスチックごみによる海洋汚染の問題も討議された。6月9日には世界各国に対策を促す「シャルルボワ・ブループリント」を採択、更に、英、仏、独、伊、加とEUは自国でのプラスチック規制の強化と海洋生態系の保護を謳った「海洋プラスチック憲章」をまとめ、これに署名した。日本は米国とともに憲章への署名を見送っている。
欧州の対応は早い。英国はこの1月、数値目標を書き込んだプラスチックごみの削減目標を発表、EUも5月には使い捨てプラスチックの制限を規定した新たな制度を議会に提案した。トランプ政権による環境問題からの後退が顕著である米国ではあるが、マイクロビーズについては2015年12月、オバマ大統領が「マイクロビーズ除去海域法」に署名、昨年7月に製造が禁止された。P&G、ユニリーバ、マクドナルドといったグローバル企業もプラスチックごみの削減に対してそれぞれ対策を講じつつある。
国連によると世界のプラスチックごみの発生量は3億トン、うち800万トンが海に流出しているという。日本人の1人当りプラスチック消費量は米国についで2番目である。北太平洋には総量1億トン超、米テキサス州の2倍以上の面積を持つごみの島が浮遊している。国土の12倍の領海を持つ海洋国家で、かつ、プラスチック消費大国である日本の責任は軽くない。

13日、新協定「TPP11」の承認案が参議院本会議で可決された。衆議院は既に関連法案も通過させており、与党は今国会での成立を目指す。
TPP11にはタイが正式に参加を表明、韓国、台湾、英国、コロンビアも関心を示す。また、これまで参加に消極的であったインドネシアも米国の保護主義化を念頭に「アジアに保護主義を持ち込ませないために協調すべき」(ユスフ・カラ副大統領)と語り、参加への意欲を示した。
一方、マレーシアのマハティール首相はTPP11の枠組みを評価したうえで、「貧しい国と富める国との自由貿易はどうあるべきか」との問題を提起、再交渉の必要性に言及した。米国市場への参入を取引材料に自国市場の開放を余儀なくされた新興国にとって、米国の離脱は「公正さ」を取り戻すチャンスと映る。とは言え、知的財産権の保護や電子商取引のルールを含むハイレベルな多国間協定が11ヶ国で合意されたことの意味は大きい。ルールは硬直化すべきではない。しかし、RCEPなど他の広域経済圏構想を主導するためにも発効を急ぐべきだ。
自由貿易を率いてきたG7の協調体制が米国によって揺らぐ中、中ロが主導するSCO(上海協力機構)12ヶ国首脳会議が青島で開催された。習近平氏は「世界の統治を完全なものにするための重要な勢力」と宣言、“非西側陣営”の結束をアピールする。しかし、SCOが“公正な自由貿易”の模範足りえないことは言わずもがなである。
12日、今や世界の不確定要因となった米国とアジアの不安定要因である北朝鮮との“歴史的な首脳会談”が実現した。先は見えない。それゆえにルールにもとづく国際協調の基盤を構築しておくことの意味は大きい。米中ロから独立したTPP11の戦略的価値はこれまで以上に高まった。

明日からG7首脳会議が開催される。しかし、通商問題における対立は深刻だ。サミットの前哨戦となった財務省・中央銀行総裁会議では、米国に対する「懸念と失望」が議長声明として発表されるなど、日欧加と米との亀裂は決定的となった。
とりわけ、欧州勢は鉄鋼・アルミ関税に関する協議で米側が「輸出数量規制」を持ち出したことに強く反発した。WTOルールを無視した米国の一方的な交渉姿勢に会議は紛糾、結果、米国の孤立が際立つこととなった。
一方、トランプ氏は「貿易戦争には負けない」との従来どおりの強硬姿勢を崩さない。「G7への不参加、つまり、ボイコットもあり得る」との声すらあがる。
パレスチナ、イラン、パリ協定、、、国際協調の前提が米国の単独行動によって揺らぐ中、G7内の決定的な亀裂は世界の混迷要因にしかならない。北朝鮮、シリア問題、対中国、対ロシアという文脈においても同様である。米国の孤立は世界にとって大きなコストとなる。シャルルボワ・サミット(カナダ)で試されるのはまさにG6側の「覚悟」である。
かつて、中国は“朝貢貿易”で繁栄を極めた。中国に貢ぎ、中国から恩寵を受け取るという特殊な貿易形態が成立した。貿易のコストは相手国側が負担した。それゆえ、中国は海運つまり海の覇権に関心を持つ必要がなかった。しかし、これが後の衰退につながる。
今、目先の貿易利益の拡大に奔走するトランプ氏、果たしてそれは将来の何と“トレードオフ”されるのか。米国もまた大きな岐路にある。

政府は外国人就労者の拡大に向けた新制度を「骨太方針2018」に盛り込む。外国人の一般労働者を受け入れる大義を「新興国の技能取得支援」から「国内の労働力不足の補完」へ実質的に転換する。
新制度の名称は“特定技能(仮称)”、5年間の技能実習を終えた就労者が業界団体等による技能試験に合格すれば更に最大5年間の就労が認められる。
具体的な数値目標も発表された。介護が毎年1万人、農業は2023年に現在の3.8倍10万3千人、建設は2025年で現在の5.5倍30万人以上、造船は2025年までに2万1千人、宿泊は現在の2.2倍2万1千人、留学生の就労についても規制緩和や手続きの簡素化が検討されているという。
しかし、4月12日付けの本稿でも指摘したとおり新制度の本質は依然“技能実習”のままである。家族の帯同は認められず、また、永住取得条件は直ちに満たされない。
OECDの外国人移住者統計によると2015年の日本への外国人流入者(ビザを保有し90日以上在留)は前年比5万5千人増の39万人、日本はOECD加盟35カ国中、独、米、英に次ぐ第4位の「流入大国」であり、実際、国内で就労する外国人は128万人に達する(2017年10月、厚生労働省)。
もはや、労働移民を認めないという“建前”の維持は困難であり、建前と現実とのギャップは無用な社会的トラブルの誘引となりかねない。在留外国人を社会に組み入れるためのソフト、ハード両面における体系的な準備を急ぐべきであり、一方で「日本の未来」に関するビジョンはきちんと描けているのか、もう一度問い直す必要がある。
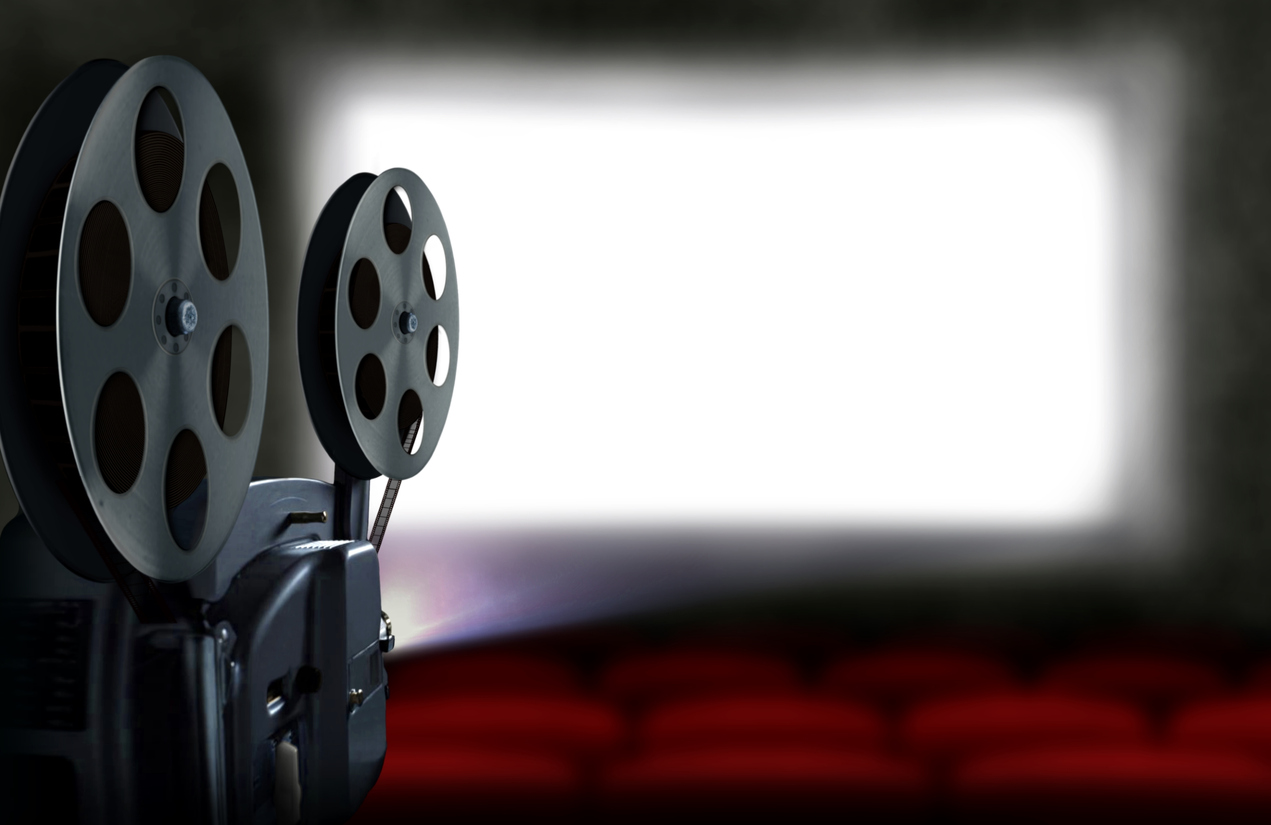
第71回カンヌ国際映画祭で是枝裕和監督の「万引き家族」がコンペティション部門の最高賞“パルム・ドール”を受賞した。日本映画の最高賞受賞は1997年の「うなぎ」(今村昌平監督)以来21年ぶりの快挙である。
また、コンペティション部門では「寝ても覚めても」(濱口竜介監督)、“監督週間”ではアニメ「未来のミライ」(細田守監督)、短篇部門でも「どちらを選んだのかわからないが、どちらかを選んだことははっきりしている」(佐藤雅彦、河村元気、c-project)が上映されるなど、日本映画のクオリティの高さはカンヌでも多いに注目を集めたという。
国内では、政府が進めるクールジャパン戦略にとって追い風、といった声もあがった。しかし、その推進役である官民ファンド「海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構)」の苦戦ぶりはこの4月に発表された会計検査院の報告からも明らかである。
同機構は2013年11月に資本金375億円でスタート、2017年末時点では630億円へ増資、政府負担は300億円から586億円へ拡大した。この間に投資した案件は17件、2017年3月末時点における支援案件の損益は▲4,459百万円、累積利益剰余金は▲5,850百万円である。80言語以上に対応したローカライゼーションの基幹インフラ、オール日本コンテンツの有料衛星放送チャンネル、、、大型投資案件の多くが厳しい状況にある。
日本のカルチャーを世界に発信することに異論はない。とは言え、より重要なことは普遍的なコンテンツの創造であって、戦略的プラットフォーム、基幹インフラ、拠点ネットワーク、、、といったいかにも“霞ヶ関”好みのビジネスモデルから世界に通用する作品が生まれるわけではない。まず取り組むべきは創作、創造、製作現場に対する長期的な支援体制の構築である。
尚、私事ではあるが21年前に“パルム・ドール”を受賞した今村作品では、友人である梶川信幸氏が制作主任として映画づくりに参画していたことを思い出した。あらためて誇らしく思う。
