
1日、トランプ氏は日本を含むすべての輸出国を対象に鉄鋼製品に25%、アルミ製品に10%の関税をかけると発表した。当初は中国を含む特定12ヶ国に絞った高関税も検討されたとのことであるが、最終的に全輸出国を対象とした案が選択された。
EUは直ちに反発、米に対する報復を警告、これに対してトランプ氏は「貿易戦争、上等。勝てる」と応じ、欧州車に35%の関税をかけると宣言した。
中国も米国産大豆の輸入制限を検討するなどEUと連携して対抗措置を講じる構えであり、世界貿易は報復と脅しの応酬という異常な様相を呈し始めた。
トランプ氏は今回の決定に際して貿易不均衡、雇用喪失といった経済・通商上の問題に加えて、“安全保障上の脅威”を強調する。一方、カナダ、メキシコに対しては「NAFTAで譲歩すれば対象から外す」ことを示唆するなど、“個別取引における条件交渉”であることも隠さない。いずれにせよ原価増が見込まれる自動車、資源、飲料業界はもとより、報復対象となる第一次産業、為替、債権、株のトリプル安が懸念される金融市場など米経済界からも批判が相次ぐ。
昨年末、トランプ氏は1.5兆ドルもの大型減税を成立させた。しかし、その原資となる財政を支える米国債の4割は外国勢が保有しており、最大の債権者は中国である。振り上げられた拳が「取引」の次元を超えて本当に貿易戦争へと向かうとすれば、米国が被る経済的な代償と外交上のリスクはあまりにも大きい。世界からの信任は揺らぎ、分断は更に深まる。
さて、中国に次ぐ米国債の保有国である日本は、3月6日現在、「影響を精査する」「協議を続けたい」などといつもどおりの対米スタンスを貫く。自由貿易の側に立ち、これを主導する好機がすり抜けてゆく。
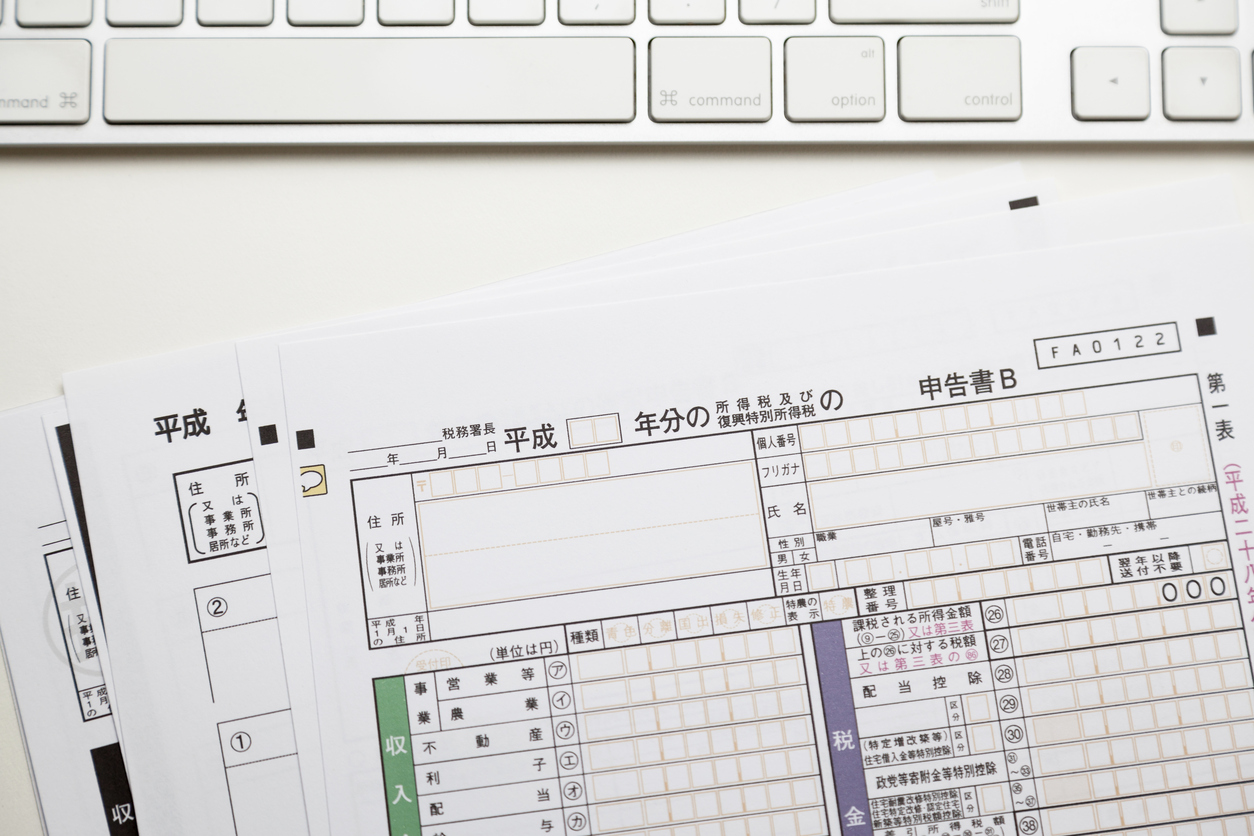
厚労省は28日、2017年の「賃金構造基本統計調査」を発表した。男性の月額賃金は335.5千円(43.3歳、勤続年数13.5年)、女性が同246.1千円(41.1歳、同9.4年)となった。
雇用形態別の前年比は男性が正社員で▲0.2%、正社員以外が▲0.4%、一方、女性は正社員、正社員以外ともに+0.6%、企業規模別では大企業が▲0.4%、中企業は▲0.6%、小企業が+0.9%となった。また、35歳以上の男性は正社員・正社員以外のいずれもほぼすべての年齢層※で前年を下回った。
※60-64歳の正社員のみ前年比プラス(+2.1%)
人手不足が深刻化する中、若者、女性、従業員99人未満の小企業など、賃金がそもそも低い層に対してささやかな待遇改善が行われる一方で、中堅企業や大企業が中高年男性の賃金抑制をはかっている構図が浮かんでくる。
こうした状況は所謂「トリクルダウン効果」が目指した好循環とはまったく異なる様相を呈していると言え、3%の賃上げという政治の掛け声が空しい。
2017年の家計消費支出(二人以上の世帯)は4年連続で実質減少となった。年金保険料のアップなど給与所得者の可処分所得が押さえつけられる中、消費税率の引き上げ、更には高額給与所得者に対する増税が控える。“分厚い中流層”の再生は更に遠のく。

8日午前、両備ホールディングス(岡山)は県内で運行している全78バス路線の4割に相当する31の赤字路線の廃止届けを国交省中国運輸局に提出したと発表した。この背景には赤字路線の運行を支えてきた主力路線への参入を仕掛けた新興の格安バス事業者「八晃産業グループ」の存在がある。
両備グループの小嶋光信代表は「廃止するために廃止届けを出したのではない。地方の公共交通の存続を賭けた問題提起である」と語った。“たま駅長”で一躍有名になった和歌山の貴志川線や中国バスなど地方公共交通の再生に尽力するとともに、補助金に頼らない自立経営のもと県内の不採算路線を維持してきた両備グループの問題提起は廃止対象となった沿線住民からも支援の声があがる。
一方、国交省は発表があった当日、そして、17時過ぎという異例とも言える時間帯に八晃グループの申請を認可した。急いだ理由は不明である。単なる手続き上の偶然かもしれない。ただ、こうした流れを受けて、15日、岡山市、玉野市、倉敷市、瀬戸内市など関連自治体は岡山県に対して地域公共交通活性化再生法にもとづく協議会の設置を急遽要請、県もこれに応じる構えだ。
今、乗合バス事業者の2/3が赤字であり、とりわけ、地方路線は苦境の中にある。背景の一端に2000年、2002年に実施された貸切バス、乗合バス事業の規制緩和があることは言うまでもない。もちろん、市場原理の導入そのものを否定するものではない。とは言え、安全性と安定性が高いレベルで求められるバス事業の公益性を鑑みれば全国一律適用の自由化の弊害は小さくないし、ましてや地方の特定採算路線への限定参入はフェアではあるまい。
運転免許の返上を後期高齢者に求めるのであれば代替交通の提案が必要だ。少子化対策の一環として教育の無償化を導入するのであれば通学の足を確保するのは当然だ。
両備グループが投じた問題は岡山のバス利用者に限定されるものではなく、また、“地方”に固有の問題として扱われるべきものでもない。地方創生、少子高齢化、GDP600兆円、人口1億人の維持、これらの政策との整合性はとれているのか、公共交通を失った地方に未来はあるのか、地方のない国土に魅力はあるのか。問われているのは日本の未来そのものである。

2月5日、インド洋の島嶼国モルディブで「非常事態」が宣言された。ヤミーン政権はナシード元大統領をはじめとする反政府系議員への弾圧を強めていたが、1日、最高裁はナシード元大統領の無罪と12人の野党議員の復権を認めた。これに対して政府は最高裁判所長官を含む判事2名を逮捕、治安当局と反政府側の対立が先鋭化しつつある。
もともとモルディブはインドとの関係が深かったが、2013年にヤミーン氏が大統領に就任すると急速に中国へ傾斜する。
ヤミーン氏は「一帯一路」への参加を表明、道路、橋梁、空港、港湾の整備に中国資本を導入、昨年12月には中国とのFTAにも署名した。
そうした中、対中債務は15~20億ドルへ拡大、金利は10~12%に達するとみられる。返済は来年以降からはじまるが、反政府側は「モルディブの財政状況では延滞は不可避、債務と引き換えに実質的な領土割譲が行われる」ことを懸念する。
2016年、中国は財政が行き詰まったギリシャから国営ピレウス港の株式51%を買い取った。2017年には債権放棄と引き換えにスリランカのハンバンタト港の運営権を取得、パキスタン、ミャンマー、バングラディシュへの投資も強める。アフリカ東部ジプチには海軍基地を設置済みだ。
かつて胡錦濤氏によって「調和の海を目指す」と説明された香港からホルムズ海峡に至る“真珠の首飾り”は、習近平氏のもと名実ともに「偉大なる中華民族」の戦略的ドレスコードとして実現される。

米の金利上昇を背景とした株安が世界に連鎖した。6日は落ち着きを取り戻したものの、米欧中央銀行による金融緩和の“終わり”が意識される中、株式市場の安定が揺らぐ。
そもそものきっかけは先週末に発表された米雇用統計。雇用改善と賃金上昇の大きさが利上げ観測を強めた。株式市場では“高値圏にある株価の調整局面”との反応が大勢であるが、インフレ懸念が取り沙汰される中で金融政策の“正常化”が加速するとの観測が強まる。
リーマンショック以降、各国は財政出動で景気を下支え、中央銀行は国債の購入等を通じてこれを後押しした。政府債務が膨張する中、低金利が維持されてきたのは各国が金融緩和で足並みを揃えてきたからに他ならない。
しかし、米FRBは2015年にはゼロ金利政策を解除、2017年には保有資産の縮小に転じた。欧州中央銀行も“正常化”のタイミングを模索する。
トランプ政権は大型減税とインフラ投資による成長を目指す。7日、米上院は2018年、2019年の歳出上限を3千億ドル引き上げることで合意した。長期金利の上昇圧力はもう一段増すだろう。
一方、日本は2013年の4月に公約した目標(=2年程度内に2%の物価成長を実現する)を未だ先送りしたままである。金融を取り巻く世界情勢が変化しつつある中、“正常化”への道筋は見えない。

30日、米フェイスブックは仮想通貨の売買、仮想通貨を使った資金調達(ICO)、バイナリーオプションに関する広告を全世界で禁止すると発表した。子会社のインスタグラムにも適用される。
同社はこうした広告の多くが「誤解や虚偽を含んでおり、誠実に運営されていない」と判断、将来、これらが社会問題化した際に“フェイスブックが詐欺的行為を助長した”との批判を回避することが狙い。
その数日前、日本ではコインチェック社を舞台に仮想通貨の巨額流出が発覚した。事件の全容はいずれ金融庁や捜査当局によって解明されるだろう。とは言え、事件後に明らかになったセキュリティ体制の杜撰さを見る限り少なくとも原因の一端が経営陣の“不誠実さ”にあったことは否めない。不正アクセスの実行犯はもちろん、同社の経営姿勢そのものが“反社会的”であったと言える。
国家からの制約を受けないネット上の仮想通貨は、“投資”という側面に脚光があたればあたるほど、投機的なヒトとマネーを呼び込む。4年前のマウントゴックス事件では、口座残高の水増し、顧客資産の着服など経営者の“業務上横領”が問われた。その記憶も新しい中での今回の事件は当局そして社会に“これ以上は見過ごせない”という流れを一気に加速させるだろう。
信用創造の新たな可能性が狭まるとすれば残念だ。しかし、テクノロジーとビジネスモデルの進化に委ねるだけでは解決しない。仮想通貨は単に通貨取引に似せた架空の投機商品に過ぎないのか。経済的、政治的、文化的な文脈において“通貨”としてのリアルな思想を社会の側からも問い直すべき時期にある。
