
ヤマト運輸の労働組合は宅配便の荷受量に総量規制を課し、労働環境の改善をはかるよう経営側に求めた。背景にはネット通販の急拡大、サービス競争の激化、単価下落、慢性的なドライバー不足がある。
一方、経営側にとっても“利益が出ない繁忙”は限界に来ており、今後、労使一体となって事業構造改革を進める方針である。
具体的には2017年度の宅配便荷受量を今年度水準に抑えるとともに大手顧客に対して値上げを要請する。また、再配達や時間帯指定サービスについても見直しを求める。
2倍を越える有効求人倍率の常態化は物流業界にとって重大な成長阻害要因である。絶対的なドライバー不足を解消できない大手事業者は6万社を越える中小個人事業者に配送業務を委託しているが、こうした下請事業者も6割が赤字である。
政府は昨年5月に改正物流総合効率化法を成立させ、事業者間の垣根を越えた協同配送を促すが、問題解決の決定打とはなっていない。
急激な需要拡大と熾烈な競争の中で進化してきたきめ細かな配送サービスはまさに“ジャパン・クオリティ”と言っていい。しかし、もはやそのコストを吸収できる余力は配送を担う側にない。店舗への投資を必要としない通販事業者、自宅に届くことの便益を享受する消費者、コスト構造の再配分が求められている。
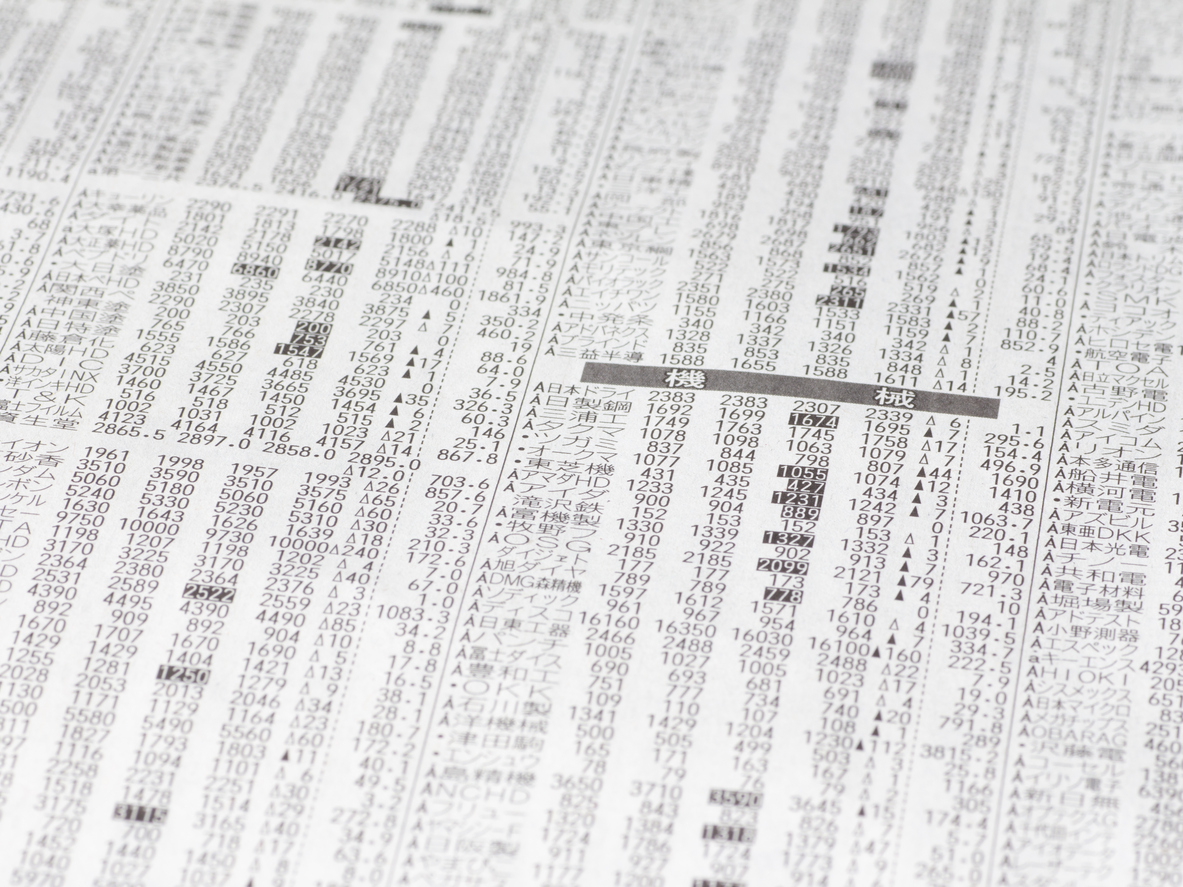
14日、4-12月期の決算発表を見送った東芝であるが、12月末時点で既に1900億円を超える債務超過であったという。加えて米WH社関連に不正な決算処理があったとの新たな疑惑も浮上した。すべては2006年に市場価値の3倍もの価格でWH社を買収したことに始まるが、結果、統治能力を欠いたまま粉飾を承継し続けた歴代経営陣が東芝を窮地に追い込んだ。
1日、日立製作所は2017年3月期の営業利益見通しを200億円引き上げたが、一方で原子力事業における700億円の減損を明らかにした。これは米GEとの共同出資会社GE日立ニュークリアエナジー社の子会社で進めてきたウラン濃縮技術の開発を断念したため。事業の厳格な見直しは当然である。しかし、持分800億円の1/8への減損はそもそもの事業評価が過大ではなかったか。
3日、三菱重工と日本原燃は仏の国営企業アレバ・グループへの出資を決めた。三菱重工の出資額は約300億円(2億5千万ユーロ)というが、2011年以降営業赤字が続く実質的な破綻企業への巨額投資は果たして経済合理性に適うのか。三菱アレバ連合が期待していたベトナムの事業は白紙撤回され、トルコについても不透明である。「20-30年後に再び原発ルネサンスが来る」(三菱重工関係者、12月9日付け日経新聞より)といった楽観論では心もとない。
いずれにせよビジネスとしての原発の事業環境が大きな岐路にあることは間違いない。三菱重工のプレスリリースでは「2015年に日仏両国政府間で確認された両国政府および原子力産業業界の連携強化への貢献」が謳われているが、原発事業はまさにその通り、あらゆる意味において一民間企業で制御できるリスクの範囲を超えている。

日米首脳会談が目前に迫った。米国第一主義を掲げるトランプ政権に対して、日本は「日米成長雇用イニシアティブ」という経済パッケージを準備しているという。公的年金(GPIF)を含む日本側資金を最大限活用し、米国内インフラへの投資や先端技術の共同開発などを通じて51兆円の市場を日米で創出し、70万人の雇用を生み出すという。
日本は巨額な対米貢献をコミットメントすることで、日米同盟の強固さをアピールするとともに為替を絡めた二国間FTAへの流れを阻止したいとの思惑であるが、果たして“予測不能”のトランプ政権に通用するか。
一方、メキシコ、チリ、ペルー、コロンビアで形成する中南米「太平洋同盟」は米を除くTPP参加国に中国、韓国を加えた新たな自由貿易圏構想を目指すという。
世界が新たな次元に移りつつある中にあって、トランプ政権への無批判な従属は日本の可能性を狭めることにならないか。米国とのパートナーシップの重要性を否定するものではない。しかし、シナリオは一つではない。アジアや中南米の潜在的可能性は大きい。世界経済の不透明感が増しつつある今こそ、日本は自由経済による市場創出にイニシアティブをとるべきである。新興国の社会的安定を支援し、事業機会を継続的に提供することで、民の成長と地政学的リスクの軽減を目指すべきであろう。そうあってはじめて国際社会におけるプレゼンスの向上と対等な日米関係が可能となる。

分断と拒絶の連鎖が現実の懸念となりつつある。27日、トランプ大統領は中東、アフリカの指定7カ国からの入国を制限する大統領令に署名、各地の空港では29日までに280人にのぼる渡航者や難民が入国を拒否された。これに対してニューヨークやボストンの連邦地裁は大統領令の執行停止を決定、入国制限の一時解除と強制送還の停止を命じた。また、イエーツ司法長官代行※、首都ワシントンを含む15の州司法長官もこの大統領令の違憲性を指摘した。
※ホワイトハウスはイエーツ長官代行を直ちに解任、後任にバージニア州東地区のダナ・ポエンテ検事を指名、同判事は大統領令を執行するとの立場を表明した
こうした中、カナダのトルドー首相は「カナダは難民を歓迎する」旨の声明を発表、独メルケル首相、仏オランダ大統領、初の首脳会談で「英米の蜜月ぶり」を演出したばかりの英メイ首相も直ちに不同意を表明した。また、スターバックスは全世界の店舗で1万人の難民を雇用する方針を発表、ツイッター社は公式アカウントで「ツイッターは移民とともにある」とつぶやいた。アップル、グーグル、フェイスブック、アマゾン、ナイキ、ゴールドマンサックス、フォード、GMなど、大手企業も相次いで懸念を表明した。
イランのザリフ外相は「今回の大統領決定は過激派集団に対する偉大な贈り物である」と皮肉ったが、残念ながら反ムスリム主義者に対する“贈り物”にもなった。29日、カナダのモスクで礼拝中のイスラム教徒に対する乱射事件が発生、6人の命が奪われた。
米国そして世界がトランプ政権に対して抗議の声をあげる中、自由と民主主義を党名に冠するわが国の与党党首は「コメントする立場にない」と意思表明を留保した。Shame!

20日、16分という短い就任演説において、「勝利はあなた方のものであり、アメリカ合衆国はあなた方の国だ」とトランプ氏は語りかけた。しかし、彼を支持する“あなた方”以外の国民が抱く懸念を払拭させる内容はなかった。演説は選挙期間中そのままの彼が、第45代アメリカ合衆国大統領として、あらためて「アメリカ第1主義」を世界に対して宣言したものであった。偉大なアメリカの実現に向けて「米国製品を買い、米国人を雇う」と語った彼は、言葉どおりTPPからの離脱とNAFTAの再交渉を表明した。
仏の歴史人口学者エマニュエル・トッドは、米国が主導したこの35年間のグローバル化を「世界の解放、エリート主義、階級への分裂、収入の格差、社会的経済的不平等が広がった時代」と捉え、その反動として「国民国家の枠組みへの回帰」がはじまった、とトランプ現象を総括、「世界は一致に向かっていない」と断じた(「グローバリズム以後」、朝日新聞出版)。
確かに、トランプ氏やサンダース氏の登場、また、英国のEU離脱も“時代の大きな流れの中での必然である”と理解すべきであろう。
暴走したグローバリズムに一定の調整は必要であり、国民国家や共同体が再興してゆく過程で民主主義の危機が超克されるのであれば、それは希望となる。
現時点でトランプ政権の行方はまだ完全に見えない。しかしながら、もしも超大国アメリカが、力を背景に排外主義の徹底を強行するのであれば、新たな差別、分断、萎縮、不正義、そして、暴力を国内そして世界に呼び込みかねない。
未来の歴史学者にとって、それは“時代の移行期における一時的な混乱”に過ぎないかもしれない。しかし、今を生きる私たち自身が“時代の必然”などと正当化してはなるまい。求められているのは時代をつなぐビジョンである。

17日、英国のメイ首相はEUからの完全離脱を宣言した。ヒト、モノ、サービスの自由な移動を保証する単一市場から離れ、独立国としての権限を取り戻す。
一方、メイ氏は「野心的な自由貿易協定」を各国と締結し、“グローバルな貿易立国”を目指すとも表明した。
EUとの交渉は容易ではあるまい。そもそも英国の正式な離脱は2年という交渉期間の終了後であり、この間における第3国との交渉は禁じられている。移行期間の設置も取り沙汰されるがこれもまだ不透明である。
日本から英国への直接投資額は22億1000万ポンド、1000社を越える企業が英国に拠点を構える。そして、その多くが英国を含む単一市場EUを見据えての進出である。
経営環境の不透明感は募る。しかし、それゆえに現時点で過剰に悲観する必要はない。むしろ、欧州戦略を見直す好機として、シンプルに自社の海外事業を問い直すことが最大の備えとなるはずだ。
今、米国の行方も見えない。習金平氏はダボス会議で「他国を犠牲にして自国の利益追求をしてはならない」とトランプ氏に釘を刺したというが、自国の政策を省みればそれもまた「取引」の言葉にしか聞こえない。
大英帝国の盟主、英国が自治植民地に対して本国との対等な地位を認めたのは1931年のウェストミンスター憲章である。以後、各国は独立へと進む。立場は逆転した。時間はかかるだろう。しかし、この交渉を通じて英国が“開かれた独立国”として新たな国家観を確立し、一方でEUも地域統合の理想と制度を再定義し、そのうえで両者が生み出す“グローバリズムの次のステージ”に期待したい。
