
7月16日、太平洋の島嶼国14か国、仏領2地域と日本、豪州、ニュージーランドが参加する「第10回太平洋・島サミット(PALM)」がはじまった。PALMは日本が主催する国際会議で南太平洋地域の安定、社会課題の解決、経済発展を目的に1997年から3年ごとに開催している。会議では、気候変動や脱炭素、防災・海面上昇対策や通信環境や金融インフラの整備、人材育成などに関する支援策が議論されるとともに、各国・各地域への個別支援についても協議される。会議は3日間の日程で最終日に共同宣言を採択する。
太平洋島嶼国・地域と日本との関係は深い。日本による委任統治時代を経験したミクロネシア地域では移民をルーツにもつ日系人が人口の2割を占める。伝統的に親日的で、人的交流も盛んである。日本にとってはマグロやカツオの主要漁場であるとともに海上輸送の要所でもある。安全保障環境が厳しくなりつつ中、各国・各地域とのパートナーシップの重要性は高まる。
一方、この地域を対米防衛ラインの最前線と位置付ける中国の圧力も増す。2019年にはキリバス、ソロモン諸島が、今年1月にはナウルも台湾と断交、中国との国交樹立を表明した。米国も関与を強める。2023年にクック諸島とニウエを国家承認、ソロモン諸島とトンガに大使館を設置する。米中対立というリスクを戦略的に利用する、あるいは、せざるを得ない国・地域もある。とは言え、「巻き込まれたくない」が本音ではなかろうか。地域の包摂と安定こそが全てのステークホルダーにとっての利益である。日本外交はまさにこれを主導いただきたい。
さて、ここまで書いたところで(株)共同通信社の「kyodo Weekly NO29」(2024.7.15)に掲載された船越 美夏氏のコラムが目にとまった。タイトルは「激戦地で眠り続ける時限爆弾」、第2次大戦中、太平洋地域で沈没した軍艦や徴用船は3855隻、80年の時を経て腐食と劣化が進み、船内に残っている最大57億ℓと推計される燃料や大量の兵器が流出する可能性がある、という。この差し迫った危機、すなわち “時限爆弾” の問題は1999年にソロモン諸島によって提起されたが、爆弾は未だ “眠り続けたまま” である。沈没船の86%、3322隻が日本船であるという。PALMの主催国であり、当事者でもある日本が果たすべき役割は大きい。

中小企業の倒産が高水準で推移している。2024年1-6月期の倒産件数は前年同期比2割を越える。構造的な後継者難に加えて、人手不足、仕入れ価格の高騰、過剰債務など、価格転嫁力の弱い下請型中小企業の資金繰りの悪化が背景にある。政府は「中小企業にも賃上げの流れが進んだ」と自賛するが、賃上げを実施した中小企業の6割が “業績の改善が見られない中での防衛的な賃上げ”(日本商工会議所、東京商工会議所の調査より)であることを看過してはならない。
一方、業績不振が常態化し、社員に十分な給料を支払うことが出来ず、公的支援と借金で延命してきた中小企業、所謂 “ゾンビ企業” は退場すべきだ、との声も大きい。技術革新に追いつけず、旧来のビジネスモデルから抜け出せない企業の淘汰はむしろ歓迎すべきであり、資本と労働力の成長産業への移動は日本経済全体の生産性の向上と持続的な成長に資する、というわけである。
しかし、はたして “苦境にある下請企業=ゾンビ企業” であるのか。3月7日、公正取引委員会は下請事業者36社に対する不当減額について日産自動車に是正勧告を行った。日本を代表するグローバル企業による「下請いじめ」は本来であれば “衝撃的” と受け止められて然るべきであるが、社会の空気は「やっぱりか」という落胆に溢れた。そして、その通り、今度はトヨタ子会社だ。7月5日、公取委は特装車などを手掛けるトヨタカスタマイズ&ディベロップメントに対して、下請企業に対する金型の無償保管と不当返品について是正勧告を発した。
令和5年度、下請法違反にもとづく公取委の勧告件数は直近10年度で最多の13件、指導件数は8千件を越える。ピラミッド型の下請構造の頂点に立つ完成車メーカーへの勧告はまさに日本のサプライチェーンの構造問題を象徴する。30年におよぶ日本経済の停滞、生産性の低さの原因はどこにあるのか。中小企業の付加価値を搾取し、生産性を押さえ込み、自立の機会を奪ったのは、イノベーションを怠り、国内のデフレに甘んじ続けてきた大手企業の側ではないか。何とかすべきはむしろこれらの “ゾンビ” たちだ。

6月24日、金融庁は三菱UFJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券の3社に対して金融商品取引法(金商法)にもとづく業務改善命令を、持ち株会社の三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)に銀行法にもとづく報告徴求命令を出した。問題となったのは所謂 “ファイアウォール規制(FW規制)” と呼ばれるルールで、三菱UFJ銀行の顧客企業の非公開情報をグループ内で共有、銀行という優越的な地位を利用して証券取引等の勧誘を行った、ことが問われた。
FW規制は銀行を中心とした業界再編と金融のグローバル化を背景に規制緩和が進んできた。2022年には、上場企業については企業側からの拒否表明がなければ同一金融グループ内での顧客情報の共有が容認された。有識者による議論は「上場企業から非上場へ、いずれは中小企業や個人へ」の方向で進んでいる。とは言え、その前提として、情報共有に対する同意確認、利益相反取引の厳格な管理、優越的地位の乱用防止、情報セキュリティの強化、が求められることは言うまでもない。
メガバンクによるFW規制違反はMUFGがはじめてではない。2022年、SMBC日興証券の株価操縦を巡る捜査の過程で、三井住友銀行の顧客企業の非公開情報がSMBCグループ内で共有されていたことが発覚している。野村HDなど独立系証券が慎重な対応を求める中で、規制緩和を主導してきたメガバンク2トップの不祥事はまさに規制緩和の “前提” に対する信頼への背信であり、議論の後退は避けられないだろう。
業界や社会において、もっとも広範な影響力、もっとも大きな既得権、言い換えればもっとも強大な “権力” を持つ者たちによるルール違反や法令軽視に関する不祥事が後を絶たない。MUFGしかり、トヨタしかり、政治家しかり、役人しかり、と言えようか。一方で、“法に反しなければ” を口実に詭弁と炎上商法を弄する者たちも増殖する。驕りと独善に塗れ、フェアであることが蔑まれる社会でいいのか。しっかりしてくれよ、日本の大人たち!

東京の不動産価格の高止まりが続く。この春以降、やや落ち着きつつあるが、新築マンションの1戸当たり平均販売価格が1億円を越えた昨年からの趨勢は変わらない。こうした中、今年1月から入居がはじまった “晴海フラッグ” で、住民票登録がない物件が全体の3割に達し、500戸を越える分譲物件が転売、賃貸に出されていていることが過熱する不動産投資の象徴事例としてあらためて衆目を集めている。
“晴海フラッグ” は、東京オリンピック・パラリンピックの選手村を改修した大規模マンション群で、もともとが都有地であるため販売価格は周辺相場に対して割安となった。結果、投資資金が殺到、売り出し時の平均倍率は70倍、もちろんすぐに完売し、同時に転売もはじまった。リセール価格は急騰、今や購入できる層は業者、富裕層、外国人、そして、ハイクラスの “パワーカップル” に限られる。
そもそも公有地の開発物件に対して、投機筋を抑える制限を何らつけなかったことも問われるが、それはひとまず置くとして、低金利、円安という金融環境がTOKYOの一等地の旨味を倍増させたということだ。先日、中国、米国、アジアで幅広く事業を展開する旧知の中国人実業家が筆者を訪ねてきた。彼曰く、「港区やベイエリアは中国人が多くて安心する。白金あたりは日本人にとっての虹橋・古北(上海の日本人居住エリア)のようだ」とのこと。彼にとってのTOKYOは投資対象であり、かつ、ビジネスや生活のリーズナブルな拠点というわけである。
18日、国土交通省は「令和6年版 首都圏白書」を発表、「東京への転入超過が20代でコロナ前の水準を越えるなど首都圏への人口流入が戻りつつある。一方、30代、40代では都内から埼玉、神奈川、千葉、茨城へ転出する傾向もみられ、コロナ前のそれぞれ2倍、4倍となった」という。同レポートは生活意識の変化も指摘する。東京圏在住者の全年齢で “地方移住” に対する関心が高まっており、とりわけ20代では44.8%に達する。とは言え、地方へのハードルは高い。都心の物件に手が届かない子育て世代は近郊4県へ、収入への懸念から若者は東京から出られない。雇用、職種、地域、働き方、資産、生活価値観、、、あらゆる局面で進行する “ギャップ” と “ミスマッチ” がウェルビーイングを遠ざける。

6月12日、EUは中国製EVの輸入に対して現行の10%に加えて最大で38.1%の追加関税を課す暫定措置を発表した。実施は7月4日から、関税率は今後の協議を経て決定されるとされ、政府からの補助金の規模や調査への協力姿勢が問われる。中国製EVへの輸入関税は米国が25%から100%へ引き上げたばかりであり、中国当局は強く反発、対抗措置も辞さない構えである。
中国は世界の自動車輸出市場で日本を抜いて既にトップに立っている。もちろん、主役はEVだ。一方、国内市場は景気の低迷と補助金の打ち切り(2022年末)※によって成長は鈍化、急拡大した生産能力と実需とのギャップが価格競争を激化させている。今年に入って市場シェアNO1の比亜利(BYD)や米テスラでさえも値下げに追い込まれた。財務基盤の弱い新興メーカーは軒並み赤字に転落、早くも再編淘汰が始まりつつある。
国外へ溢れ出した中国製の低価格EVに身構える欧州の危機感は当然だ。とは言え、自動車産業を育成すべく外資との合弁を促してきた中国が、結果的に外資の “生産部門” に甘んじ続けた状況を打開すべく、産業政策の方向性を次世代市場(EV)に転じた判断は見事だし、自国の産業育成のための政策投資それ自体が “不当” であるとは言い難い。特定産業への財政支援は多かれ少なかれどこでもやってることであり、補助金による市場育成は言わば正攻法とも言える。問題はその “多かれ少なかれ” にある。桁違いの “規模” の大きさがもたらす影響が尋常でないということだ。
中国製EVへの課税を巡る攻防は新たな政治問題だ。ただ、世界のEV市場の6割を占める中国は外資にとって無視できず、ことEVを巡っては外資が “学ぶ” 側にある。VWは新興メーカー“小鵬汽車(シャオペン)” に出資、同社のIT技術を活用し、開発コストを抑える。ステランティスは “零跑科技(リープモーター)” と合弁会社を設立、オランダを拠点にこの秋からリープモーターブランドのEVを欧州で販売する。3月20日、スマートフォン大手“小米科技(シャオミ)”グループの小米汽車が初のEVを発売した。価格帯は5百万円前後ながら初回販売5万台を発売後27分で売り切った。設立からわずか3年、本体の現預金は2兆8千億円を超える。欧米そして日本勢が警戒すべき本当の相手はこちらである。
※2024年4月、中国当局は国内消費の刺激策の一環として、新エネルギー車(NEV)への購入補助を再開、旧型乗用車からの買い替えに対して約22万円(1万元)を助成する。
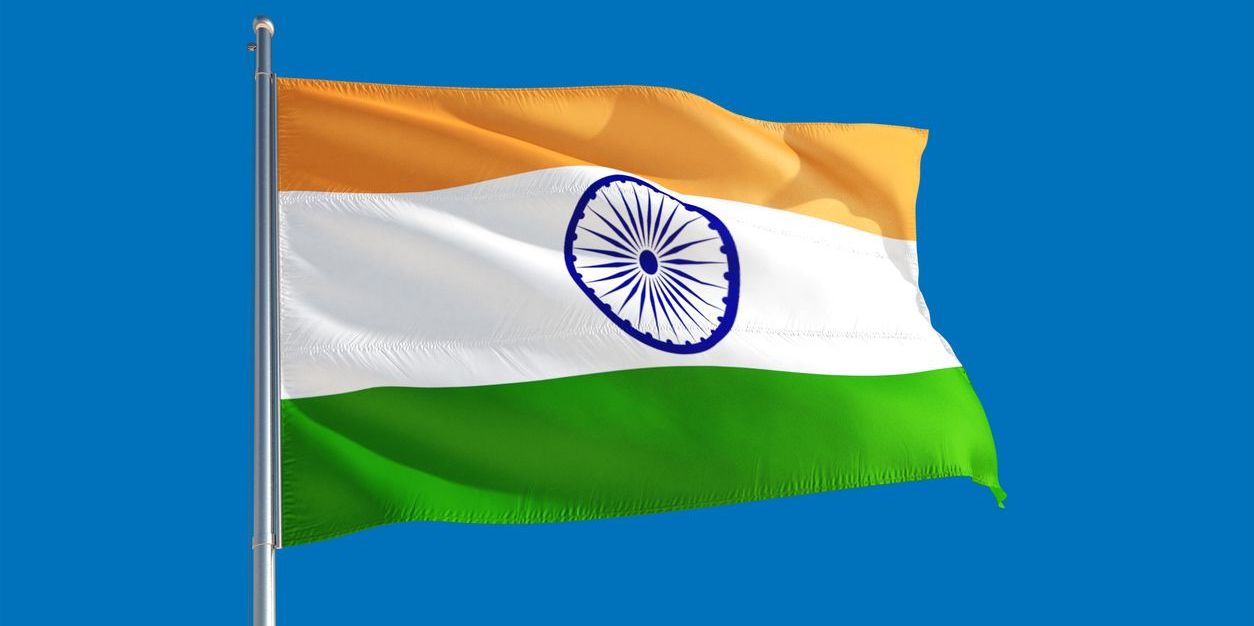
6月4日、有権者約9億7千万人を擁するインドの総選挙が開票された。結果は与党連合「国民民主同盟(NDA)」が293議席を獲得、過半数を確保した。モディ首相は与党連合の3期連続の勝利を「歴史的偉業」と自賛、6月8日の宣誓式に臨む。とは言え、モディ氏率いるインド人民党(BJP)は2019年選挙の303議席から240議席に後退、単独過半数272議席に届かなかった。野党連合は229議席に躍進、これに対抗するうえでもNDA側の少数政党の影響力も強まる。国政におけるBJPの求心力低下は避けられまい。
一方、国際社会におけるインドの存在感は揺るがないだろう。人口は既に中国を抜き世界1位、ドイツを抜いてGDPが世界3位となるのも時間の問題だ(IMF予測では2027年)。初代首相ネルー氏から続く全方位外交も顕在だ。2022年9月、モディ氏はプーチン氏との首脳会談の席上「今は戦争の時代ではない」と直言する一方、欧米の対露制裁には加わらずロシア産原油の輸入を拡大、ロシア経済を下支えする。中国とは国境で対峙しつつ、上海協力機構(SCO)のメンバーでもある。米バイデン政権には国賓として迎えられ、2023年にはG20首脳会議で議長国を務めた。
インドの立ち位置は “グローバルサウス” の盟主である。植民地時代の負の遺産をひきずり、富の配分や国際秩序の在り方に不満を持つ新興国や途上国のリーダーとして振る舞う。そして、そのためには自由、人権、民主主義といった価値観を越えて、政治的に “中立” である必要があり、ここをカムフラージュに自国の利益を徹底追求するのがインド流と言えよう。
問題はモディ氏の極端なヒンドゥー主義化、権威主義化である。選挙期間中、氏は自身を「神に選ばれし者」と称し、イスラム教徒を「侵入者」と表現した。圧勝が予想されたBJPの苦戦は格差の拡大、失業率の高まりが主因とされるが、独立以来の国是である政教分離主義の放棄に対する批判票も少なくないだろう。ヒンドゥー原理主義にもとづく国家建設が氏の理想であれば、多様性と非同盟主義に支えられたインドの強みはやがて失われてゆくはずだ。対立と分断は停滞を招くだけである。グローバルサウスのリーダーが目指すべきは1947年に掲げられたインド独立の理想である。
【関連記事】
「インド、多様性を未来につなぐために世俗主義への回帰を」今週の"ひらめき"視点 2023.9.17 – 9.21
