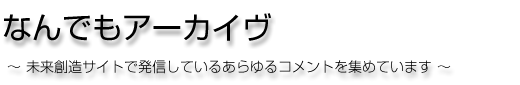異質な文化に対する相互の寛容が過激主義を封じる
24日、国際捕鯨委員会(IWC)の総会がはじまった。日本は国際司法裁判所の判決(2014年)を受けて南極海での捕鯨を一端中止したが、昨年末から再開、今回は再開後初めての総会ということもあり反捕鯨国の強硬姿勢が目立つ。
調査捕鯨の実施主体である財団法人日本鯨類研究所の予算が鯨肉の売上収益で成り立っているという視点に立てば、反捕鯨国が主張する「調査捕鯨の名を借りた商業捕鯨」との批判に一定の理があることは否めない。これに対して、日本は、これまで要求してきた“日本近海での捕獲枠”問題を取り下げ、調査捕鯨の科学的意義と正当性を議論の俎上にあげる。しかしながら、そもそも捕鯨産業の発展を目的に設立されたIWCの性格は既に変質してきており、捕獲頭数を巡る現実的な交渉を展開してきた日本と反捕鯨国との論点は嚙み合わない。
もはやこの問題は、“産業の保護”や“資源の維持”といった議論では片付かない。民族の伝統や食文化、生態系の維持、動物愛護、先住民族の権利や地球温暖化や環境問題も絡む。反捕鯨の急先鋒オーストラリアやニュージーランドにとっては観光資源(=ホエール・ウォッチング)の拡大といった思惑もあるだろう。シーシェパートに象徴される過激な暴力集団を封じ、IWCにおける議論を前へ進めるためにも日本は戦略全体を再構築すべきではないか。現実の国際世論に対応した、ぶれることのない大義をベースに捕鯨の在り方そのものを自ら問い直す必要があるということだ。キーワードは生物と文化の多様性、そして、共生である。
今週の”ひらめき”視点 10.23 – 10.27
代表取締役社長 水越 孝
~変化の予兆をつかむ、変化の本質を見抜く~
今週のWebニュースクチコミランキングはこちらからもご覧になれます。