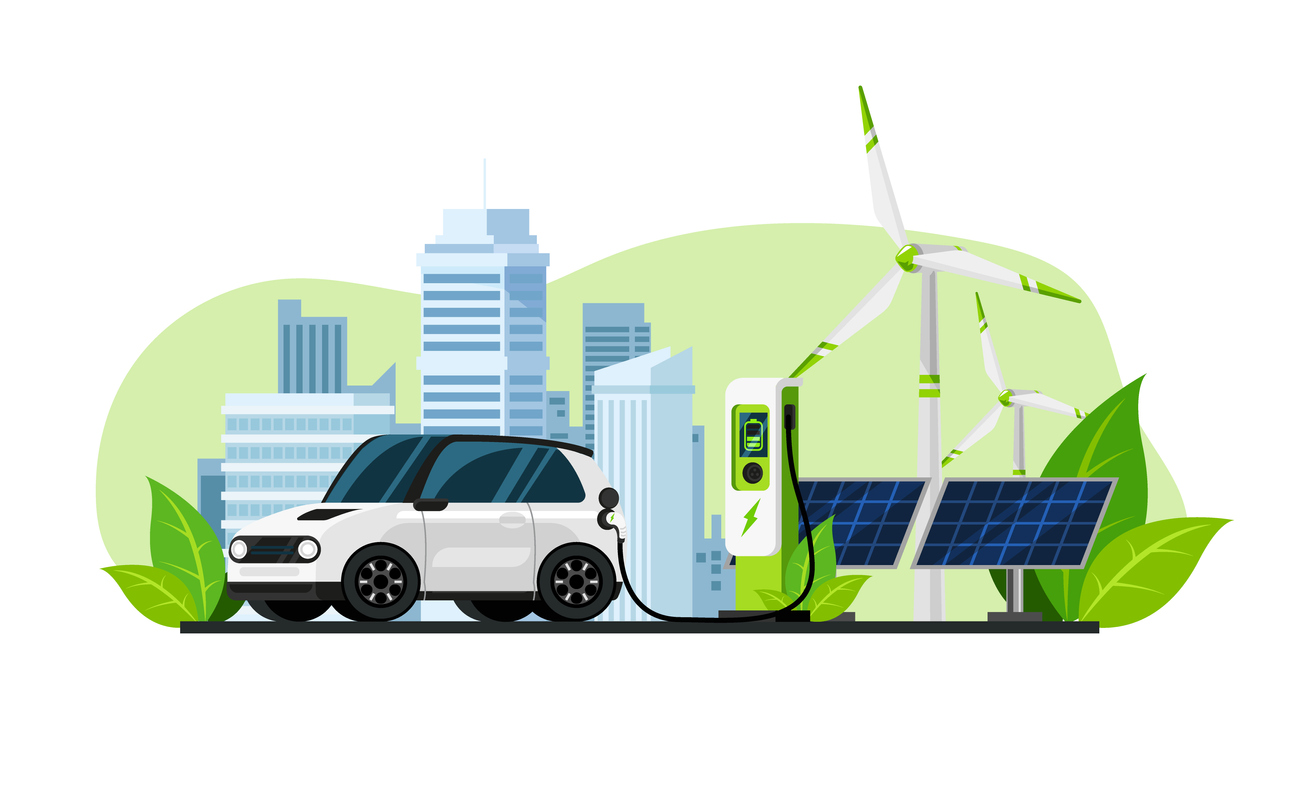
4月23日、世界最大級の自動車展示会「上海モーターショー」が開幕した。主戦場は電動化と自動運転である。内外の大手自動車メーカーからIT系スタートアップ企業まで、まさに群雄割拠と言える状況の中、各社は自動運転レベル3に対応したEVやPHV、AIを実装したスマート・モビリティの完成度と提案力で競い合う。そこでは欧米日の“エスタブリッシュメント勢”のブランド力も色褪せる。
トヨタは華為技術(ファーウェイ)のOSを採用、「スマートフォンと同じ使い勝手を実現した」とアピール、ホンダの現地合弁会社は中国新興AI企業が開発した“Deepseek(ディープシーク)”を新型車に搭載、BMWも中国市場向けの車種にDeepseekを搭載すると発表した。EVの弱点、“充電時間”に対するソリューションも実装されつつある。バッテリー交換式のEVメーカー上海蔚来汽車(NIO)はすでに国内3000か所にバッテリー交換ステーションを設置済だ。欧州主要都市への展開も進める。交換に要する時間はわずか3分~5分である。比亜迪(BYD)も“1秒2㎞”の高速充電システムを開発、フル充電に要する時間はこちらも5分だ。
2024年1月、経済産業省などはバッテリー交換式EVについて「我が国で開発・実証される技術の国連基準化を目指してオールジャパンで取り組む」と表明、京都や東京でタクシーやトラックなど商用車分野における実証実験をスタートさせている。とは言え、オールジャパンゆえであるのか、既得権の大きさゆえであるのか、社会実装にはまだまだ時間を要する状況だ。そう、ここが欧米日の“エスタブリッシュメント勢”に共通した弱みであり、国家の強力な産業政策のもと、生き残りを賭けて凌ぎを削る中国新興起業家たちとの差が歴然となる局面だ。
さて、そのBYDが日本の軽自動車市場に専用EVを投入すると発表した。軽自動車は新車市場の4割を占める。欧米からさんざん“非参入障壁”と批判され続けてきた日本メーカーの独壇場である。まさにチャレンジだ。一方、国内からは人材の引き抜きや技術流出を懸念する声があがる。ただ、インド市場を制した故鈴木修氏であれば、きっと“正々堂々、受けてたつ”とおっしゃられるのでは? スズキのインド進出は1982年、誰もが無謀な挑戦と評した。今、日本勢に必要なのはこのベンチャースピリットだ。かって世界の自動車市場の盟主であった国の大統領が「日本の非関税障壁はけしからん。日本はボーリング球をクルマにぶつける検査をしている!」などと難癖をつけている今こそ、グローバル市場の重心を引き寄せる好機である。

4月14日、総務省は「2024年10月1日時点における外国人を含む日本の総人口が1億2380万2千人、前年比55万人減(▲0.44%)、死亡者が出生児を上回る“自然減”は89万人で過去最大」と発表した。総人口のうち日本人は1億2029万6千人で前年比89万8千人減(▲0.74%)、外国人は350万6千人、同34万2千人増(+9.8%)。外国人の増加は傾向的ではあるが、現状では“焼石に水”と言えよう。
総人口に占める割合は東京がトップで11.5%、これに神奈川7.5%、大阪7.1%、愛知6%、埼玉5.9%、千葉5%と続く。首都圏1都3県で29.9%、首都圏+大阪+愛知で43.0%、都市部の寡占状況は変わらない。年齢別では文字通り“少子高齢化”が加速、15歳未満の総人口に占める割合は11.2%と過去最低(前年比34万3千人減)、65歳以上は29.3%と過去最高(同1万7千人増)、とりわけ75歳以上の割合は16.8%(同70万人増)に達している。
こうした中、各自治体は自身の人口減少に歯止めをかけるべく、移住・定住促進策や子育て支援の手厚さ、独自性で競い合っている。しかしながら、都道府県別で人口増となったのは東京と埼玉のみで、いずれも“社会増”。すなわち、他地域からの流入であって“自然減”を“社会増”が上回った結果である。東京は首都ゆえの圧倒的な求心力と子供関連施策の充実ぶりが奏功していると言えるが、その東京であっても2023年の婚姻件数は2019年比で▲17%(全国平均は▲21%)、自然減の反転は期待できない状況にある。
自治体間競争を否定するものではない。しかし、“移動”で全体が増えるわけではない。この構造は“ふるさと納税”と類似する。確かに都市から地方への流れは生み出した。個別にみれば恩恵を受けた自治体は少なくない。一方、返礼品コストや地方交付税による減収補填を鑑みると全自治体の行政サービス財源の総和は減少している。日本が人口置換率2.07を割り込んだのは1974年だ。半世紀もの無策の結果が今である。その今から半世紀後、2075年の人口は約8700万人と推定される。50年後の日本はどうあるべきか、この問いを出発点に目先の奪い合いを越えた、持続的で総合的な施策を考えてゆきたい。

3月31日、政府の中央防災会議は南海トラフ巨大地震の被害想定を公表した。東日本大震災の6倍、292兆円と試算された被害規模の大きさはもちろん、被災の様相を刻々と記述した内容にあらためて慄然とさせられる。発災と同時に61万棟から128万棟が揺れのため全壊、最大7.3万人が命を失う。直後の津波で最大20.8万棟が全壊、9.7万人から21.5万人が死亡、加えて火災により最大76.8万棟が焼失、最大2.1万人が犠牲となる。発災翌日の避難者は340-610万人、中京・京阪神都市圏の帰宅困難者は330-400万人に達するという。
報告書はライフライン、交通インフラ、災害関連死、孤立集落、文化財、エレベーター内の閉じ込め、ご遺体への対応に至るまで項目ごとに被災の影響をきめ細かく検討している。また、近畿阪神・中京圏という巨大都市と日本のサプライチェーンの要と言える太平洋ベルト地帯が被災することによる国内外の暮らしや経済への影響、生産活動・物流寸断の長期化に伴う産業構造の変化、国際競争力の低下リスクについても言及している。
一方、原子力災害に関する記述は物足りない。原発リスクはあくまでも“複合災害”の1つとしての扱いであり、「浜岡や伊方の原子力発電所の地震対策は原子力規制委員会の指導・監視のもと、事業者が確実に取り組むべき」との指摘にとどまる。静岡県が策定した浜岡地域の原子力災害避難計画では、全面緊急事態に際して例えば掛川市では富山市や黒部市、磐田市は金沢市や小松市が避難先として想定されている。避難経路は東名→名神→東海北陸道だ。はたして南海トラフ巨大地震発災に伴う複合災害発生時にこの計画は機能するのか。
政府は同様の試算を2013年に行っている。この時の想定被害額は220兆円、政府はこれを受けて防災対策基本計画をとりまとめた。しかし、12年を経て想定被害額は拡大した。背景には社会資本の老朽化問題がある。下水管腐食による八潮市の道路陥没、上越市の水力発電所の水圧管路の破断、笹子トンネル崩落事故も記憶に新しい。限られた予算、技術者不足、資材高騰といった自治体や事業者など管理者側の事情もあるだろう。しかし、被災エリアが広域におよぶ巨大地震対策では、縦割り行政を越えた司令塔と予算が必要だ。とりわけ、最悪の複合災害である原発リスクを最小化するためには従来の枠組みを越えた体制が必須である。学ぶべきことのすべては“フクシマ”にある。

4月2日、米トランプ政権はすべての国・地域に対して一律10%の基本関税を課すとともに、貿易相手国の関税率や非関税障壁に応じた“相互関税”を課すと表明した。トランプ氏は「この日は長い間待ち望んできた解放の日だ」、「相互関税はアメリカにとって経済的な独立宣言である。今こそアメリカが繁栄する番であり、新たに獲得する富で、減税と国家債務の削減を実現する。アメリカは再び偉大になる」などと述べた。
公表された相互関税は中国34%、台湾32%、インド26%、韓国25%、EU20%、ベトナム、インドネシア、タイなど東南アジア諸国も軒並み30%を越える。日本は24%だ。2024年の対米輸出額は21兆3千億円、うち自動車と自動車部品で7兆2千億円、全体の34%を占める。建設用重機、光学機器、半導体製造装置の輸出額も大きい。海運・物流業界など輸出関連業界への影響も小さくないだろう。政府には“24%”の不当性を毅然と主張するとともに自由貿易への回帰を促していただきたい。
しかしながら、はたしてトランプ氏の思惑どおり米製造業は復活出来るか。高関税による物価高は消費者を直撃するだろうし、仕入れ、卸価格の突然の高騰は事業者にとってコスト増でしかない。確かに関税強化は海外から直接投資を呼び込むインセンティブにはなるが、そもそも高品質で割安な輸入品に依存してきたサプライチェーンを短期間で作り変えることには無理がある。ましてや移民を制限する施策を進めつつ国際市場で戦えるレベルまで米製造業の人件費を下げることなど不可能であろう。
トランプ氏が“先祖返り”に血道を上げているこの4年間を日本はどう活かすか。輸入を止めることなど出来ない米国においては相互関税が日本企業に相対的に有利に働くケースもあるだろう。もちろん、大半の輸出産業にとっては突然の“巨大災害”だ。であれば、国は早急に危機対応予算を組んで関連事業者を支えるとともに、TPP、RCEPといった多国間自由貿易を軸とした市場開拓、供給網の再編に向けた支援の枠組みを整えていただきたい。いずれにせよこの4年間は事業構造改革を進め、国際的なプレゼンスを高める絶好の好機である。私たちはそれぞれの立ち位置においてこのチャンスを活かすべく、じっくりと“その先”を見据えて行動してゆきたい。

コメの小売価格の高止まりが続く。3月10日から16日までのスーパーにおける平均価格は5㎏あたり4,172円、1年前の2倍だ(農林水産省)。コメが店頭から消えたのは昨年の夏、当初、政府は「南海トラフ巨大地震注意の発出に伴う買いだめ、インバウンド、おにぎりブームによる需要増が要因であり、新米が店頭に並び始める秋口には落ち着く」と説明した。2024年の収穫量は2023年を22万トン上回った。しかし、価格は戻らない。この状況について「JA全農など大手の集荷量が21万トン減った(2024年末時点)。一部の卸業者による在庫調整の可能性もある」などとし、コメの需給バランスは全体として均衡しているとの立場を崩さなかった。
ただ、年明け後も状況は改善されず、2月に入ってようやく政府備蓄米21万トンの放出を決定、3月10日に第1回入札を行った。はたして「消えた21万トン」の原因が非農協系事業者による“売り渋り”であったとすれば、備蓄米の放出前に売り抜くのが自然だ。現時点でその兆候が見えないのは“更なる値上げ期待”があるのか、従来の政府説明に齟齬があるのか、そのいずれかということだ。
そもそも猛暑による高温障害のため2023年米は不足していた。需給は2024年上半期から既にタイトな状況にあった。そこに夏場の“想定外”の需要が重なったわけであるが、想定外とされた規模は収穫量比でせいぜい3%程度に過ぎない。この3%が“小売価格が倍になる”ほどの供給不足を招いた主因だとすれば、いかにぎりぎりの需給見通しの中で生産計画が立てられているかということだ。言い換えれば、コメ余りによる価格下落に対する過剰なまでの忌避がコメ行政の根底にあるということだ。
「減反」政策は2018年に廃止された。とは言え、主食用米から飼料用米に転作すれば転作奨励金がつくし、生産目標は政府の需給見通しをベースに都道府県単位で決定されている。需要の右肩下がりを所与の条件とし、補助金の効率を高めることを目指した減反思想が今も根付く。昨年改正された「食料・農業・農村基本法」は食料供給困難事態に対する施策として「輸入促進」を明記したが、平時の縮小均衡思想に縛られたまま主食であるコメの供給が困難となる事態を回避できるのか。食料安全保障は国が果たすべき責任の一丁目一番地だ。JAの在り方も含め、コメ行政の根本を今一度問い直す必要があろう。

3月11日、東日本大震災から14年が経った。死者行方不明者22,332人、全半壊の住宅被害406,157棟、社会基盤施設、ライフライン、建築物等の推計被害額16兆9000億円、災害救助法が適用された自治体は10都県241市区町村に及んだ。そして、現在にあっても27,615人もの人々が避難生活を強いられ、あの日、19時03分に発出された原子力緊急事態宣言が解除される見通しはない。被災は今も進行中である。
昨年度までに投じられた復興予算は約41兆円(執行見込額)、ハード面での事業は完了した。県内総生産も発災前を上回る。福島ロボットテストフィールドをはじめとするイノベーション拠点も整備された。しかし、かつてあった日常、そこにいるはずの多くの人は未だ戻っていない。失われた住宅と同数の災害公営住宅を建設することでコミュニティが再生されるわけではい。地域の復興は道半ばだ。
福島県主催の追悼復興記念式典に出席した石破首相は「世界一の防災大国を目指す」と宣言した。異論はない。とは言え、震災の2年後には国土強靭化基本法が成立、2018年には“地震・津波・土砂災害の防止”、“救助・医療の災害対応力の強化”、“食料・電力・通信をはじめとするライフラインの確保”など160項目がリストアップされ、2020年度までの3年間に7兆円を投じて「特に緊急に実施すべき対策を完了または大幅に進捗させる」との計画を公表している。はたしてその成果は検証されたのか。
東日本大震災は社会の在り方や私たち自身の生活価値観を根本から問い直す契機となったはずだ。しかし、この14年間、私たちはどう生きてきたのか。社会の何が変わったのか。昨年、“原発依存度の低減”が国の政策目標から消えた。国土強靭化対策も“能登”には間に合わなかった。2011年3月31日、当社は緊急レポート「東日本大震災における経済復興プロセスと主要産業に与える影響」を発表、“温存されてきた古い体質、棚上げされてきた課題を清算し新たなビジョンをもって日本を再興すること、これをもって復興の道筋とすべき”と提言した。そう、復興は未だ途上にある、ということだ。
ご参考:2011年3月31日にリリースした当社レポート『東日本大震災における経済復興プロセスと主要産業に与える影響』を無償でご提供させていただきます。
ご希望の方は、ホームページよりお申し込みください。
お申し込みの際、『お問い合わせ内容』に『東日本大震災における経済復興プロセスと主要産業に与える影響 希望』とご記入ください。順次ご提供させていただきます。
お申し込みはこちら
