
10月8日、新型コロナウイルスの世界の感染者数は3,580万人、死者は104万人を越えた。一旦は落ち着いたかに見えた欧州も再び感染が拡大、10月2日にはマドリード全域が封鎖された。ニューヨークも10月7日からブルックリンとクイーンズの9地区で再びロックダウンに入った。日本も一向に収まることなく今月初旬には8万5千人を突破、中国を抜いた。
一方、比較的早期に感染を押さえ込んだアジアも7月から9月にかけて第2波が懸念された。しかし、いずれも「感染爆発」には至らず、インド、フィリピン、インドネシアを除くと概ね落ち着きつつある。
経済産業省の日系海外現地法人四半期調査(4-6月期)によると、7-9月期に対するASEAN地域の “先行DI” は4-6月期の “現状DI” に対して+37.4ポイント、経済は急速に回復に向かうと予測された。当該期間における情勢を鑑みると恐らくこの見通しは間違っていないだろう。しかし、日本がそうであるようにコロナ禍はアジア各国の構造変化を加速させる。したがって、あらゆる社会、産業の質的な変化に備える必要がある。
当社はこの7月、中国、タイ、インドネシア、ベトナムの日系現地法人を対象に独自の緊急調査を実施したが、コロナ禍にあって現地法人が真っ先に取り組んだ施策はやはり「テレワークの導入」(53.9%)であった。
影響は “働き方” 改革に止まらない。アジアはもともとWi-Fiなどデジタルインフラの整備が早かったこと、加えて外出自粛等の施策が徹底されたことにより都市部のビジネス需要はもちろん、生活、教育、医療、金融、エンターテインメント領域におけるオンライン市場は日本以上に一挙に浸透、拡大した。
また、BCPの強化(32.6%)、販売先の多様化(24.8%)、仕入れ先・生産拠点の分散(23.4%)など脱中国の流れを背景とした “サプライチェーンの見直し” も急速に進展する。同時に、利益剰余金の積み増し(24.1%)、現地での研究開発体制の拡充(22.0%)など、これまで以上に “現地化” 戦略が強化される。
もちろん、現状では “買い手” としての中国を無視することは出来ない。しかし、下記グラフからも見てとれるように各国現地法人の駐在員は既に米中対立のその先を見据えている。
【アジアの日系現地法人駐在員が注目する地域】

出典:(株)矢野経済研究所「アフター・新型コロナ~アジア4か国の産業構造変化と成長市場」(2020年9月29日発刊)
“チャイナプラスワン” は新型コロナウイルスと米中対立を背景に急速に進むだろう。その受け皿の筆頭であるアセアン諸国は、これを契機にグローバルサプライチェーンにおける自国のポジションの強化をはかるとともに、自国産業の高度化、内需振興を目指す。今、アジアは大きな変革の途上にある。日系現地法人にとっても新たな、そして、無限のチャンスがそこにある。
※「アフター・新型コロナ~アジア4か国の産業構造変化と成長市場」の詳細はこちらへ
その他本調査に関する提供情報

29日、NTTは上場子会社NTTドコモの完全子会社化を発表、NTTグループは再び統合に向かう。所管官庁である総務省もこれを容認、1985年以来、旧電電公社の民営・分社化に象徴される規制緩和を通じて、成長と競争を促してきた通信産業政策は大きな転機を迎える。
会見では、国内トップシェアでありながら低収益に甘んじるNTTドコモに対する不満と反省も伺われたが、「世界レベルのダイナミックな環境変化に対応したい」(NTT澤田社長)、「NTTの強力な資産を活用し、グローバル競争力を高める」(NTTドコモ吉沢社長)など、次世代通信技術で先行する欧米や中国勢に対する危機感が強調された。
とは言え、完全子会社化すれば直ちに勝てるわけではない。GAFAに対抗し得るプラットフォームを現時点で築くことは不可能だし、基地局市場もファーウェイ、ノキア、エリクソンの3社が8割を押さえる。米中対立によって生じるファーウェイの隙をつくことで一定のシェアがとれたとしても、5G世代における周回遅れを解消するには至らない。
本命はNTTネットワーク基盤技術研究所が手掛ける光技術による大容量、低遅延、低消費電力の次世代無線ネットワーク、IOWN(アイオン:Innovative Optical & Wireless Network)構想のグローバル展開か。5Gのその先を見据えたオープン・ネットワークの可能性は技術的にも市場的にも大きい。NTTドコモの運用ノウハウと技術はその実装に欠かせない。ただ、同じく完全子会社である地域会社を抱え込んだままの大所帯で、大胆かつ迅速な意思決定が可能であろうか。
会見ではグローバル市場における競争相手が “非通信会社” であることの脅威が語られていたが、そうであれば巨大な既得権を擁するオールNTTの再現はむしろ足枷ではないか。次世代IT市場を勝ち抜くためには身内のパズル合わせを越えた次元での経営資源の補完と再配置が必須である。そのためにもまずはNTT自身が、34.69%を持たれている “霞が関” から自由になることが肝要だ。そうあってはじめて本物の革新が期待できる。

米中対立を背景とした政治による経済への介入に対して、経済の側から「待った」の声があがる。
21日、米EVテスラは、米中通商摩擦の中で課された中国からの輸入部品に対する課税の撤廃を求めて国際通商裁判所に提訴した。テスラはトランプ政権による経済報復措置として課された一連の関税は「違法」であると主張する。
その2日前、サンフランシスコ連邦地裁は、中国IT大手テンセントの対話アプリWeChatに対する「米国内での使用を20日付で禁止する」とした大統領令の執行を停止する仮処分を下した。米国憲法が保障する表現の自由を侵す懸念があるとの原告側の主張を認めた。
中国動画投稿アプリTikTokも「27日付で新規のダウンロードを禁止する」との大統領令の差し止め請求をワシントン連邦地裁に起こした。
内需の流出、雇用の喪失、課税逃れ、貿易赤字、不公正取引、格差の助長などグローバル経済がもたらした負の側面は各国に共通した課題である。もちろん、各国の産業政策や対外交渉の根底には安全保障という国益が含まれる。しかし、それゆえに経済的共存のための国際的なルールづくりが模索されてきたはずだ。
今、米中対立は確実にその一線を越えてきており、両国はともにその強権的な姿勢を崩さない。いずれにせよ経済という視点からは非生産的であり、合理的な企業活動を制限するものでしかない。
ただ、自国内での統制強化と近隣への権益拡大をはかる側が国際協調を主張し、自由と民主主義の盟主であったはずの側が自国第一主義をかざし国連に背を向けるという矛盾の中で、企業はどう行動すべきか。
16日、スウェーデンのアパレルH&Mは自らの経営判断で新彊ウイグル自治区を産地とする繊維の取引を停止すると発表した。企業にとって大切にすべき価値は何か、経営理念と行動原則は一致しているか、問われているのはコーポレートアイデンティティーの在り様そのものということだ。政治からの介入は回避し難い。しかし、「鷹は飢えても穂を摘まず」、せめてこうありさえすれば “企業の社会的責任” に対するリスクは最小化できるはずである。
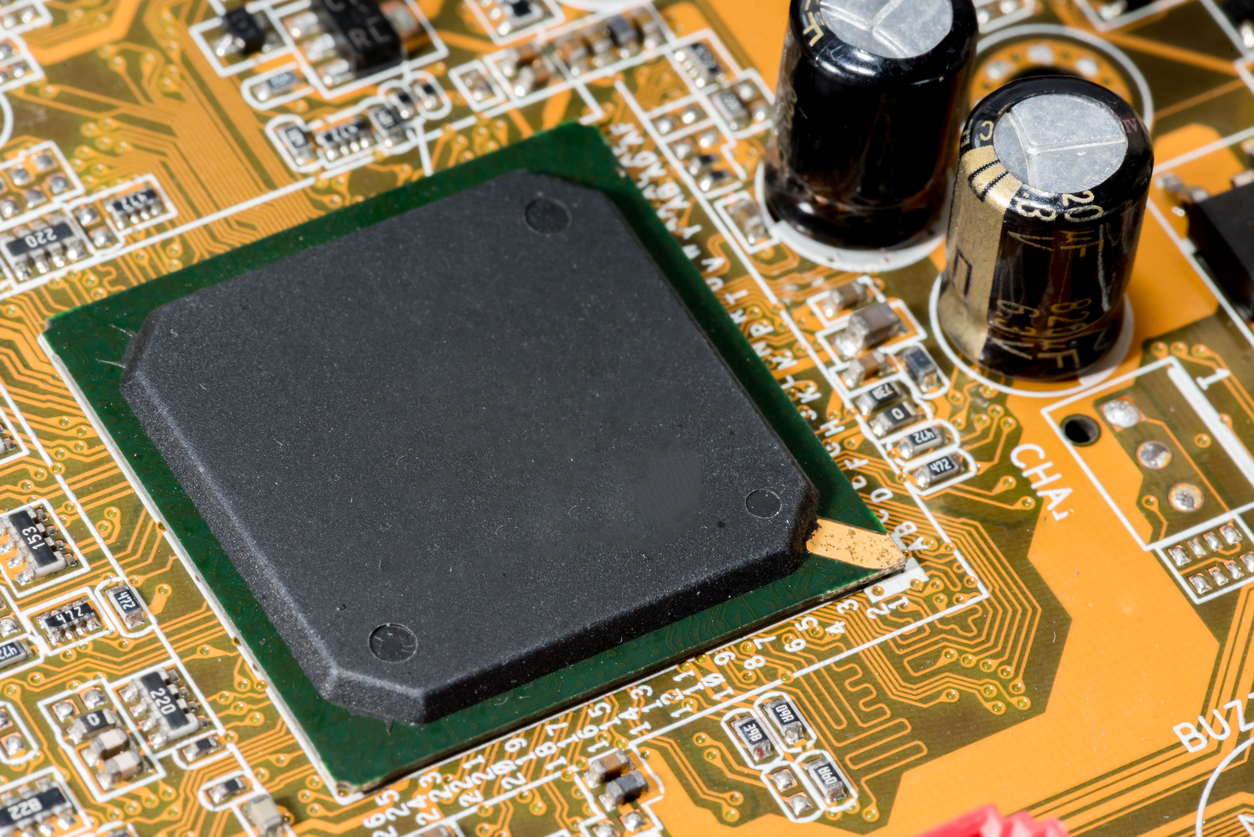
9月15日、華為技術(ファーウェイ)に対する米国の追加的な制裁措置が発効した。
米国は2019年に米国製半導体のファーウェイ向け輸出を禁止、この5月には米国企業の技術を使ったすべての製品供給の禁止を発表した。それでもこの時点では設計におけるファーウェイの関与が条件付けられていた。しかし、8月にはこの条件も外すことを決定、15日、これが発効した。結果、半導体製造子会社HiSilicon社からの調達も含め、ファーウェイへの米国製の技術が使われた半導体の供給が完全に閉ざされた。
今回、米国は各国の電子部品メーカーに対して「販売した自社製品が最終的にファーウェイに届いていないことを保証する義務」まで課している。子会社はもちろん関連会社や第3者を通じての迂回取引も見逃さない徹底ぶりだ。
ファーウェイを優良顧客としてきたサムスン電子、SKハイニックなどの韓国勢、そして、ソニー、キオクシア、三菱電機をはじめとする日本勢への影響は大きい。
一方、台湾は特需に沸いた。制裁措置の発効を前にファーウェイ向けの電子部品の駆け込み需要が集中、8月の海外輸出額が前年同月比8.3%増、311億7,000万ドルと史上最高額を更新した。
しかし、特需はむしろこれからだ。2019年、ファーウェイは世界のスマートフォン市場でアップルを抜いてサムスンに次ぐ2位に浮上した。しかし、ここが崩れる。上位3社を追うシャオミ、OPPO、そして、それに次ぐメーカーにとってもシェアを奪取するチャンスである。
ファーウェイ排除は5Gのインフラ市場の再編も促す。ファーウェイ、エリクソン、ノキアの3社で8割を占めるモバイルインフラ市場も揺らぐ。かつて、ここにはルーセント、ノーテル、モトローラといった名前があった。今、日本勢はそれぞれシェア1%にも届かないNECと富士通がかろうじて「その他」の一角を占めるに過ぎない。
6月、そのNECはNTTと提携、世界市場への再参入を目指すと発表、2030年には世界シェア20%を目指す、と宣言した。チャンスは政治がもたらした。しかし、両社においては官を頼ることなく、また、高品質=高価格を言い訳にすることなく、堂々と世界との勝負に勝ちにいっていただきたく思う。

ドイツ政府は意識不明のまま国内医療機関に搬送されたロシアの反政府指導者について「旧ソ連が開発した神経剤が使われた」との見解を発表した。EU、NATOもこれを強く非難、もちろん、ロシアは事実無根と否定する。
こうした中、ロシアとドイツを海底パイプラインで結ぶ天然ガス事業 “ノルドストリーム2” の中止論が現実味を帯びてきた。
ノルドストリーム2は対ロ安全保障の観点からこれまでも幾度となく見直し論が浮上した。米トランプ政権も建設関連企業に制裁措置を課す。ただ、総事業費1兆円を越えるプロジェクトの経済効果は大きく、また、脱石油、脱原発を進めるうえでの戦略インフラという背景もあり、政府は “政経分離” の方針を貫いてきた。しかし、今、ドイツ国内からも強硬論が広がる。
とは言え、もともと “政” の要請で始まったノルドストリーム2であっても、現時点で “経” の動きを止めるのは容易ではない。7日、ドイツ経済東欧委員会は「事業停止」に反対する立場を明確にした。事業にはヴィンターシャル(独)、ユニーパー(独)、ロイヤル・ダッチ・シェル(英蘭)、オーエムヴィー(オーストリア)、エンジー(仏)など、多くのエネルギー関連企業が参画する。影響はドイツ一国にとどまらない。
一方、メルケル氏は対中政策の転換も進める。2日、政府はインド・太平洋外交に関するガイドラインを閣議決定した。主張の骨子は「法の支配」の尊重であり、覇権主義を否定し、開かれた市場を重視し、自由と民主主義という基本的な価値観を共有する国との連携を強化する。すなわち、中国依存度の低減である。
しかし、こちらも簡単ではない。VW、ダイムラー、BMWは世界販売台数の3-4割を中国で占める。シーメンスはガスタービンの共同開発で国営企業と契約を締結、BASFも広東省の石油関連施設建設に100憶ドル規模の投資を表明している。政府は2017年に外国貿易管理法を改正し、以降、中国への技術流出を規制してきた。しかし、個々の企業つまり “経” にとっては14億人を有する世界第2位の経済大国に代わる市場はない、ということだ。
対ロ、対中、いずれも一筋縄ではゆかない。それでも関係の見直しに舵をきる。それほど “政”における基本的な価値観の相反が深刻になりつつある。
8日、欧米の製薬メーカー9社は新型コロナウイルスのワクチン開発に際して「安全性を最優先とし、医学の科学的・倫理的水準に従う」との共同宣言を発表した。つまり、政治的な圧力によって研究、臨床、承認のプロセスが歪められることはない、言い換えれば、“政” の “経” への介入を拒否する、と言うことだ。
そう、これこそが正しく “政経分離” であって、ドイツの方針転換は、“経”、すなわち、民の活動に不正に介入する政への加担を拒否する、ということである。
“政” と “経” は相手側のそれとの落としどころを見出すことが出来るのか。米中対立も一線を越えつつある中、世界で “政” と “経” が縺れ合う。

8月29日から31日にかけて中印が領土を争うカシミール地方ガルワン渓谷付近で、双方から「相手方が自国の実効支配線を越えた」との非難声明が発せられた。この地域では6月にも越境をめぐって両軍部隊が衝突、7月にはインドは仏製戦闘機5機を、8月には中国もステルス戦闘機2機を当該地域に配備するなど一触即発状態が続いている。
国境での紛争はモディ政権の “脱中国依存” を加速させる。モディ氏は「貿易赤字は “安価な中国製品の大量流入” が主因であり、これが国内製造業の発展を妨げている」と表明、中国企業の排除を進める。国境紛争を背景に大衆もこれを支持する。しかし、新型コロナウイルスの押さえ込みに失敗し、経済の停滞と感染拡大の悪循環が続く中、産業構造転換は足踏み状態にある。こうした状況のもとでの中国資本、中国製品のボイコットは雇用、消費にとって短期的にはマイナスだ。加えてインドの主力工業品である医薬品の原材料は依然として中国に依存しており、現時点で代替先はない。
中国はこうした隙を突く。ただ、いち早く新型コロナウイルスを乗り越えたはずの中国も経済のV字回復には懸念が残る。IMFは2020年の経済見通しについて「中国は主要国で唯一プラス成長が可能である」と予測するが、当の中国は5月に開催された第13期全人代で今年の経済成長に関する目標数値の公表を見送った。米との対立の行方など情勢は不透明である。
8月、習近平指導部は「双循環」という新たな経済ビジョンを表明した。“双” とは国内大循環と国外循環の両立という意味である。つまり、海外と連携しつつ内需主導に成長の軸足を移す、ということだ。国外を “一帯一路” と言い換えれば、つまり、米国との決裂を前提に世界のブロック化を覚悟した戦略、との解釈も成り立つ。であれば、香港、台湾、南シナ海、新彊、カシミールにおける強硬姿勢も頷ける。ただ、それが国際社会に対する牽制であるのか、覚悟であるのか、覚悟であるとしてもどこまでの覚悟なのか、本意は分からない。
今、世界はCOVID-19のワクチン開発に凌ぎを削る。そして、次に来る課題はその配分だ。ワクチンは世界の “陣営” を分けることになるのか、それとも、国際協調への回帰を導くのか、ここが分水嶺かもしれない。
